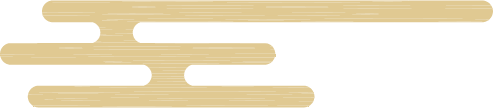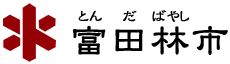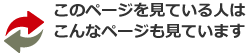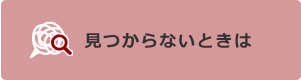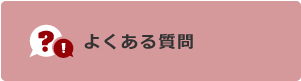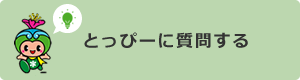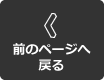児童扶養手当
児童扶養手当は、父母の離婚等により、父または母と生計を同じくしていない児童を育てている方に対し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
外国籍の方についても支給の対象となります。
支給対象
次のいずれかの要件に該当する児童を監護する母、児童を監護し、かつこれと生計を同じくする父、または父や母に代わって児童を養育(児童と同居、監護し、生計を維持)している方(以下養育者)が受給できます。
なお、この制度でいう「児童」とは、18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童をいい、児童に政令で定める程度の障がいがある(特別児童扶養手当を受給している)場合は、20歳未満の児童をいいます。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで出産した児童
- 父または母がDV防止法(※)による保護命令を受けた児童
※DV防止法…「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」
ただし、上記の場合であっても次のいずれかに当てはまる場合は、受給することができません。
- 父、母、養育者または児童が日本国内に住所を有しないとき
- 児童が里親に委託されているとき
- 父または母の配偶者に養育されているとき(配偶者には、内縁関係にある者を含みます。ただし、政令で定める程度の障害の状態にある者を除きます)
- 児童が児童福祉施設等に入所しているとき(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)や、少年院・少年鑑別所などに収容されているとき
- 受給者または児童が死亡したとき
- 受給者または児童の在留期間が切れてしまい、「在留資格なし」になったとき
支払日
手当は認定されると、請求日の属する月の翌月分から支払われます。
支払日は奇数月(11月、1月、3月、5月、7月、9月)の各11日となり、それぞれの支払月の前月分までの手当を、認定請求時に指定いただいた口座に振り込みます。
ただし、11日が土曜日・日曜日・祝日等の金融機関休業日にあたるときは、その直前の金融機関営業日が支払日となります。
支給額
手当額は、請求者または配偶者及び扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹など)の前年の所得(1月から9月の間に請求される場合は、前々年の所得)によって、全部支給、一部支給、全部停止(支給なし)のいずれかに決まります。
毎年11月1日から翌年の10月31日までを支給年度として、年単位で手当の額を決定します。
毎年8月に現況届を提出していただき、児童の監護状態や前年の所得や養育費等を確認したうえで、11月分(翌年1月支払分)以降の手当の額等を決定します。
| 対象児童数 | 全部支給 | 一部支給 |
|---|---|---|
| 1人目 | 46,690円 | 46,680円~11,010円 |
| 2人目以降 |
11,030円を加算 |
11,020円~5,520円を加算 |
※令和7年4月分からの対象児童1人あたりの月額を示しています。
※令和6年11月分より第3子目以降の児童に係る加算額が第2子目と同様に引き上げとなりました。
※手当の月額は「物価スライド制」の適用により変動することがあります。
所得制限
請求者または配偶者及び扶養義務者の所得額と下表の額を比較して、全部支給、一部支給、全部停止(支給なし)のいずれかに決定されます。
|
|
父、母または養育者 |
孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者の |
|
|---|---|---|---|
|
扶養親族等の数 |
全部支給の |
一部支給の |
|
|
0人 |
69万円未満 |
208万円未満 |
236万円未満 |
|
1人 |
107万円未満 |
246万円未満 |
274万円未満 |
|
2人 |
145万円未満 |
284万円未満 |
312万円未満 |
|
3人 |
183万円未満 |
322万円未満 |
350万円未満 |
|
4人 |
221万円未満 |
360万円未満 |
388万円未満 |
|
5人 |
259万円未満 |
398万円未満 |
426万円未満 |
※令和6年11月分より所得制限限度額が引き上げとなりました。
〔※1〕所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族または特定扶養親族がある場合には上記の額に次の額を加算した額となります。
- 「父、母または養育者」の場合
(1)老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円
(2)特定扶養親族1人につき15万円 - 「孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者」の場合
老人扶養親族1人につき6万円(扶養親族等の全員が、老人扶養親族の場合は1人を除く。)
〔※2〕扶養親族等の数が6人以上の場合には、1人につき38万円(扶養親族等が上記の〔※1〕の場合はそれぞれ加算)を加算した額となります。
公的年金等との併給
公的年金等を受給している場合、または児童扶養手当認定後に受給できるようになった場合は、届出が必要です。
公的年金等を受給できる可能性がある場合は、必ず担当窓口までご相談ください。
届出が遅れると、手当の返還が必要となる場合があります。
※平成26年12月1日以降、公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金等)を受給していても、その額が児童扶養手当の額より低い場合には、差額分の手当が受給できるようになりました。
※児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分(令和3年5月支払分)以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算額部分を上回る場合、その差額を手当として受給できるようになりました。
認定請求
担当窓口で必要な書類等を確認・相談の上、手続きをしてください。
(すべての必要書類がそろってから申請の受理となります。)
状況に応じて必要書類が異なる場合がありますので、必ず事前にご相談下さい。
受給資格についての審査後、認定となった場合、手当は請求日の翌月分からの支給となります。
現況届
法律に基づき、児童扶養手当の受給資格者は、毎年8月1日~31日の間に「児童扶養手当現況届」の提出が必要となります。
毎年8月1日頃までに郵送されてくる案内に記載の説明文をご確認いただき、手続きをお願いします。
この手続きを行わないと、11月分(翌年1月支払分)以降の手当が受けられなくなりますので、必ず期限内にお手続きください。
なお、現況届は受給資格者ご本人様がお手続きいただく必要がありますので、ご注意ください。
郵送や、委任状等での代理人による手続きはできません。
一部支給停止適用除外事由届出書
以下の要件に該当される方は、就労・求職の状況あるいは障がい・病気・家族介護等により就労が困難な状況について届出いただく必要があります。
届出が無い場合は手当の支給額が約2分の1となりますので、郵送されてくる案内に記載の説明文をご確認いただき、期限までに手続きをお願いします。
- 児童扶養手当の支給開始月の初日から起算して5年
- 手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年を経過したとき
(法第6条第1項の規定による認定の請求をした日において3歳未満の児童を監護する受給資格者にあっては、この児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したとき)
その他届出
受給資格がなくなった場合(婚姻(事実婚を含む)や児童を監護しなくなった場合など)には、「資格喪失届」の提出が必要となります。
受給資格がないにもかかわらず受給された手当は一括返還していただくことになりますので、お早めにお手続きください。
また、住所を変更した場合や、世帯構成等に変化があった場合は、状況に応じた届出が必要となります。
詳しくは、担当窓口へお問い合わせください。
関連リンク
- 児童扶養手当について - こども家庭庁<外部リンク>
お問い合わせ先(担当窓口)
こども政策課 給付支援係 児童扶養手当担当
電話:0721-25-1000(内線283)