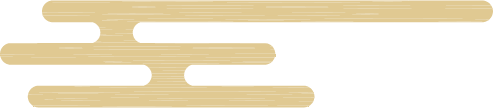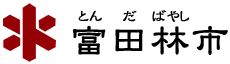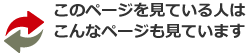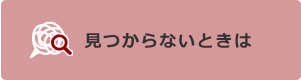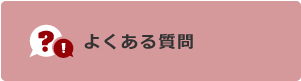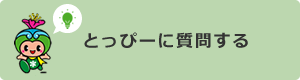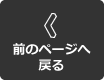介護サービスにかかる費用
介護保険を利用してサービスを受けるときは、利用者が費用の一部を負担していただくことになります。また、費用が高額になる場合はその一部が支給されます。
施設を利用する場合は所得などの状況により、食費や居住費の負担の減額を受けることができる場合があります。
利用者負担割合
介護保険の利用者負担は原則として、サービスにかかった費用の1割から3割※のいずれかです。
※65歳以上で一定以上の所得がある人は利用者負担が2割または3割になります。2割ないし3割負担となる人は、所得基準によってかわります。
一定以上所得者とは
2割負担となる人
3割の対象とならない人で、本人の合計所得金額が160万円以上かつ同じ世帯の65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯で280万円以上、2人以上世帯346万円以上の人です。
3割負担となる人
本人の合計所得金額が220万円以上かつ同じ世帯の65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯で340万円以上、2人以上世帯463万円以上の人です。
介護保険負担割合証
介護保険が必要な状態であると認定を受けた方に対し、介護保険負担割合証が交付されます。住所や氏名、利用者負担の割合などが記載されています。
介護保険負担割合証は、介護保険被保険者証とは異なります。
区分支給限度基準額
在宅で介護保険のサービスを利用する場合、要介護状態区分ごとに、1か月に給付を受けられる限度額が定められています。利用者負担は原則としてサービスにかかった費用のうち負担割合証(1割から3割)に記載された割合です。
| 要介護状態区分 | 区分支給限度基準額 |
|---|---|
| 要支援1 | 50,320円 |
| 要支援2 | 105,310円 |
| 要介護1 | 167,650円 |
| 要介護2 | 197,050円 |
| 要介護3 | 270,480円 |
| 要介護4 | 309,380円 |
| 要介護5 | 362,170円 |
※交付日が令和元年9月30日以前の介護保険被保険者証には、改正前の区分支給限度基準額が記載されていますが、改正後の区分支給限度基準額に読み替えて使用することができます。
高額介護サービス費
同じ月に利用したサービスの利用者負担(1割から3割)の合計額(同じ世帯内に複数の介護サービス利用者がいる場合には、その合算額)が高額になり、利用者負担上限額を超えたときは、超えた分が申請により払い戻されます。
ただし、福祉用具購入費と住宅改修費の自己負担分、食費・居住費(滞在費)、その他施設における日常生活費、特別なサービスの費用等は払い戻しの対象とはなりません。
利用者負担上限額の判定は、サービス利用月ごとに、その初日の世帯の課税状況で判断されます。
対象となる方には、高齢介護課より支給申請書を送付しますので、必要事項を記入の上、提出してください。翌月以降の支給については、申請の必要はなく、初回に指定された口座に自動的に振り込まれます。
※課税状況や所得状況に変化があり、ひと月当たりの利用者負担上限額が変わると、追加給付や差額の返還請求を行う可能性があります。また、サービス費請求情報が変更になった場合も同様に追加給付や差額の返還請求を行いますので、ご了承ください。
利用者負担上限額(1ヶ月に本人が負担する金額の上限)
<令和3年8月1日から>
|
利用者負担段階区分 |
利用者負担上限額 | |
|
住民税課税世帯 |
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の世帯 |
140,100円(世帯) |
|
課税所得380万円(年収約770万円)以上 課税所得690万円(年収約1,160万円)未満の世帯 |
93,000円(世帯) | |
|
課税所得380万円(年収約770万円)未満の世帯 |
44,400円(世帯) | |
| 住民税非課税世帯 |
課税年金収入とその他の合計所得金額の合計が年額80万円超の方 |
24,600円(世帯) |
|
課税年金収入とその他の合計所得金額の合計が年額80万円以下の方 |
24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
|
|
老齢福祉年金受給者、生活保護受給者 |
15,000円(個人) | |
受領委任払いについて(施設入所・入院のみ)
受領委任払いとは、施設への支払いをあらかじめ利用者負担上限額とすることで、高額介護サービス費の払い戻し手続きが省略できる支払い方法です。
介護保険施設に月の初日から末日まで1ヶ月以上継続して入所・入院されている場合は受領委任払いの制度を利用することができますので、希望される方は入所・入院中の施設にご相談ください。
施設利用時の食費・居住費(滞在費)について〈負担限度額認定証〉
介護保険施設での入居・滞在・入院にかかる食費と居住(滞在)費は、保険給付の対象外ではありますが、所得状況によって負担の軽減(補足給付)を受けられる場合があります。
申請から利用方法について
利用者負担段階が第1~3段階(2)に該当し、施設入所・入院、または短期入所(ショートステイ)を利用される方は、高齢介護課で「介護保険負担限度額認定証」(以下、認定証)の申請をしてください。
所得及び資産状況を審査後、給付対象となった方には認定証を発行します。施設サービスを利用の際には、必ず認定証を施設に提示してください。提示されないと補足給付を受けられませんので、ご注意ください。
※認定証は申請のあった月の初日から有効となりますが、月を遡ることはできません。
例)4月30日に申請→4月1日から有効 5月1日に申請→5月1日から有効(4月への遡りは不可)
※通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション等には使えません。
※毎年更新手続きが必要です。
申請に必要なもの
(1)介護保険負担限度額認定申請書 [PDFファイル/407KB]
※両面印刷でのご提出をお願いします。
(2)本人および配偶者の名義の全ての通帳の写し等
※詳細は負担限度額認定申請にかかる添付書類について [PDFファイル/447KB]をご確認ください。
負担限度額認定の要件
<令和3年8月1日から>
|
世帯の課税 及び資産状況 |
所得状況 |
補足 給付 |
利用者 負担段階 |
|
本人、配偶者(※1)を含め、 世帯全員が市民税非課税 かつ、基準(※2)を超えた 預貯金等がない。 |
老齢福祉年金受給者、生活保護受給者 |
対象 | 第1段階 |
|
本人の課税年金収入額と非課税年金収入額とその他の 合計所得金額特別控除後の合計が年額80万円以下の方 |
第2段階 |
||
|
本人の課税年金収入額と非課税年金収入額とその他の合計 所得金額特別控除後の合計が年額80万円超120万円以下の方 |
第3段階(1) |
||
|
本人の課税年金収入額と非課税年金収入額とその他の 合計所得金額特別控除後の合計が年額120万円を超える方 |
第3段階(2) |
||
|
本人、配偶者(※1)もしくは世帯員が市民税を課税されている。 基準(※2)を超えた預貯金、有価証券、金銀などの時価評価額が把握できる貴金属、 投資信託、現金等を所有している。 |
対象外 |
標準 |
|
(※1)世帯分離をしていても、配偶者の所得及び資産を勘案して判定します。配偶者とは事実上の婚姻関係を含みます。
(※2)基準金額は以下の通りです。虚偽の申告で補足給付を受けた場合、決定の取り消しや罰則規定があります。
| 第1段階・2号被保険者 |
預貯金等が単身1,000万円、夫婦2,000万円を超える場合 |
| 第2段階 |
預貯金等が単身650万円、夫婦1,650万円を超える場合 |
| 第3段階(1) |
預貯金等が単身550万円、夫婦1,550万円を超える場合 |
| 第3段階(2) |
預貯金等が単身500万円、夫婦1,500万円を超える場合 |
利用者負担額のめやす(居室の種類や施設の食費設定金額によって異なる場合があります。)
<令和6年8月1日から>
介護保険施設等における居住費の負担限度額が令和6年8月1日から変わります(周知用リーフレット) [PDFファイル/253KB]
| 利用者負担段階 |
居住費等 |
食費 | ||||
| ユニット型個室 |
ユニット型 個室的多床室 |
従来型個室 | 多床室 |
施設 サービス |
短期入所 サービス |
|
|
第1段階 |
880円 | 550円 |
550円 (380円) |
0円 | 300円 | 300円 |
|
第2段階 |
880円 | 550円 |
550円 (480円) |
430円 | 390円 | 600円 |
|
第3段階(1) |
1,370円 | 1,370円 |
1,370円 (880円) |
430円 | 650円 | 1,000円 |
|
第3段階(2) |
1,370円 | 1,370円 |
1,370円 (880円) |
430円 | 1,360円 | 1,300円 |
|
標準 |
2,066円 | 1,728円 |
1,728円 (1,231円) |
437円 (915円) |
1,445円 | 1,445円 |
※( )内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用とした場合の金額です。
社会福祉法人等による利用者負担軽減制度
介護保険サービスを利用するとき、利用者はサービス費用の一部を負担することになっていますが(利用者負担の原則)、社会福祉法人または市町村が経営する社会福祉事業体の提供するサービスについては、低所得者に対する利用者負担の軽減制度があります。(但し、利用者負担軽減実施を届け出ている法人等に限る。詳しくはサービス事業者にご確認ください。)
対象となるサービス
- 訪問介護(ホームヘルプ)・訪問介護相当サービス・訪問型サービスA
- 通所介護(デイサービス)・通所介護相当サービス・通所型サービスA
- 短期入所生活介護(ショートステイ)
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護※
- 夜間対応型訪問介護※
- 認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護※
- 看護小規模多機能型居宅介護※
- 介護老人福祉施設サービス※
※印は要介護の認定をお持ちの人のみ
対象となる利用者負担
- 介護サービス費の1割分
- 対象サービス利用時の食費・居住費(滞在費)・宿泊費(特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)
※入所の方は利用者負担段階により異なりますので詳しくは高齢介護課までお問い合わせください
※生活保護受給者は個室の居住費及び滞在費のみとなります。
軽減の程度
利用者負担の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)
※生活保護受給者等については、利用者負担の全額
有効期間
申請月の初日から7月末日まで
※毎年更新手続きが必要です。
要件
生活保護受給者及び市民税非課税世帯で、次の要件すべてを満たす人のうち、収入や世帯の状況等から生計が困難である人。
- 年間収入が、単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること
- 預貯金等の額が、単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること
- 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと
- 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
- 介護保険料を滞納していないこと
※ここで言う世帯とは、住民票の同一世帯です。また、世帯員とは申請者と同じ世帯に属する人です。世帯状況が不明な場合は、住民票で確認できます。
申請の方法
「社会福祉法人等による利用者負担軽減対象確認申請書」、「収入等申告書」を記入し、高齢介護課窓口で申請してください。申請には次のものが必要です。
※申請を希望される方は、予め高齢介護課へご相談ください。
添付書類
- 前年中の収入額がわかるもの(源泉徴収票、年金支払通知書、給与明細等)
- 預貯金額がわかるもの(通帳等、お持ちの口座すべて)
※1、2はすべての世帯員について必要です。
※1について、書類がなく、通帳で確認できる場合は1年間に受け取った金額がわかる箇所を用意してください。
認定結果が出るまで
申請受付後、預貯金額を規定の金融機関に問い合わせます。金融機関から回答が返ってくるまでに時間を要するため、結果が出るまで2か月程度かかります。その間、サービスは利用できますが、請求事務に関係しますので、軽減制度の申請中であることを必ずケアマネジャーに連絡してください。
介護保険利用者負担額助成(市独自利用料減免)
介護保険サービスの利用者負担を支払うこと著しく生活が困難となる低所得者に対して、その一部を助成することでサービスの利用を促進するとともに市民生活の安定を図るため、市独自の利用料減免の制度です。
対象となるサービス
- 居宅サービス(特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、特定福祉用具購入、住宅改修を除く)
- 小規模多機能型居宅介護
- 看護小規模多機能型居宅介護
- 地域密着型サービス
※介護予防サービスを含む
要件
次の要件すべてを満たす人のうち、収入や世帯の状況等から生計が困難である人。
- 年間収入102万円、世帯員が1人増えるごとに57万円を加算した額以下であること
- 預貯金等の額が、単身世帯で102万円、世帯員が1人増えるごとに57万円を加算した額以下であること
- 世帯が不動産を所有していないこと(ただし、居住用地にあっては100平米以下、居住用家屋にあっては総床面積120平米以下のものを除く)
- 世帯が自動車を所有していないこと(ただし、通院または生活維持のために限定的に運用される自動車を除く)
- 世帯に住民税または所得税の課税者がいないこと
- 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
- 介護保険料を滞納していないこと
申請の方法
「介護保険利用者負担額助成認定申請書」、「収入等申告書」、「資産申告書」を記入し、高齢介護課窓口で申請してください。申請には次のものが必要です。
※申請を希望される方は、予め高齢介護課へご相談ください。
- 前年中の収入額がわかるもの(源泉徴収票、年金支払通知書、給与明細等)
- 預貯金額がわかるもの(通帳等、お持ちの口座すべて)
※1、2はすべての世帯員について必要です。
※1について、書類がなく、通帳で確認できる場合は1年間に受け取った金額がわかる箇所を用意してください。
認定の有効期間
申請月の初日から7月末日まで
※毎年更新手続きが必要です。
助成金の額
利用者負担額(一割負担から社会福祉法人軽減後)の2分の1。
※高額介護サービス費の給付がある場合は、その額を控除した後に助成する。
助成申請と認定の流れ
1.認定申請をする。
「介護保険利用者負担額助成認定申請書等の必要書類を記入し、添付書類を添えて、市へ申請します。
2.認定の結果を受け取る。
市は、預貯金、資産及び収入状況等の調査を行ったうえで要件を審査し、結果を通知します。(審査には2か月程度かかります。)
3.月々の支払いの助成金を請求する。
助成の認定を受けた人は、月ごとにサービスを利用した翌月末までに、「介護保険利用者負担額助成申請書」と該当するサービスの領収証を添えて市に申請します。
4.助成金の支払い
市は、サービス事業者からの実績との突合により、助成額等を審査し、助成金を指定口座に振り込みます。