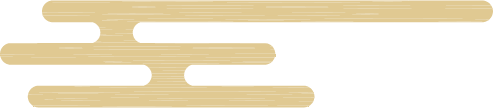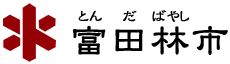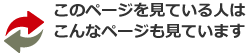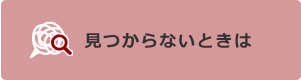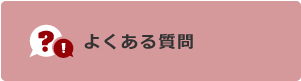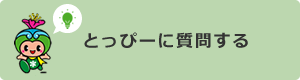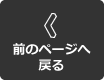児童手当の抜本的拡充について(令和6年10月分から)
令和5年12月22日に閣議決定された「こども未来戦略」で掲げる「こども・子育て支援加速化プラン」に基づき、児童手当の抜本的拡充が実施されることとなりました。これにより、令和6年10月分からの児童手当が以下のとおり変わります。
拡充後(令和6年10月分以降)の手当の初回支給月は、令和6年12月です。
児童手当の抜本的拡充による変更点
| 拡充前〈令和6年9月分まで〉 | 拡充後〈令和6年10月分から〉 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支給対象 | 中学校修了まで (15歳年度末まで) |
高校生年代まで (18歳年度末まで) |
|||||||||||||||||||||
| 所得制限 |
以下、所得制限限度額・所得上限限度額表のとおり
※扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上のものに限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。 |
所得制限なし |
|||||||||||||||||||||
| 手当月額 |
受給者(請求者)の所得が、 A.所得制限限度額未満の場合 A.所得制限限度額以上B.所得上限限度額未満の場合 B.所得上限限度額以上の場合
※児童一人当たりの月額を示しています。 |
以下、月額表(拡充後)のとおり
※児童一人当たりの月額を示しています。 |
|||||||||||||||||||||
| 多子加算 算定対象 |
中学校修了後18歳年度末までの子 | 18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子 | |||||||||||||||||||||
| 支給月日 | 6月、10月、2月の各5日 ※5日が金融機関休業日の場合はその直前の営業日 |
偶数月の各10日 ※10日が金融機関休業日の場合はその直前の営業日 |
1. 支給対象の拡大
児童手当の支給対象が、中学校修了まで(15歳年度末まで)の児童を養育している方から、高校生年代まで(18歳年度末まで)の児童を養育している方に変わります。
あわせて、多子加算の算定対象(第○子としてカウント可能な子)となる年齢も、22歳年度末までの子に引き上げられます。
多子加算の算定方法の見直しについて
- 18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子であって、その親等の児童手当受給者に経済的負担がある場合(留学中も含む)は、進学・就職等の状況や同居別居にかかわらず、上の子(第○子)としてカウントします。
- 経済的負担の有無については、「監護相当・生計費の負担についての確認書」による申立てが必要です。また、申立ての内容に疑義が生じた場合等は、その他の書類の提出を求める場合があります。
2. 所得制限の撤廃
従来の所得制限限度額および所得上限限度額が撤廃されます。これにより、特例給付の支給区分が廃止となり、受給者や配偶者の所得によらず、全員が児童手当の本則給付となります。
また、受給者や配偶者の所得が所得上限限度額を上回ったことにより、受給資格が消滅することもなくなります。
3. 多子加算(第3子加算)の増額
3歳以上小学校修了前の児童だけでなく、支給対象年齢のすべての児童が多子加算の対象となります。
多子加算の対象となった場合の児童一人当たりの手当月額も、15,000円から30,000円へ増額されます。
4. 支給月および支給回数の変更
6月・10月・2月の年3回(前月までの4ヶ月分をまとめて支給)から、偶数月の年6回(前月までの2ヶ月分をまとめて支給)へ変更されます。
あわせて、支給日も各月5日から各月10日となります。
※支給日が金融機関休業日の場合はその直前の営業日となります。
各種手続き
| 説明 | 必要な手続き | |
|---|---|---|
| 新たに受給資格が生じる方 | (1) 受給資格者の所得が所得上限限度額以上(=拡充前の対象外所得者)の場合 | 認定請求 |
| (2) 受給資格者が中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している場合 | ||
| (3) 施設等受給資格者で、高校生年代の児童のみが委託等されている場合 | ||
| 受給額が増額する方 | (4) 受給者の所得が所得制限限度額以上所得上限限度額未満(=拡充前の特例給付受給者)の場合 | なし |
| (5) 受給者が中学生以下の児童と高校生年代の児童をともに養育している場合 | なし | |
| (6) 受給者が現行制度において既に多子加算を受けている場合 ※(8)の場合を除く | なし | |
| (7) 受給者が新たに多子加算を受けることとなる場合 ※(8)の場合を除く | なし | |
| (8) 受給者に、新たに多子加算の算定対象となる18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子がいる場合 | 確認書提出 | |
| (9) 施設等受給者で、委託等されている児童の中に高校生年代の児童がいる場合 | 額改定請求 |
- 新たに受給資格が生じる方や、受給額が増額する方のうち、上表の(8)(9)に該当する方は、書類の提出等の手続きが必要です。
手続きが必要となる見込みの方へは、令和6年8月下旬から9月上旬にかけて、市から制度改正のお知らせと必要書類を郵送しています。 - 受給額が増額する方のうち、上表の(4)~(7)に該当する方は、手続きは不要です。令和6年8月下旬から9月上旬にかけて、制度改正のお知らせのみ郵送しています。
また、令和6年10月分以降の手当の支給日までに順次、市から額改定(増額)通知を郵送します。 - 公務員(独立行政法人、派遣出向職員を除く)の方の児童手当は、勤務先から支給されます。公務員の方の手続き等については、勤務先へご確認ください。
- 認定請求書等の書式は、担当窓口(富田林市役所4階 20番窓口)でもご用意しています。
その他
-
令和6年8月1日時点で以下のいずれかに該当する方には、順次、制度改正のお知らせや、手続きに必要な書類等を郵送しています。(手続きの必要がない方にも制度改正のお知らせは郵送します。)
- 児童手当または特例給付の受給者である方
- 本市に住民票があり、令和4〜6年度に受給者または配偶者の所得が所得上限限度額を超過したことにより、児童手当もしくは特例給付の受給資格が消滅した方
- 本市に住民票がある高校生年代(平成18年4月2日〜平成21年4月1日生まれ)の児童の保護者の方(※児童の住所宛てに郵送します。)
- 令和6年10月1日以降の認定請求について、支給開始年月が令和6年9月以前の場合は、拡充前の制度を適用します。
- 本市への認定請求書等の提出期限は、令和7年1月31日(金曜日)です。
令和7年1月31日(金曜日)以降にご提出いただいた場合、手当の支給が遅れることがあります。
※ 最終の提出期限は、令和7年3月31日(月曜日)です。最終の提出期限を過ぎてご提出いただいた場合は手当が不支給となる期間が発生しますので、ご注意ください。
よくある質問(Q&A)
Q.児童手当が拡充(制度改正)されるのはいつですか。
A.令和6年10月1日に改正法が施行され、令和6年10月分から適用されます。拡充後(令和6年10月分以降)の手当の初回支給日は、令和6年12月10日(火曜日)です。 ただし、手続きの時期によっては、支給が遅れる場合があります。
Q.多子加算とは何ですか。
A.「多子加算(第3子加算)」とは、受給者が22歳年度末までの子どもを3人以上養育している場合に、3人目以降の児童手当額を増額するものです。なお、令和6年度における「22歳年度末までの子ども」とは、平成14年4月2日以降生まれの子どもを指します。
※大学生年代の子がいる場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
Q.高校生年代の子どもで、すでに就職している場合も児童手当の支給対象になりますか。
A.高校生年代までの児童が就労収入を得ていたり、受給者と別居している場合であっても、受給者がこの児童を監護しており、かつ、生計を同じくしている場合には、児童手当の支給対象になります。ただし、児童が受給者と別居している場合は、定期的な面会・連絡をしている等の監護の実態について「別居監護申立書」による申立てが必要です。
Q.18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子どもで、すでに就職している場合も多子加算の算定対象になりますか。
A.18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子どもが就労収入を得ていたり、受給者と別居している場合であっても、学費や生活費の一部を受給者が負担している場合には、多子加算の算定対象になります。ただし、「監護相当・生計費の負担についての確認書」による申立てが必要です。
Q.22歳年度末までの子どもが3人未満の場合でも、「監護相当・生計費の負担の確認書」の提出が必要ですか。
A.22歳年度末までの子どもが3人未満の場合は、多子加算の算定対象とならず、手当額に影響しないため、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出は必要ありません。
関連リンク
- 児童手当
- 児童手当 - こども家庭庁<外部リンク>
- こども未来戦略(リーフレット等) - こども家庭庁<外部リンク>
お問い合わせ先(担当窓口)
こども政策課 給付支援係 児童手当担当
電話:0721-25-1000(内線205)