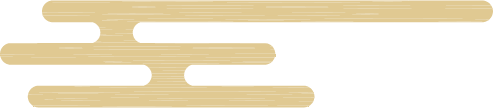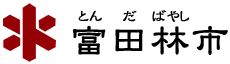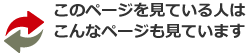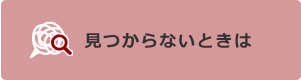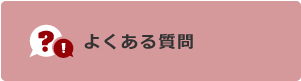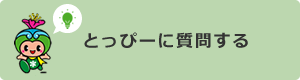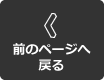伝統工芸品【大阪金剛簾】


【事業者】 杉多製廉簾株式会社<外部リンク>
万葉のはるか昔から受け継がれる日本の和の文化 【大阪金剛簾】
日本の簾の起源は飛鳥、奈良時代とされ、平安時代の宮中等の間仕切りや装飾に使用された御翠簾(おみす)が、現在の御座敷簾の原型と言われています。
大阪金剛簾の元となる簾づくりは、江戸時代の明暦年間に富田林の新堂村で竹籠づくりから始まり、簾づくりも行われるようになったと伝わっています。金剛山麓や富田林で良質の竹に恵まれた事が原因であり、天然の素材を生かした優雅で格調高い簾は、日本的な風流さを備えています。
1960年頃に簾産業は全盛期を迎え、1985年に大阪府知事から「大阪の伝統工芸品」の指定を受け、1996年に通商産業大臣(現:経済産業大臣)より「大阪金剛簾」の名称で「伝統的工芸品」の認定を受け、本市の伝統産業として継承されています。
伝統と現代の融合
杉多製廉株式会社は、伝統的な技術を大切にしながら、現代のインテリアにも調和するデザインを取り入れた簾も制作しています。
伝統の技と現代の感性が融合した大阪金剛簾は、時を超えて多くの人々に愛されています。


生産者からのメッセージ
「お座敷簾」は熟練の職人が一つひとつ心を込めて作り上げる伝統的工芸品です。
その閑静な佇まいの中に優雅で格式高いお座敷簾がやすらぎと夏の「涼」をお届けします。上品な色合いと生き生きとした表情が特徴で、見ているだけで涼やかな気持ちにさせてくれます。
かつて皇居をはじめ、将軍・大名・豪商の権威をあらわす装具としての「お御簾」、夏に涼しさを招き、夏の風物詩として愛用され発展してきた「お座敷簾」。
この美しい日本の伝統を守り続けるため、弊社は簾作り一筋に「簾の文化」を未来へと伝えていきます。
寄附者様へのメッセージ
富田林市の伝統工芸品「大阪金剛簾」を通じて、日本の美と涼を感じてみませんか?
寄附を通じて、この素晴らしい伝統を支え、未来へと繋げるお手伝いをしてください。
あなたのご支援が、伝統工芸の継承と発展に大きな力となります。
簾おすすめ返礼品
-
お座敷簾No.21 幅約88cm×高さ約172cm 日本製 1枚
- 【室内用】和風ブラインド 本麻 白・茶(幅約88cm×高さ約170cm)
🔍お礼品を探す
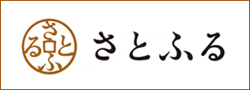 <外部リンク>
<外部リンク>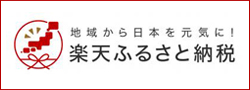 <外部リンク>
<外部リンク> <外部リンク>
<外部リンク> <外部リンク>
<外部リンク>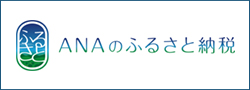 <外部リンク>
<外部リンク> <外部リンク>
<外部リンク> <外部リンク>
<外部リンク>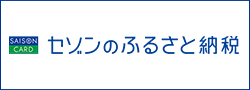 <外部リンク>
<外部リンク> <外部リンク>
<外部リンク>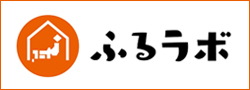 <外部リンク>
<外部リンク>