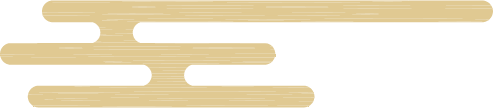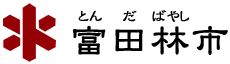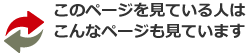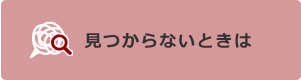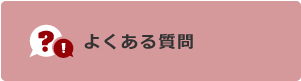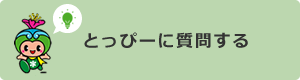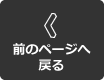空き家問題に関するよくある質問
空き家の近隣の方へ
空き家を適切に管理する責任は、空き家の所有者等(所有者又は管理者)にあります。
近隣同士の問題は、たとえそれが空き家であったとしても、民々の問題ですので、原則として当事者の間で解決していただくことになります。
所有者等の連絡先をご存知であれば、直接、当事者同士で話し合いをしてください。
連絡先は、自治会や近所で交流のあった人などが把握している場合も少なくありません。
ぜひ一度、ご近所で聞き取りをしてください。
なお、隣の空き家の所有者が不明の場合は、法務局(富田林市の管轄は大阪法務局富田林支局<外部リンク>)で登記事項を閲覧すれば所有者がわかります。複雑な場合は、弁護士や司法書士等の専門家に相談しましょう。
市では、所有者などに対して「適切な管理のお願い」をしていますが、このお願いには強制力が伴いません。空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく措置は、空き家を放置することが著しく公益に反する場合(倒壊により公道の通行人に著しい危険が及ぶ場合など)に限り行うものです。
隣地の空き家トラブル対応は、民法に基づく民事的手法が、解決への一番の近道です。
地域の中でのトラブルは、発生してから対策を考えていては問題が大きくなり、解決も困難となります。ご近所の方と繋がりを持つことで解決できるトラブルもありますので、日ごろから声を掛け合ったり、連絡先を交換したりしましょう。
また、私たちが日々暮らしている住環境は、自分たちで守りご近所同士が助け合うことで、トラブルの発生が抑制され、住み心地のよいまちになっていくことでしょう。
いつも地域の動きに関心を持ち、一人一人ができる予防対策を考え、実践してみては如何でしょうか。
質問項目一覧(項目をクリックすると回答をご覧いただけます)
- Q1 隣の空き家の竹木が越境して困っています。なんとかなりませんか?
- Q2 空き家に蜂やカラスの巣があり、野良動物も棲みついています。どうにかなりませんか?
- Q3 空き家の所有者を調べたいのですが、どこで調べられますか?
- Q4 所有者が亡くなっていて相続人がいない場合はどうすればいいですか?
- Q5 隣の空き家の傾きや落下物などにより自宅等が被害に遭いました。どこに相談すればよいですか?
- Q6 空き家に不法侵入者がいるようで不安です。どうしたらよいですか?
- Q7 所有者等にはどのような責任がありますか?
- Q8 税務署や金融機関等から差押えを受けた空き家は、誰に管理責任がありますか?
- Q9 老朽化した空き家は市がなんとかしてくれるんですか?
- Q10 住宅を解体すると固定資産税はどのくらい高くなるのですか?
Q1 隣の空き家の竹木が越境して困っています。なんとかなりませんか?
A1 隣地から越境した竹木、雑草、ツタの繁茂などについては、基本的には民々の問題(相隣問題)ですので、行政が指導したり介入したりすることはできません。当事者間で話し合って解決していただくことになります。
なお、令和5年4月に民法が改正され、越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切除させる必要があるという原則を維持しつつ、民法第233条第3項各号のいずれかに該当する場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました。
ただし、相手方と思わぬトラブルが生じる可能性もありますので、隣地から越境した枝の切除をお考えの場合は、事前に弁護士等にご相談ください。
<参考>
民法
第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)
1 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3 第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
(1)竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
(2)竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
(3)急迫の事情があるとき。
4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
弁護士への相談
富田林市では無料の弁護士法律相談を実施しています。(事前予約制)詳しくは「法律相談」のページをご覧ください。
都市魅力課 電話 0721-25-1000(内線182)
Q2 空き家に蜂やカラスの巣があり、野良動物も棲みついています。どうにかなりませんか?
A2 空き家の所有者等が、巣を駆除したり、動物が棲みつかないようにしたりなどの対策を講じる必要があります。
<参考>
空家等対策の推進に関する特別措置法
第2条(空家等の所有者等の責務)
空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めなければならない。
※蜂や鳥の巣駆除のご相談について、詳しくは「野鳥・巣等の捕獲や駆除について」のページをご覧ください。
※野良動物の苦情・相談について、詳しくは「動物愛護について」のページをご覧ください。
Q3 空き家の所有者を調べたいのですが、どこで調べられますか?
A3 法務局で登記事項証明書の交付を受けたり、登記簿等を閲覧したりすることで、土地や建物の所有権を有する者の氏名や住所を確認することができます。ただし、最新の情報でない場合もあります。詳しくは、弁護士や司法書士などの法律の専門家にご相談ください。
Q4 所有者が亡くなっていて相続人がいない場合はどうすればいいですか?
A4 弁護士、司法書士にご相談ください。その空き家に利害関係があると認められれば、家庭裁判所に相続財産清算人の選任の申立て(民法第952条)ができます。所有者が行方不明の場合には、同様に不在者財産管理人の選任の申立て(民法第25条)ができます。
Q5 隣の空き家の傾きや落下物などにより自宅等が被害に遭いました。どこに相談すればよいですか?
A5 弁護士にご相談ください。空き家の所有者等に対して、自宅等が現に侵害を受けている場合には「妨害排除請求」、侵害を受ける可能性がある場合には「妨害予防請求」を行うことができます。
Q6 空き家に不法侵入者がいるようで不安です。どうしたらよいですか?
A6 空き家に不法侵入者がいる間に警察へ通報してください。いなくなってからでは捜査が難しいそうです。
ただし、不法侵入者ではなく、所有者等が管理に訪れている場合もありますので、ご注意ください。
Q7 所有者等にはどのような責任がありますか?
A7 建物が倒れたり、瓦等が落下したりするなどにより、近隣の家屋や通行人等に被害が及んだ場合、その建物の所有者等は損害賠償など管理責任を問われます。
<参考>
民法
第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
1 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
空家等対策の推進に関する特別措置法
第5条(空家等の所有者等の責務)
空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めなければならない。
建築基準法
第8条(維持保全)
1 建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。
Q8 税務署や金融機関等から差押えを受けた空き家は、誰に管理責任がありますか?
A8 管理責任は所有者等にあります。差押えを受けると、一般に売却等ができなくなりますが、所有権や管理責任が差押えた者に移るわけではありません。
差押えた者の申し立てで競売などが行われ、落札した者に所有権が移転されるまでは、所有者等に管理責任があります。
Q9 老朽化した空き家は市がなんとかしてくれるんですか?
A9 空き家の管理責任は、所有者等にあります。市は空き家が適正に管理されていない場合、所有者等に適切な管理を行うよう促していきます。
なお、「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、そのまま放置すれば倒壊するおそれがあるなど、適正に管理されていない空き家を状況に応じて「管理不全空家等」や「特定空家等」に認定し、空き家の除却や修繕など、周辺の生活環境の保全を図ることが必要と認められる場合には、市が所有者等に対し、法律に基づく「助言」や「指導」、「勧告」などの措置ができることについて定められています。
Q10 住宅を解体すると固定資産税はどのくらい高くなるのですか?
A10 土地や建物を所有している人には、毎年固定資産税を負担していただいています。税額は、土地及び建物の課税標準額の 1.4%の額です。
住宅が建っている土地の課税標準額は、住宅用地特例により200平方メートルまでは評価額の6分の1に、200平方メートルを超える部分については3分の1に軽減する措置がとられています。(特例が受けられるものは住宅の床面積の10倍が限度です。)
住宅を取り壊したときはこの特例措置がなくなりますが、非住宅用地の課税標準額は、負担調整措置により評価額の約70パーセントとなります。
また、住宅を取り壊すことにより建物の固定資産税はなくなります。土地の評価額が低い場合などは、建物を解体することにより税額が低くなる場合もあります。