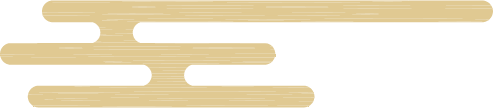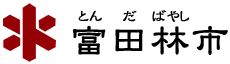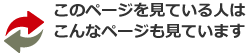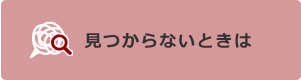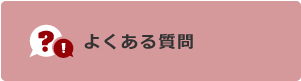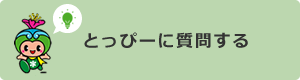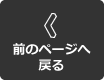令和7年度 にしこおり日記(毎日更新中)
2026年も『にしこおり日記』をよろしくお願いいたします。
『にしこおり日記』は、なまものですので、時間が過ぎると鮮度に課題が出てきます。でも捨てるのはもったいないので、私がおいしくいただきます。次回は、3月当初(2日(月曜日)午前中を予定) に1月分の、3月中旬に2月分の、それぞれ『にしこおり日記』を食べる予定です。読者のみなさん、お早いめにご賞味くださいね。毎日読んでも、週末にまとめて読んでも、不定期に読んでも、『にしこおり日記』を読んで『にしこおりファミリー』になりましょう!
☆さまざまなご意見ご感想をお寄せください。『にしこおりファミリー』みんなで創ろう『にしこおり日記』☆
2月26日(木曜日) 活気のある一日 〜伏山台小見学(そら組)、にこにこ広場、PTA活動〜
今日も全員出席、何よりも素晴らしいことです。このあとも健康第一で過ごしていきましょう。さて今日のそら組(5歳児)は、午前中にバスに乗って伏山台小学校に行ってきました。ここ数年、そら組では4月に入学する小学校へ、その子だけでなくクラス全員で一緒に見学に行っています。今年は2学期に藤沢台小学校へ、そして今日、伏山台小学校へ行ったわけですが、同じ市立小学校でも、それぞれに特色があります。今日の伏山台小学校の校舎は一部4階建てになっていて、4階からの眺めは素晴らしかったです。本園は東側がよく見渡せるのですが、伏山台小学校は西側の展望がよかったです。図書館では、たくさんの本を目の前にしてなかなか一つに絞れない様子も見られました。また、校長室にもおじゃまさせていただきました。「こうちょうせんせい、ひろくていいなあ」と羨ましがる声も聞かれました。運動場でも遊ばせてもらったのですが、あまりに広過ぎたので、エリアを区切って遊ぶことにしました。最後は全員で、長方形の運動場の長辺を走って終わりました。お隣りの伏山台幼稚園の年長(5歳児)も、一緒に見学・交流しましたよ。また、帰りには、伏山台幼稚園の年少(3歳児)も来てくれて、私達を見送ってくれました。伏山台小・伏山台幼のこどもたちや先生方、いろいろとお世話になりありがとうございました。園では、にこにこ広場が開催されていたり、保護者のみなさんがPTA活動として遊戯室で論議や作業をされていたりと、活気のある一日となりました。
2月25日(水曜日) ご心配をおかけしました
今日は、3連休明けでこどもたちの登園状況を心配しておりましたが、全員元気に登園してくれて嬉しかったです。朝から出張に出たのですが、「えんちょうせんせいどこいくの?」「お勉強にいくよ!」「いってらっしゃい、がんばってね」と送り出してくれました。お昼に帰ってきたのですが、ちょうど入れ違いでみんな降園したあとでした。ここでこの日記を書こうとしたのですが、市役所全体のHPがつながらなくなっているようでした。午後からは、『ゆったりクラブ(預かり保育)』のこどもたちのみとなりました。私は再び別のところに出張しました。帰ってきてパソコンを開いたのですが、まだ復旧できていないようでしたので、諦めて降園しました。(翌26日朝に書きました。昨日は更新されていないことを心配していただき、申し訳ありませんでした)
2月22日(日曜日)23日(月曜日・祝日)24日(火曜日・21日の代休)と、3連休となります。暖かくなりそうですが、こどもたちには十分な休養をとってあげてください。次の幼稚園は25日(水曜日)です。元気に登園してね。待ってま〜す!
2月24日(火曜日・代休) 12時30分に登園したら・・・
昨日一日空けただけなのですが、池の水は、夏のような減り方でした。気温が20℃を超える状況では、池や川からの蒸発もあるのですが、草木がたくさん水を吸っているのでしょうね。川の中では、水草が芽を出してきました。春がゆっくり過ぎていったらいいのにな。14時降園予定で園で過ごしていきます。
2月23日(月曜日・祝日) 今日は自宅にてゆっくり過ごしました。
2月22日(日曜日) ウナギはいませんが・・・
朝からとても天気がよく、気温もウナギ登りで上がっていきました。さすがにビオトープ池の水量が気になり、13時30分に登園しました。やはり水位はいつもより低下していましたので、タンクを開栓して補水しました。補水には約35分かかります。池にはメダカが多数いて、日向ぼっこをしていました。また今日は、ドジョウも池底のドロの上にいましたが、私の気配を感じて、全速力でドロの中に潜っていきました。タンクが空になったら、今度は明日以降の補水のために水を張ります。こちらは約30分で満水となります。この補水と貯水の間に、事務処理をしたり、片付けをしたりします。満水となったら、水道を止めて完了です。15時には降園する予定です。
2月21日(土曜日) 『頭のてっぺん!100点』 〜生活発表会(劇ごっこ)〜
今日は生活発表会です。『全員出席』ただただこれを祈って、いつもより早く家を出ました。いいお天気でしかも今日は暖かくなるとのこと。舞台は整い、あとはこどもたちの登園を待つばかりでした。前半は、はな(4歳児)・ほし(3歳児)組で、8時30分〜40分に登園でしたが、バッチリ揃いました。時には渋い顔をして登園することもありますが、今日はとても嬉しそうでした。お家の人がたくさん来てくれたこともあるのでしょうね。張り切っている様子も見られました。そら(5歳児)組は、はな・ほし組の発表中に登園してくるので、登園の姿を見ることはできませんでしたが、大丈夫だったそうです。どちらの劇も、終わったあとに私が審査(得点発表)をする大役を仰せつかったのですが、ほし組のこどもたちには、点数(数字)は、まだむずかしいのです。これまでも、体のどのへんまで来ているか(足の下から上にあがっていく)を担任の先生から教えてもらっていて、昨日は『鼻の上』のところまで来ていたとのことでした。今日は、もちろん『頭のてっぺん!』でしたよ。はな組は、点数の前に少ない人数でよくやったことを褒めた上で、『100点!』を出しました。そら組は、『111点!』としました。これは、11人全員が助け合って劇を創り上げたという意味で、100点+11点=111点としたわけです。ぜひ、各ご家庭でこどもたちの感想をお聞きになったり、逆にお家の人からも話をしてあげてください。そういった会話の積み重ねが、次の育ち、こどもたちのやる気(意欲)にもつながっていきます。よろしくお願いします。あとになりましたが、幼稚園協議会委員のみなさまには、お休みにも関わらず、こどもたちの劇をご観覧いただき、後の協議にも参加いただきました。ありがとうございました。
2月20日(金曜日) 明日を元気に迎えよう 〜生活発表会前日、最終練習〜
今朝もなかなかの冷たさでした。10時頃までは日が差さず肌寒かったのですが、以降は日もさしてきて、14時頃まではまずまずいい感じで過ごせました。明日の生活発表会に向けて、この間ずっと練習を重ねてきました。いろいろなことがありました。こどもたちからの発想で、劇がより楽しくなったり、声を掛け合って次のセリフや動きを確認したり、音を揃えて歌を歌ったり・・・。時には、うまくいかなくて悩んだこともありました。それでも励まし合って壁を乗り越えてきました。最終練習では、両方とも98点の高得点がついたようです。そら組(5歳児)では、あとの2点について(課題)考えたようです。明日の本番では、こどもたち自身から、『笑顔と100点』が出るように演じてくれるでしょう。そのためにも、今日はいつもより少し早めに布団に入りましょう。みんなが元気に明日の本番を迎えられるようにね・・・。
2月19日(木曜日) 「わあわあ」「きゃっきゃっ」 〜メリハリのある生活〜
今日は昨日よりも最高気温が低いという予報でした。現在14時過ぎですが8℃ということで、確かに昨日よりも低いのですが、体感的にはほぼ一緒か、ひょっとしたら今日の方が暖かく感じられるかなといったところです。今日も朝から、劇の練習がありました。私は外で作業をしていたのですが、どちらの劇も、歌だけでなくセリフも声がよく出て、何を歌っているか、何と言っているのかとてもよくわかりました。また、どちらも練習が終わって、遊戯室から下に降りてきた時に嬉しそうな表情が見られました。昨日、私は満足したのですが、主人公のこどもたちも満足しているのではないでしょうか。当たり前のことなのですが、こどもたち自身が舞台に乗るのですから、こどもたちがやりがいを感じられなかったら、劇をする意味がないのです。いつも言いますが、『できたかできなかったか』ではなくて、『やるかやらないか』なのですね。そして、午後は職員も一緒になって鬼ごっこをしていましたが、この時のこどもたちのはしゃぎようはすごかったです。「わあわあ」「きゃっきゃっ」みんなが走りまわって歓声をあげます。実際の3倍くらいの人数がいるのではと思えるほどでした。こういうメリハリも、とても大事なことですね。本番まであと2日、明日は最後の練習です。こどもたちにも職員にもくいが残らないように臨んでほしいものです。
2月18日(水曜日) 満足しました! 〜生活発表会練習参観(中盤)〜
今朝の最低気温は1℃でした。昨日の最低気温とたった1℃の違いですが、ビオトープ川の護岸や、腐葉土入れの草の上には霜が降りていました。そして、いつものように川上から順にビオトープの様子を確認していきました。昨日の作業(グラグラ石を固定するために真砂土を入れる)のあとの様子も見ました。この作業は何度かやらないと効果が出にくいので、今日もまず水をまいて土を沈め、上に再び土をのせていくことにしています。朝の自由遊びの際に、「昨日みたいにトラックで土運ぶ?」と、ほし組(3歳児)に聞いたのですが返事がありませんでした。みんなは別の遊びをしに行きました。「本物のトラックと違うからかな?」など考えていると、1人だけが私に近寄ってきて作業をじっと見ているので、「トラックやる?」と声をかけると「やる!」と嬉しそうに返事してくれました。やりとりを見ていた職員が、その子と一緒に倉庫に二輪車をとりに行ってくれました。みんなの前では(やると)言いにくかったのでしょうか。ショベルに5はいの土を載せて「出発!」、約20mの距離を慎重に運んで、別の場所に土を下ろします。これを3往復やってくれました。時間が来たので今日はこれでおしまいとなりましたが、とても満足してくれて嬉しかったです。このあと、はな組(4歳児)ほし組(3歳児)の合同劇を、続けてそら組(5歳児)の劇を観せてもらいました。私にとっては、初回に続いて2度め(中盤)の観劇となったのですが、合同劇の方はコンスタントに登ってきたなあ、そら組の劇はここに来て一気に登ったなあと、それぞれ感じました。そら組のこどもたちには、やはりこれまでの経験が大きいんだなあと劇を見ていてつくづく思いました。もちろん両方の劇練習に大満足でした。
2月17日(火曜日) 「ごっつんこ?!」 〜生活発表会予行(そら組)〜
今朝の最低気温は2℃でした。昨日の昼からずっと、気温は下がりっぱなしだったのです。そして、今(14時現在)10℃です。昨日の最高気温より2℃低いのですが、どう考えても昨日よりも暖かく感じます。日差しがあるのとないのでは、こうも違うものなのですね。今日は昨日に続き、生活発表会の予行がありました。いつもよりも早いめ、しかも元気に登園してくるそら組のこどもたちを見ていると、ものすごいやる気を感じました。さらに、昨日に続き幼児教育センターの先生が観に来てくださいましたので、こどもたちのテンションもますますアップです。私は、昨日同様園庭にて作業です。天気がよく気持ちもいい中で、真砂土を園庭にまいたり、グラグラ石(ビオトープ川の護岸の敷石がぐらついている)の回りに入れたりしました。午後には、ほし・はな組のこどもたちに『真砂土運搬』を手伝ってもらいました。子ども用の荷物運搬二輪車(建築現場で使う一輪車の小型)に土を入れてあげると、最初はゆっくり慎重に、慣れてくると少しスピードをアップして運んでくれました。「ごっつんこ!」二輪車の前が土山にぶつかって、こう言ってみんな大笑いしていました。ビオトープ川からも「ごっつんこ!」こちらは、川を流れている枯れ草が川底の石に当たるたびに、そう言って楽しんでいました。こんなおもしろい「ごっつんこ!」、何度あってもいいなあ。私は、明日か明後日に、劇ごっこ(中盤)の練習風景を観させてもらう予定です。
2月16日(月曜日) 不思議なこと 〜生活発表会予行(ほし・はな組)〜
今朝はふとんから出るのに全く苦労なしでした。テレビから流れる天気予報は、「5時現在、大阪は10℃で、今日の最高気温は12℃でしょう。」思わず「はあ?」と声が出ました。「今(5時30分)が10℃で、寒くないから起きるのに苦労なしか!」と思う反面、「最高気温12℃って今より2℃上がるだけ?」ってどうよ。そして、前にもありましたが、最低気温は朝方じゃなくて、今日の深夜24時(明日の0時)の3℃ということになるのだそうだ。本当に不思議ですね。7時30分に登園してから、今(14時15分)まで、心持ち暖かくなったような気がするが、日が照ってこないので、この先はどんどん気温が低下していくと思うと、気持ちも沈みがちになりそう。明日からは、『寒の戻り』ということで、また寒くなるようです。これも困ったものですね。服装も体調も日替わり?!になりそうだし・・・。さて、今日は生活発表会の予行(ほし組(3歳児)・はな組(4歳児))でした。いよいよ今週末が本番ということで、衣装なども揃ってきて雰囲気も高まってきているようです。体調には十分気をつけてあげていただき、みんなで楽しく観劇できればと考えていますので、どうぞよろしくお願いします。明日は、そら組(5歳児)の予行があります。また、今日は校務員チームさんが、真砂土を運んできてくださいました。園庭の2ヶ所に分けてトラックから下ろしてもらいました。乗り物好きにはたまらないシーンでしたが、こどもたちが園庭にいない時間だったので残念でした。昼から、ほし組とはな組は、園庭にて自由遊びをしましたが、こどもたちは築山のようになった土の山に登ったり降りたりして感触を楽しんでいました。「山がへっこむって不思議やなあ?」登っても降りても少しずつ山が低くなることに気づいての言葉でした。なお、この土は、園庭(グランド部分)に撒いたり、ビオトープ川の護岸のかさ上げに使ったりしますが、作業が終わるまでは、今の位置において置くことにしました。いろいろな遊び方で楽しんでみてね!
2月15日(日曜日) 今日は昨日の様子から、午前中に登園した方がいいなあと考え、10時40分に登園しました。南門から入るのですが、ご近所に転居されてきた方と出会い、少し立ち話をしました。「日曜日なのに何かあるのですか?」ビオトープ全般のことと、池の補水の話をさせていただきました。転居されてくる前から、園だよりをポストにいれさせていただいていたのですが、「楽しく読ませていただいています」と言っていただけ、とても嬉しかったです。こうやってまた『にしこおり』の地で、新しい人との出会い、お付き合いが始まっていく、素敵なことですね。ビオトープ池の水量は、やはり昨日と同じくらい減水していましたので、早速補水を始めました。そうそう、今日は朝から暖かいからでしょう、水面近くにメダカが10数匹、日向ぼっこをしていました。長い間、姿を見ることができなかったのですが、元気に育っていてよかったです。そして、なんとドジョウも1匹ですが見かけることができました。春も近くまで来ましたね。
2月14日(土曜日) 今日は登園予定はなかったのですが、あまりに暖かいのでビオトープ池の水量低下が気にかかり、13時30分に登園しました。昨日、池の水をほぼ満水にして降園したので、大きなことにはなっていなかったのですが、それでも、ここ2〜3ヶ月にはなかったくらい減っていて、ポンプのパイプがほぼ水面より上に出ていました。今からまた満水にして降園しようと考えていますが、明日は今日以上に気温が上がるということなので、明日もどこかで登園できるよう調整していきます。
2月13日(金曜日) あっという間に 〜『劇ごっこ練習』日々進化〜
今朝も、7時現在で気温は2℃でしたが、日差しはしっかりあります。天気予報も『晴れ』となっていて、青空が広がっています。8時を過ぎて薄雲が広がってきましたが、おそらく大丈夫でしょう。また昨日よりもわずかながら最高気温も上がるようです。こちらにも期待しましょう。今日も劇ごっこの練習は続いています。私は、今日は観劇しませんでした。来週月曜日・火曜日で予行練習をします。これを中盤の観劇としようと思っています。こどもたちもいい意味で緊張してきたのでしょう。劇の練習の合間の外遊びは、いつも以上に動きが大きく、歓声があちらこちらで上がっていました。劇の練習で声を出すことに慣れてきたというのもあるのでしょうね。園庭を声をあげて走り回っている姿を見ていると、どこかホッとします。自分自身のこども時代と同じ光景が広がっているからでしょうね。こどもたちが安心して、いっぱい遊び、いっぱい食べれる。そんな社会をおとなが創っていかなければなりませんね。また、遊ぶ姿の中にたくさんの成長があります。「あんなことにも興味を持つようになったかあ!」「そんなことができるようになったかあ!」「不思議なことを発見したなあ!」あげれば切りがないくらいたくさんの成長です。あっという間にお帰りの時間です。たくさん遊んで大満足のこどもたちは、タイマーが鳴ると一目散にお部屋へと駆けていきます。
2月12日(木曜日) 信じるということ 〜『劇ごっこ練習』続く〜
雨上がりの朝は、空気がきれいなのかとても気持ちがいいですね。7時現在、気温は2℃で冷たいはずなのですが、月曜日・火曜日に比べれば、随分ましに感じています。登園してきて、最初に南門を開けるのですが、月曜日・火曜日は凍っていて冷たく困りました。今朝は、雨が降ったあとなので、解錠して門を開ける際に服を濡らして困ってしまいました。思わず「やっぱり晴れがいいなあ」と、こんなところからも思ってしまいました。日が照っていて、水蒸気が上がっているのでしょうか、金剛葛城の峰は、薄いカーテンがかかっているかのように輪郭だけが見えています。今日も、劇ごっこの練習風景を観せてもらいました。今日は、一昨日に書いた通り、先に、ほし組(3歳児)はな組(4歳児)合同劇を通しで観せてもらった後、交代して、そら組(5歳児)の劇を途中まで観せてもらってから、給食を取りに行きました。今の段階での私のジャッジは、ほし組はな組合同劇が、そら組の劇を一歩リードしていますが、そこは3度めの『劇ごっこ』ですから、そら組がこれから底力を発揮してくると信じています。
2月11日(水曜日・祝日) 雨でビオトープ池の補水も必要ないだろうと予測し、登園しませんでした。
2月10日(火曜日) 大きな期待を 〜『劇ごっこ練習』〜
今朝も7時段階で−1℃と冷え込んでいます。ただ青空が広がり日もさしてきましたので、昨日の残雪や氷も融けていくことでしょう。登園してきたこどもたちは、昨日のはしゃぎようがなかったかのように、冷静に?部屋に入っていきました。今日は、先にそら組(5歳児)、後ではな組(4歳児)・ほし組(3歳児)が、それぞれ遊戯室で劇の練習をしました。私は今季初の練習風景を観させてもらいました。先のそら組の劇は、すべて観せてもらったのですが、あとのはな組・ほし組合同劇は、給食を小学校まで取りに行く関係で、劇の途中までしか観ることができませんでした。木曜日に、観れなかった残り半分だけ観させてもらう予定です。そら組のこどもたちは、幼稚園最後の『劇ごっこ』となります。ここでの育ちが小学校生活にスムーズにつながればいいなと考えています。こどもたちが自分たちで高め合っていけるかどうかがポイントとなるでしょう。一方、はな組・ほし組も、基本はそら組と同じなのですが、役になりきって表現する活動(元気、表情豊か)に重きをおいています。こどもたち全員が「たのしい(たのしかった)」と言える『劇ごっこ』となるよう大きな期待をしています。
2月9日(月曜日) 千載一遇(せんざいいちぐう)
今朝は−2℃でした。少し早めに家を出て、駐車場へと向かいます。車は意外にも霜が降りているだけで、フロントガラスにエアコンで温風を送ると3分程度ですべて解けました。旧170号線を南へ、錦織北の踏切を渡った瞬間、「えっ!」と車の中で叫んでしまいました。一面の銀世界ではありませんか。慎重に車を走らせ幼稚園へ。北門の鍵は何とか開いたものの、門扉が凍って開きません。何度か揺すって「カリカリカリッ」という音を立てながらもゆっくり開けることができました。南門もほぼ同じ状況でした。園庭は一面の銀世界です。1番に登園したものだけが見れる特権を感じながら、職員室まで行きます。扉を開けてから、各部屋を開けに回ります。そのあと、南門付近の氷を割ったり、削ったりして安全確保に努めましたが、完全には削り取れず、日があたってきたので一旦そこを離れ、屋根からのつららを落としに回りました。再び南門付近へ。何とか通路を確保し、登園する園児を迎えることができました。「せっかくの機会なので、雪遊びを楽しませよう!」朝の自由時間を、雪だるま作りや雪合戦などにに当てる予定です。登園してきたこどもたちは、朝の準備を終えると一目散に園庭に出ました。職員も出て雪合戦の始まりです。生まれて初めて雪合戦をする子もいるのではないでしょう、少し戸惑いながら、そして雪を投げることなく、ずっと逃げまくっている子もいました。しかし、まわりの様子を眺めながら、徐々にやり方がわかってきたのか、一緒に投げあっていました。また、雪だるまがビオトープの川岸を中心に複数できました。あと、ビオトープ池には、厚さ1cmを超える、しっかりした氷が張っていました。少し割って、両手で持って「ハイポーズ」写真に収まっていました。事故やケガに注意しながら、千載一遇のチャンスを大いに楽しみました。なお、今日も劇の練習を行いました。本番まで2週間、どんどん伸びることでしょう。
2月8日(日曜日) 雪の中を買い物に行っただけで、一日家の中におりました。
2月7日(土曜日) 13時30分に登園、前日にためておいた水をビオトープ池に入れながら、職員室にて作業。タンクが空になったので閉栓し、再度タンクに水を貯めていく。満水になるまで約30分かかるので、再び職員室に戻り、作業の続きをする。15時降園予定で動いています。今日は日中も寒い(14時現在8℃)ので、なかなか辛いですね。
2月6日(金曜日) やるやん! 〜『発育測定』〜
今朝は、もう暖かいといってもいいほどでした。7時の段階で外気温は4℃でした。最近の朝の冷え込みからすると、「4℃だったら問題ないわ」という感じですね。天気予報によれば、朝夕は曇り空になるが、日中は日差しも十分にあるとのこと。雨の心配もないようですが、これほど雨が降らないというのも困ったものですね。さて、午前中には、毎月1回行っている『発育測定』を行いました。みんな大きくなっていますが、特にそら組(5歳児)のこどもたちは、入園当時のことを思い起こして、ずいぶん成長したなあと感じています。私は、熊手を持ってビオトープの川岸の枯れ草を集めました。途中、ほし組(3歳児)はな組(4歳児)のこどもたち3人が私の横に来ました。「えんちょうせんせい、なにしてるの?」もう何度も聞いたセリフです。「葉っぱ取りやでえ」とこれまたいつもと同じように答えました。「なんのはっぱ?」おっと今日はパターンが違います。しかも今日は枯れ草です。答えに困ったわたしは「えっと、えっと・・・」と考えるようにつぶやきました。」すると「えんちょうせんせい、しらんの?」と不思議がられました。少しくやしくて「えっと、みんなは知ってるの?」と逆に聞き返しました。ここで「しってるよ!」と一人の子が言いました。私が「教えて!」と言うと、「それはね、ほそながはっぱ(細長葉っぱ)!」こう来たではありませんか。そうです、枯れ草は細くて長いものだったのです。思わずうなりました。「やるやん!」 今日のそら組は、早くも劇の通し稽古(けいこ)をしたそうです。これも「やるやん!」 私は、予定通り来週月曜日に観させてもらいます。はな・ほし組も、この日に観れたら観るつもりです。
2月5日(木曜日) ほっこりにしこおり 〜『いちご組』(2歳児未就園児広場)〜
今朝も、冷え込みはあるものの、昨朝に比べるとまだ幾分ましなような気がしています。7時で外気温1℃でした。こうなると不思議なもので、霜は降りていましたが、氷点下ではないので、氷は見られませんでした。登園したほし組(3歳児)の子が「きょうは、こおりがないなあ」と寂しそうにつぶやいています。「ないねえ、明日の朝はあるかもねえ」と私がこの子の横でつぶやくと、「あした、また(池を)みようっと!」と、元気をとり戻して部屋に入っていきました。今日もまた自然から一日が始まりました。今日は『いちご組』がある日です。前回に引き続きお弁当持ちの13時までとなっていますが、もうすっかり慣れていて、お家の人が一旦帰られても、何ともない様子でスタートしました。在園児も「おはようございます」と、保護者の方にも声をかけていました。とてもほのぼのとしていていい感じでした。在園児は、劇の練習が進んでいます。午前中は、時間帯を2つ(ほし(3歳児)はな(4歳児)の合同とそら組(5歳児))に分けて、遊戯室(本番の会場です)を使っての練習も始まりました。私は、最初、真ん中、本番と3回観せてもらうことにしています。伸びたところ、変えたところ、工夫したところなどが、毎日観るよりも、よりはっきりとわかるようにするためでもあります。週明け(月曜日)にでも、最初の観劇をさせてもらう予定です。今からすごく楽しみです。午前中薄曇りでしたが、午後になってしっかりと園庭に日が当たるようになってきました。今日もほっこりです。
2月4日(水曜日) 自然も遊んで学ぶ道具
今朝は、私の感覚ではこの冬一番の冷え込みではなかったかと思います。7時の段階で、外(車の外気温計)は氷点下1℃となっていました。園内のビオトープの草(川岸)にも霜が降りて幻想的な世界です。もちろん池には氷が張っています。8時になりました。日がしっかりと差してきましたが、まだまだ霜も氷も残っています。早く登園してきたこどもたちは、この美しい姿を見ることができるんですよね。さて、今日の1番は誰かな?楽しみです。と考えているうちに、ほし組(3歳児)の子が早くも登園してきました。この子だけがビオトープが霜できらめいているのを観れました。まずは部屋で朝の準備です。続いて、そら組(4歳児)はな組(5歳児)各1名が、通用門で一緒になり2人仲良く登園してきました。元気な挨拶とともに大急ぎで各部屋へ。さすがは先輩たち、最初のほし組の子よりも先に園庭へ。『水やり』へと急ぎます。8時45分頃から登園ラッシュとなりました。「きのう、いえでおすしたべたでえ!」「なんなんとう(南南東)むいてたべた? なんなんとう!」こんな会話が聞かれました。春の節分と言えば、恵方(今年は南南東)に向かって、巻きずしを丸かじりすると、1年間幸福になれるということですが、詳しい意味はわからずとも、こうやって家庭で話をされているというのがとてもいいですね。最もこの恵方巻、関西では定着していますが、関東の方では最近までみられなかったことらしいですね。私は、昔から日本全体で行われていたことだとばかり思っておりました。氷の方は、全員見ることができました。ほし組のこどもたちは、遠巻きに見ています。「池にはまったら冷たそう」と心で思っているようでした。そら組のこどもは、池に手を入れて氷をすくっている子、ひしゃくを持ってきて氷を叩いている子、別のところに行ってきれいな円形の氷を持ってきた子・・・さまざまな動きがあって面白かったです。「つめたい」以外にも「きれい」「かたい」「なくなる(とける)」「われた」「でっかい」などなど多彩な表現があったのも興味深かったです。『にしこおりっ子』は自然現象でも遊び学んでいるのです。今日は午前保育でしたが、外はものすごく暖かで、11時30分降園後も、多くのこどもたちが園庭開放を楽しんでいました。
2月3日(火曜日) 「えんちょうせんせいって、おにさん?」〜『節分』のつどい〜
今日も朝からいい天気で気分も上々↑↑。そして今朝の登園はいつも以上に早く、9時の時点で多くの子が朝の用意を終え、『水やり』もサササのサとやって、遊具や三輪車等で遊ぶ姿が見られました。みんないい顔をして楽しそうです。おとなでもそうですが、こどもたちも遅刻するとバツ悪そうで、表情もどこか淋しげです。すでに何かが始まっているところに入っていくのって勇気がいるし、すでに終わってしまったことがある場合もありますものね。本当に朝(一日の始まり)って大事ですね。今日も天気がいいので、たくさん外遊びをして楽しみました。そのあと、各部屋に戻って『劇ごっこ』の練習をしました。ほし組(3歳児)・はな組(4歳児)は、一緒に劇をします。まずは実際にやってみて考えていきます。そら組(5歳児)は、まずは構想を練って練習していきます。どちらも創造していくことを大切にしています。こどもたちだけでなく、職員も楽しんでやってくれています。これもまた嬉しいことです。今日もまた「お腹が空いた!」という声があちらこちらでしていて、給食は、あっという間にすべての食缶がすっからかん(缶)でした。今月は『完全残さいゼロ』でいけるのではないかと、もくろんでいます。さて、午後は自分たちでつくった鬼の面をかぶって、園庭に出ました。『豆まき』の用意をしていると、どこからか「ガッ、ガッ、ガッ、ガオ〜ッ!」と大きな声がしてきました。あちらこちらを見て探している子、怖くて耳をふさぐ子さまざまでした。やがて園長にとてもよく似た『おに』が現れました。そら組とはな組のこどもたちは「えんちょうせんせいや!」と言いながら豆まきを始めましたが、ほし組(3歳児)は「・・・・」と声を出すことができません。これは、怖いというよりも「なんかえんちょうせんせいとにてるけど、おにさんやなあ?!」と不思議に思っているようでした。それでも、そら組・はな組のこどもたちの様子を見て、同じように「おにはそと!」と元気な声で豆まきを楽しんでいました。鬼がどこかへ去って、子どもたちも部屋に戻りました。だれもいなくなった園庭には、豆まきをした豆が散らばっています。昨年同様、鳥たちがたくさんやってきて、豆をついばむ姿が見られたらいいなあと思っています。園庭はこどもたちのものでも、鳥たちのものでもあるのですね。園長によく似た、本当はやさしい鬼のものでもあるのです・・・。
2月2日(月曜日) いい天気で遊ぶday(でぇ)
2月が始まりました。とてもいいお天気で朝から気持ちがいいですね。最低気温は2℃と相変わらず厳しい寒さですが、天気がいいとテンションも上がります。ビオトープ川や池の水が透き通っているのもいいし、朝日に照らされて水の流れがきらめいているのもまた美しいですよ。午前中はいい天気で結構長い時間外遊びを楽しみました。その分、お腹も空いたのでしょう。2月最初の給食も、おかわりもいっぱいしてくれて完売完食でした。すべてきれいになった食缶をみていると本当に気持ちがいいですね。午後になっても晴天が続き、ここでも外遊びをしっかり楽しみました。私も、南側フェンスに巻き付いているツル外しを中心に、外での作業を行いました。体育倉庫の裏だけが残っているのですが、ここは一日中、日が当たらず寒いので、もう少し暖かくなってからやろうと考えています。今日もほし組(3歳児)の子が「えんちょうせんせい、なにしてるの?」と声をかけてくれました。「葉っぱとりしてるよ」と答えると、「はっぱとりはビオトープ(の池や川)でしょ!」と言うのです。「いや、ここもね(葉っぱとりしてるねん)・・・。」と言いかけたのですが、それはやめて「そうだね、後でやるね。」と言いました。「ところで、どうしてビオトープの葉っぱとりしてると思う?」と尋ねると、「ドロになるから」と言うので、更に「ドロになったらどうしてだめなの?」と突っ込むと、「メダカやエビが(目が見えなくなって)こまるから!」と元気に教えてくれました。日々の生活の中での体験が知識としても身についてきていることが、とても嬉しくまた頼もしく感じました。
2月1日(日曜日) 今日は、買い物と車検があり、登園しませんでした。2月は『逃げる』といいますが、逃さないようにしますね。
1月31日(土曜日) 15時過ぎに登園。池の水補充、新しい水をタンクに入れる。16時15分頃降園予定。1月が『行き』ますね。
1月30日(金曜日) 寒中温あり! 〜『誕生会』『園内研修会』〜
今朝の空は、雲ひとつない快晴でした。登園途中から「この空からして、ビオトープ池に氷が張っているやろな」(天気のいい冬の朝は最低気温が低いから)と予想していましたが、やはり張っていました。これまでとは違って広範囲かつ厚い氷でした。登園してきたこどもたちのうち何人か(これもまた自然体でいいんですよね)が、池を覗き込んでニコニコしていました。みんなで観察もいいのですが、こういう自然な姿もまたいいものですね。さて、今日は『誕生会』がありました。1月生まれのこどもたち(本日の主役)は4人でした。みんなでお祝に歌を歌ったり、ゲームをしたりして楽しみました。おやつとしてうちのシェフが『ぜんざい』をつくってくれました。美味しくておかわりしたいこどもたちに「後で給食残さず食べれる?」と職員が尋ねると、どの子も即答で「いける!」ということで、おかわりありとしました。ほのぼの温かい雰囲気でした。『ぜんざい』を初めて見たのか「この黒い汁は何だ!」と言わんばかりの様子で、困っている子もいました。確かに初めてなら驚くでしょうね。黒い汁なんて『イカスミ』と『ぜんざい』ぐらいですもの。でも、おいしいんだよね。次回はチャレンジしてね。午後からは『園内研修会』が開催されるので、そら組(5歳児)は12時45分降園、ほし組・はな組(3・4歳児)は、引き続き保育としました。「保育を見に来て下さい」と関係各所に案内させていただいたところ、幼稚園の先生だけでなく、小学校や保育園の先生も多数来てくださいました。保育を参加していただいた後、貴重なご意見やご感想をいただきました。非常に高い評価をいただき、職員一同大喜びでした。もちろん、こどもたちがよくやっているからこそであるということも再認識しました。今日は、寒い中ではありましたが、みんなで温かい気持ちになりました。
1月29日(木曜日) 生活リズムに乗ろう 〜『マット先生の英語あそび』〜
今日も、寒い朝で一日が始まりました。幼稚園から見える金剛山は、山の上半分に雪が積もっているようです。時々日が差すと、とてもきれいです。曇っている時より鮮明になるからでしょうね。今日は『マット先生の英語あそび』がありました。学期に1回なのですが、こどもたちも私達職員も楽しみにしています。私は、彼が日本に来てから、30年来の知り合いで、来てくれると日本語と英語が混ざった不思議な会話を楽しみますが、彼が流暢な日本語で話すのを聞くたびに、英語を学ばなくてはならない、学んでもいいなあと思います。一方、連日『元気っ子タイム』で体力をつけながら、『劇ごっこ』の練習を開始するなど、幼稚園生活の新しいリズムもできてきています。楽しく生活するためには、こどもたちだけでなく、おとなも『早寝早起き朝ごはん』が土台になってきます。保護者のみなさんには、こどもたちが9時までに登園でき、一日のいいスタートがみんなと一緒にきれますよう、送迎よろしくお願いします。
1月28日(水曜日) 「とても楽しみです!」 〜入園説明会(いちご組)〜
今日は、いちご組(2歳児の広場)と並行して、入園説明会を行いました。こどもたちは、はな組のお部屋で好きなあそびを楽しみました。それぞれ異なったあそびやポジションがあって、それもまた面白かったです。外にも出て園庭遊びも楽しみました。もうすっかり幼稚園に慣れてきて、在園児と混ざったらわからなくなる程です。保護者のみなさんには、遊戯室にて入園にあたっての説明と諸連絡を聞いていただきました。来年度は母語が日本語ではない幼児(保護者)が入園してくれるので、冒頭の私(ヘッドコーチ)からの挨拶も、英語?でさせていただきました。そのあと、園長代理(スペシャルコーチ)から、具体的な内容について説明や諸連絡を行い、最後に来年度の3歳児PTA役員(各学年から1名ずつ選出)を決めていただきました。保護者のみなさんも我々職員も「とても楽しみです!」 なお、今日は水曜日で午前中保育なのですが、午後のゆったりクラブ(預かり保育)がいつもの水曜日より多くなっています。
1月27日(火曜日) あっという間に一日が過ぎて
今日は、取り組みや行事がないという、幼稚園ではめずらしい日でした。朝から「これをやって、あれをやって」と予定を立てて動こうとしていた矢先、別件が入ってきました。それをやっている途中に、また別の仕事が入ってきて午前中は、あっという間に過ぎていきました。給食をはさんで、「昼からは(先程のこれやあれ)やるで」と意気込んでいたのですが、またまた別のことをしなければならなくなって、結局時間切れとなってしまいました。これやあれは急ぎのものではないのですが、次にまとまった時間がとれるのは、少し先になりそうです。なかなかうまくはいかないものですね。
1月26日(月曜日) 楽しみながら 〜『PTA広報委員会』『初任者研修』〜
『元気っ子タイム』が始まります。園庭には青、ピンク、黄各色の帽子が不規則に散らばっています。列に並んで規則的になっているのもいいのですが、この不規則(=自然)な色合いもなかなかいいですよ。こどもたちとともに職員も一緒にやっています。私はというと同じことをやると、後々みんなに迷惑をかけてしまうので、足の曲げ伸ばしから少しずつ体をほぐしていきます。こどもたちはもう慣れたもので、楽しく軽快に動いています。どんぐり体操、マラソンが終わりこどもたちが部屋に戻ろうとする頃にようやく、私の体がやわらかくなってきます。このあと作業をしながら歩くことにしています。午前中、遊戯室ではPTA広報委員会が開催され、修了記念の文集『Tomato』の作成に向けた作業を委員のみなさんがしてくださいました。保護者同士楽しみながらやられているのがいいなあと感じました。ご参加ありがとうございました。また今日は、初任者研修の一環で、中学校の先生が『異校種で学ぶ』をテーマに、そら組(5歳児)で一日研修されました。午後には、ご自身で考えてこられた3種類のゲームで、こどもたちを楽しませてくださいました。中学校と幼稚園ではさまざまな違いがありますが、土台になっていることは同じだと感じてもらえれば嬉しいなあ。
1月25日(日曜日) 午前中は買い物、昼食後テレビでマラソン観戦等のんびり過ごす。
1月24日(土曜日) 13時30分登園、池の水補給、事務作業等で14時30分降園
1月23日(金曜日) 自然が育ててくれる豊かな心 〜『藤沢台小学校』訪問(そら組)〜
今朝も外は冷たかったです。ビオトープ池には、連日氷が張っています。今日は、水草が良い働きをしてくれて、いろいろな形の氷ができていました。登園してきたこどもたちに氷を見せました。今日は、昨日の教訓(池の水はとても冷たい)から、氷を火ばさみにはさんで取りました。はじめにとれたものを見て、『剣(けん、つるぎ)』か『刀(かたな)』と言うだろうなと私は予想を立てたのですが、出てきたのは『おはし』でした。なるほど! こどもたちは、自分たちの生活に密着しているものから探したのですね。次に板状の氷を取りました。周囲の模様から「これは、(杉の)木やろ」と目論んだのですが、こどもたちが口にしたのは『はっぱ』でした。そうか!木のように立体になっていないなあ、平面だから『葉っぱ』か! 本当にこどもたちの直感、観察眼はすごいです。そして、一緒に自然の美しさを満喫することができました。しばらくするとひとりの子が「畑、ザクザクになってるで!」と走って知らせに来てくれました。「えっ!」何人かのこどもたちが裏の畑へと走っています。「畑が荒らされているのかな?」私も後を追います。「なるほど、ザクザクやな」畑には霜柱が立っていました。このザクザクも自然が生み出した造形、感触なのです。自然は豊かな心を育ててくれます。さて、今日は、そら組(5歳児)が藤沢台小学校を訪ねました。今年度のそら組は、錦郡小学校、伏山台小学校、そして藤沢台小学校へ入学する予定で、それぞれの小学校へ進む子だけではなくて、クラス全員で訪問させていただき、施設や教室を見せてもらったり、校庭で遊ばせてもらったりしています。今日は、「休み時間に1年生と鬼ごっこした」と、嬉しそうに教えてくれました。錦郡小学校以外は、年によって変わるのですが、各小学校のご協力のもと、これからもこの訪問が続けられたらいいなあと思っています。
1月22日(木曜日) 輪になって 〜『錦寿荘交流会』『いちご組』『校区交流会』〜
今朝はとびきり寒かったですね。「これはいけてるやろ!」通用門を開け、ビオトープ池に直行しました。「あるある!!」池には薄いながらも氷がしっかり張っていました。こどもたちが来たら知らせなくては・・・。いや、待てよ。これは自然に見つけるまで黙っておこう。そんなことを考えながら、朝の準備を始めました。登園してきたこどもたちは、なかなか池の様子に気づきません。無理ないですよね。寒くて登園したらまずは部屋に入りたいですものね。やがて園庭遊びをしようと外に出てきたこどもたちの中から、「いけにこおりはってる!」と歓声が上がりました。私の出番?!です。近づいていくと、こどもたちが輪になっていて、一人の子が、氷に手を触れました。「つめたいっ!!」いやいやこの勇気に拍手です。これ以上やると池にはまる子が出そうですので、私がこどもたちに負けないくらいの勇気を出して、両手を氷の下に入れて、氷をすくいあげました。こどもたちはかしこいです。ちゃんと一列に並んで氷を待っています。心の中では「えっ、そんなにいるの」と泣き叫んでいましたが、ここはグッとこらえて、再び両手を池の中に・・・。こどもたちは「えんちょうせんせい、すごい!」と褒めてくれるのでした。こういうのを『やりがい』っていうのでしょうね。さて、今日は、地域の『錦寿いきいきクラブ』のみなさんにお招きいただき、こどもたちと一緒に『Zooと(ずーっと)』さんによる人形劇を見せていただきました。園児の周りに地域のみなさんが輪になってくださいました。年間3回も(学期に一度ずつ)、地域のシニアクラブのみなさんと交流させてもらえること、本当に嬉しく、またありがたく思っています。帰りにはおみやげもいただき、こどもたちは更に喜んでいました。園では、並行して『いちご組』(2歳児広場)があり、今日はお弁当を持ってきてもらって一緒に昼食もいただきました。午後からは、第二中学校区の公立中・小・幼の先生方が集まって『校区交流会』(会場は錦郡小学校)が開催されました。先に公開授業があり、そのあとテーマ別に集まって議論を深めていく予定です。たくさんの輪ができた一日でした。
1月21日(水曜日) 一緒に楽しみ学びましょう! 〜『保育参観』〜
今日は保育参観です。こどもたちがつくった遊びなどを保護者のみなさんも一緒に楽しみましょう。天候がよければ外遊びもしたいと考えています。私の方は、大阪市内で一日研修があるため登園できませんが、向こうで楽しみながら学びたいと考えています。(前日に記載しました)
1月20日(火曜日) 早起きはきみの体を守るため 〜『発育測定・保健指導』〜
今朝は、曇り空ながら寒さはましに感じました。昨日夜、天気予報を見て驚きました。「明日(今日のことです)の大阪の最高気温は7℃、最低気温は7℃でしょう」えっ、どういうこと?!最高と最低が同じとは・・・。この時点では、一日中変化がないということだったのでしょうね。ところが実際には、最高気温が11℃、最低気温が0℃となりそうです。しかも本日の最高気温の11℃は午前!0時(今日の0時)、最低気温の0℃は午後12時!(今日の24時)、つまり一日中気温は下がり続けるっていうわけです。そんな中で、今日は『発育測定・保健指導』を行いました。『発育測定』は、身長・体重を計測しました。『保健指導』では、川西幼稚園の保健の先生に来ていただき、生活リズム、とりわけ早起きについて、どうして早起きしなければならないのかを具体的に話していただきました。「朝起きてから幼稚園に来る(登園)するまでに、家でするのは何かな?」との問いかけに「あさごはん」「はみがき」「かおをあらう」「きがえる」「トイレにいく」などなど、こどもたちから反応(答え)が返ってきました。「それぞれ、どうしてしなければならないのかな?」先生とこどもたちとで一緒に考えていきました。こどもたちはよく知っていて、「たくさん遊びたいから」(朝ごはんを食べる)、「虫歯になりたくないから」(歯を磨く)、「パジャマでは、そと(幼稚園も含む)にでたらかぜひく」 (きがえる)と次々に、実に的を得た理由を出してきました。そこで、「じゃあ、遅くに起きた方がいいのかな、早めに起きた方がいいのかな」、こどもたちは「早めに起きる!」となりました。「『早よ起きや!』言うても起きない」保護者の方からこんな声も聞こえてきそうですね。ぜひ、今日の幼稚園の保健指導のことを、家でも復習してあげてみてください。お家の人も一緒に早起きしましょうね。あなたの体を守るために。(16時になりました。先にも書いたとおりで、朝より冷えてきました。)
1月19日(月曜日) この冬最後の暖かさ?! 〜『ひろみ先生の英語あそび』〜
今朝は、自分の吐く息が白くなっていました。私にとっては、この冬初めてのことでしたが、みなさんはどうでしょうか? でも、こんな日は一日天気がいいことが多いんですよね。今、15時前ですが、日陰でも15℃あります。日なたでは20℃ぐらいに感じます。今日は週明けということもあってかややゆっくりめの登園でしたが、それでも「おはようございます!」と元気な挨拶(今朝は、ほし組(3歳児)がよかったなあ)が園内に響き渡ると、「よっしゃ、今週も一生けん命やるぞ!」と気合が入ります。今日は、午前中に『ひろみ先生の英語あそび』がありました。地域にお住まいの先生で、こういったところでも本園児への支援の輪が広がっていることを痛感しています。また、英語『教室』でも、英語『学習』でもなくて、『英語あそび』となっているところがいいですね。言語系は早いうちからと言われる方もありますが、幼稚園では、英語にふれる、英語であそぶ、英語になれるということで進めてくださっています。そうすることで、英語が楽しいという土台を作れたら、小学校以降の英語学習にスムーズに入っていけます。保護者のみなさんにも自由に見学してもらっていて、内容はよくご理解いただいています。日中は、天気が良い時にやっておこうと、南門の上にある『りゅうきゅうあさがお』のつるを切りました。何人もの園児が今日もまた「えんちょうせんせい、なにやってんの?」と聞きにきてくれます。少しでもわかりやすいように、ゆっくりていねいに説明することを心がけています。本線(1番太いつる)のみを残して、あとはすべてきれいにしました。切り落としたつるや葉は、細かく切って腐葉土箱に入れました。冬を越えて春から初夏を迎えるころには、栄養たっぷり、ふかふかの腐葉土になるでしょう。この腐葉土を畑やプランターに混ぜ込んで利用することで、より立派な野菜や美しい草花ができます。こうやって自然の恵みを循環させています。明日からはいよいよ本格的な冬となりそうです。15時〜16時の園庭開放でも、まだ暖かさが残っていて、たくさんの親子が楽しんでいます。明日からも暖かかったらいいのにな・・・。
1月18日(日曜日) のんびりと・・・
今日もいい天気は続いていて、午前中に買い物を済ませて、早めの昼食をとってから、テレビにて『都道府県対抗駅伝』を観ていました。これロボットが走ってもひとつも感動しないでしょうね。人間ってすごいなあと思いながら、のんびりと観戦しました。
1月17日(土曜日) 予感的中です!
今日もいいお天気でとても暖かいですね。朝から買い物に出て午後は家にいたのですが、家の中にいるのはもったいないなあと思っていると、「あっ!」と気がつきました。「ビオトープ池の水位が下がっているのでは?!」と。というわけで15時に登園。すぐに池をのぞきにいくと、予感的中、約5cmの低下がみられました。昨日にタンクにためておいた水(すこしでも塩素類を抜こうとしてためています)を注ぎました。タンクが空になったら、また水道水を張ります。できるかぎり雨水等で補水したいのですが、お天気が続くと、水道水に頼るしかないのですね。で、このタンクに新しい水がたまった時点で降園することにします。
1月16日(金曜日) 暖かい(温かい)といいね! 〜『会食(『雑煮』等)』『避難訓練(地震)』〜
今日は、とても暖かい朝でした。登園したときにすでに7℃あって、そのあともぐんぐん気温が上昇しました。14時現在、職員室前の日陰ですら16℃もありました。こどもたちは楽しく外遊びをしてから、『元気っこ体操』『マラソン』を行いました。暖かさに体もほぐれていたのでしょう、動きがしなやか(やわらか)でした。私も「今日は外回りやるぞ!」と気合を入れて、まずは餅花を片付けて、続いてビオトープ川の泥すくいをしました。途中で、川の中のエビが忙しそうに動き回っているのを見つけました。泥をすくったので、エビが餌にありつけると喜んでいたのでしょうか、どんどん石の隙間からも出てきて、ウッドデッキ前の橋の下には数え切れないほどのエビがいました。エビは後ろへジャンプするものだとばかり思っていましたが、どうも淡水に住むエビは前に走るようです。腰を曲げることもしないようです。また研究したいと思います。「えんちょうせんせい、なにしてるの?」ほし組(3歳児)はな組(4歳児)は、いつも興味津々で尋ねてきます。ズバリ答えることもありますが、たいていは、「何してると思う?」と逆に聞くようにしています。そしてこのごろは、自分たちでじょうずに答えを導き出してくることが増えてきました。そのあと、はな組のこどもたちが「クイズをするのでみにきてください」と伝えに来てくれたので、一緒に保育室に行きました。各園児手づくりのクイズブックをもとに、絵を見せながら「ここにかくれているのはなんでしょう?」と質問してくれるのですが、これがなかなかの難問で困ってしまいました。「ヒントを下さい」とお願いすると、上手にヒントをくれました。おかげで、なんとか全問正解でたくさんの拍手をもらいました。嬉しかったです。会食は、お正月にちなんで『雑煮』の他、『天ぷら(かき揚げ)』『ダイコン葉のいためもの』と素敵な料理が並びました。この中には自分たちで育てたダイコンや年末に行ったおもちつきで作った丸もちも入っていましたよ。いずれもとても美味しく、たくさんいただきました。降園前に、抜き打ちで地震を想定した避難訓練をしましたが、ほし組(3歳児)のある子は、園だよりの行事予定を見ておられた保護者の方から、「今日は避難訓練がある」と聞かされていたらしく、サイレンが鳴ると同時に、さっと行動できていました。このような親子の関係のもとで、こどもはすくすくと成長していくのですね。とても素敵ですばらしいことだと感心しました。こちらも『温かい』日の出来事でした。
1月15日(木曜日) 小正月 〜『いちご組』『PTA文集原稿作り』『読み聞かせ』〜
今朝も、なかなかの冷え込みで、登園途中の車内表示では外気温は0℃となっていました。けれども、登園直後に見たビオトープ池には氷は全くなかったので、氷点下にはなっていなかったのでしょうね。ただ、いつもと違うのは、朝から日差しがしっかりあったということで、こどもたちは朝の自由遊びを早くから楽しんでいました。また今日は、8時45分の段階で半数を超える園児が登園してきていたので、9時にはこどもたちの元気な遊びが園庭に広がっていました。なかでも、日頃ゆっくりめの登園になっている子が、早く来て嬉しそうにみんなと遊んでいる姿を見ていると、こちらまで嬉しくなってきました。「きょうめっちゃ早いなあ!」と仲間から声をかけられて、ちょっと照れくさそうにしている様子もありました。こどもってやっぱり遊びたいんですよね。家では一人遊びになるから、幼稚園では集団で遊びたいというのもありますよね。今日は今年最初の『いちご組』(2歳児未就園児広場)がありました。こちらも天気がとてもいいので長い時間外遊びをすることができました。またPTA役員のみなさんが、年度末の文集作りに向けて、原稿を作成してくださっていました。いつもありがとうございます。また、3学期に入って2回めの給食がありましたが、今日もおかわりも含め全員完食でした。特にほし組(3歳児)の食べっぷりのよさは感動すら覚えるものですよ。午後には、大阪大谷大学の先生による『読み聞かせ』がありました。定期的に来てくださり、こどもたちも楽しみにしています。また、私たち職員にも、毎回の感想や新しい絵本の紹介などまとめて送ってくださっています。私たちの学びにも大いに繋がっています。さて、午後からは日差しが消えて薄曇りとなりました。気温は下がっていないのですが、日がなくなると体感的には寒くなってきますね。これからが寒さの本番ですが、早く春が来ないものかと思う小正月です。
1月14日(水曜日) 華が咲く 〜『にこにこ広場』『おはなし会』〜
今朝は、私用のためおやすみをいただき、11時前の登園となりました。未就園児広場『にこにこ広場』や、おはなし会(ボランティアの方による読み聞かせ)があり、園内はいつも以上ににぎやかになっていました。天気もいいので園庭にて『お帰りのあいさつ』をしました。午後からの『ゆったりクラブ』(預かり保育)に参加するこどもたちは遊戯室へ上がりました。降園するこどもたちの多くは、園庭開放(最大12時30分まで)を楽しんでいました。見守ってくださる保護者のみなさんも、いつもより寒さがまし?なようで、井戸端会議に華が咲いていました。良い時間が流れていました。
1月13日(火曜日) 『生きた教育』『活かす教育』 〜凧揚げ、ビオトープ〜
今朝は、登園してまず園内を1周してから、職員室に行きました。日曜日の風の影響で変わったことがないか点検するためです。昨日もひと通り見て回って確認したのですが、こどもたちの登園前に再度確認しておきたかったのです。さて、今朝は天気がとてもいいので気持ちがいいし、日差しのもとでは暖かさもしっかりと感じられます。登園してくるこどもたちも元気よく「おはようございます!」と挨拶してくれました。いい天気は、人間の気分も心地よいものにしてくれますね。またまた自然の凄さを感じています。更に風が収まったとはいえ、無風ではありません。自由遊びで「たこあげしたい!」という声が、ほし組(3歳児)はな組(4歳児)の中から起こりました。レジ袋に糸をつけた簡素なものですが、一生けん命走ってみると、自分の体と水平ぐらいの位置まで凧は上がっていました。中には、ゆっくり歩いて(疲れたからかもしれませんが)うまく風を取り入れている子もいて、感心することしきりでした。どの子もにこにこ笑顔でお正月遊びを楽しんでいましたよ。私がビオトープの川岸の石畳を補修していると、はな組の子が「えんちょうせんせい、なにしてるの?」と話しかけてきてくれました。「石がグラグラしていて、みんなが上を歩いたらケガするかもしれないから直しているんだよ」と教えると、「そういうことか」と納得した様子を見せてくれました。別の子は「そのスコップ、いえにもあるよ」と私の手元を指さして教えてくれました。「これって便利なんだよね」「そうそう」 こういった小さなことから会話が始まり、学びにつながっていくんですよね。これまた話の種は自然なんですよね。で、職員がこの続きをやってくれるんですよね。先程の子に「園長先生とどんなお話してたの?みんなに教えてあげて」とね。で、石とケガの話をみんなに伝えたところで、「それ以外でも、この石が川に転がっていったらどうなると思う?」とみんなに振ると、「かわがよごれる」「めだかにあたったらけがする」「えびとかも(ケガする)」って話がひろがっていったんですよね。これこそが『生きた教育』『活かす教育』なんですよ。私とこの職員との間に打ち合わせ等一切なし。あうんの呼吸?っていうやつなんです。
1月12日(月曜日・祝日) 身が引き締まります 〜成人の日〜
朝から登園しました。来る途中、晴れ着姿の方を見かけました。今日は成人の日で、本市でも『はたちのつどい』が行われますが、自分自身の昔のことやわが子の時のことを懐かしく思い返してみました。さて、ビオトープ池には、氷がしっかり張っています。これからが寒さ本番となります。心も体も温かくしましょうね。
1月11日(日曜日) 自然の力を感じ考える
一日中、すごい風でしたね。そんな中短い時間でしたが外にいると、人間ってちっぽけなものだなあとも感じました。そしてこの風って何かうまく使えないものかなあとも思いました。
1月10日(土曜日) 学びは力を生む
大阪市内で開催された『人権問題学習研究集会』に参加しました。たくさんの人が集まっていて、活気のある場となりました。また、自分なりに歴史の整理をすることができました。
1月9日(金曜日) 「ぎゃははは!」 〜冬のトレーニング始まる〜
昨日のお帰りの際お願いした「登園時刻を早めよう」(特にそら組(5歳児)は、4月からの小学校登校時刻(8時30分)を考えて、まずは8時45分には登園しよう)についてご理解いただき、今朝は8時45分の段階で半数を超えるこどもたちが登園していました。朝の準備を済ませ、9時にはたくさんのこどもたちが園庭で自由遊びを楽しんでいました。このように保護者のみなさんと職員が、同じ思い同じ方を向いて動くことで、こどもたちは友だちとともに、楽しい時間をより長く過ごすことができるんですね。そうなるとどんどん遊び、どんどん学ぶことができますから、ぐんと伸びていくというわけです。引き続きよろしくお願いします。自由遊びのあとは、今日から『冬のトレーニング』が始まりました。トレーニングといっても、つらくきびしいものではありません。最初に『どんぐり体操』をします。楽しい音楽に合わせて、体をほぐしていきます。そのまま「走れ、走れ、1・2・3・4・・・」の音楽に合わせてリズムよく『マラソン』をします。スピードを競うものではなく、自分のペースをいかに持続させるかを主眼においています。そら組(5歳児)はな組(4歳児)は、昨年のことをすぐに思い出してやっていました。ほし組(3歳児)のこどもたちは、初めてやったのですが、音楽が楽しいのか、体操(踊り)が面白いのか、両方ともなのかわかりませんが、「ぎゃははは!」とはしゃぎながらやっていました。これにつられたのか、そら組ほし組のこどもたちも喜んでやっていました。さすがに『マラソン』は、声を出しながら走るのは難しい(しんどい)のですが、笑顔は絶やさずに黙々と走っていました。
1月8日(木曜日) 「なんか生えてる!」 〜3学期始業式〜
「おはようございます」元気な朝のあいさつが園庭に戻ってきました。そして「あけましておめでとうございます」「今年もよろしくお願いします」こどもたちと職員がお互いに新春の挨拶を交わしていました。朝の準備が終わって、早速自由遊びです。そんな中、ある子が園庭で『水やり』をしながら「なんか生えてる!」と叫びました。私が近づいて「どれどれ?」と尋ねると、自分の植木鉢を指さして「これこれ」と教えてくれました。2学期の終業式(12月24日)には、土だけ(球根は2つ植えてあった)の植木鉢から、冬休みの間に芽が出ていて、今朝、その芽を見つけて喜んだというわけです。とても素敵な、3学期の、そして1年のスタートとなりました。始業式では、3学期は1年間のまとめと、1学期の準備(0学期と呼んでいます)の両方をする、とても大切な学期なんだよと話しました。これはこどもたちだけでなく、私たち職員にとっても同じこと、毎日を一生けん命に生活していきますね。そして『にしこおりファミリー』のみなさんとの協同で、地域として『にしこおり幼稚園』を創造していきましょう。本年もどうぞよろしくお願いいたします。
12月25日(木曜日)から1月7日(水曜日)までは、冬季休業(冬休み)のため、『にしこおり日記』も、お休みとさせていただき、新年1月8日(木曜日)より再開いたします。どうぞよいお年をお迎えくださいませ。
今日も「早寝、早起き、朝ごはん!」こどももおとなも元気にいきましょう。「さあ、みんなでやってみよう!」
園児が、保護者が、職員が、一緒になっていろいろと考え、楽しみながら動いています。
園庭開放について
平日であれば、いつでも来ていただいて結構ですので、気軽に遊びに来てください。ときどき園外保育等で園を空けることがありますので、「今から行きます!」と一報くださればありがたいです。(せっかく来ていただいたのに、閉まっていたら申し訳ないので・・・)
電話0721(24)3306 錦郡幼稚園まで 短時間でももちろんOk!
バッタ・コウロギなど秋の虫が顔を出しはじめました。園庭ビオトープでは、四季おりおりさらによく見ると毎日多様な変化をみせてくれます。こんな様子もぜひ見に来てくださいね。