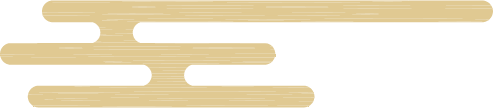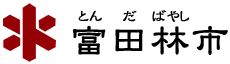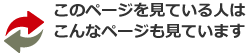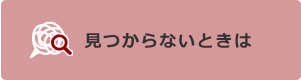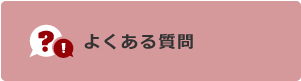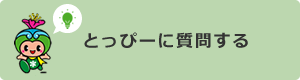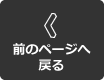富田林市認知症と伴にあゆむ笑顔のまち条例
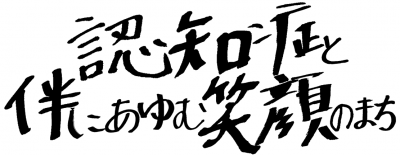
- 令和6年3月 条例の解説と制度を紹介した「みんなに知ってほしい 認知症のこと」を作成しました。 [PDFファイル/3.06MB]
- 令和5年9月 認知症施策に関する意見交換会「MEET☆ミーティング」を設置しました。
- 令和5年9月 広報とんだばやしに特集を掲載しました。※内容は掲載時のものです。 [PDFファイル/598KB]
- 令和4年12月 広報とんだばやしに特集を掲載しました。※内容は掲載時のものです。 [PDFファイル/3.4MB]
- 富田林市認知症と伴にあゆむ笑顔のまち条例が制定されました。
- 施行日は令和4年10月1日です。
趣旨
高齢化の進展に伴い、2025年には高齢者の5人に1人にあたる、約700万人が認知症になることが予測されています。
本市では、平成22年に「富田林市認知症対策5カ年計画」、また、平成25年には「第2次富田林市認知症対策5カ年計画」を策定し、「MEET★とんだばやし(みんな笑顔と笑顔で手をつなごう)」をスローガンに、医師会や歯科医師会、薬剤師会などとも連携しながら、市民フォーラムの開催や認知症相談窓口の設置、認知症サポーターの養成、家族交流会の開催など認知症について総合的な取り組みを実施してきました。
認知症は誰もがなり得るものであり、家族や身近な人が認知症になることなども含め、多くの人にとって身近なものになってきています。こうした中、これまで進めてきた認知症に関する取り組みを基盤として継承しながら、認知症があってもなくても、同じ社会の一員として、地域をともに創っていくことができる「認知症と伴にあゆむ笑顔のまち」の実現を目指します。
富田林市認知症と伴にあゆむ笑顔のまち条例の内容
詳細は以下のリンクからご参照いただけます。
- 富田林市認知症と伴にあゆむ笑顔のまち条例 [PDFファイル/174KB]
- 富田林市認知症と伴にあゆむ笑顔のまち条例 概要 [PDFファイル/290KB]
- 富田林市認知症と伴にあゆむ笑顔のまち条例解説(作成次第掲載予定です。)
基本となる考え方(第3条)
認知症と伴にあゆむ笑顔のまちの実現を推進するための基本理念を定めています。
- 認知症の人の意思が尊重され、尊厳及び希望を保持し、自分らしく暮らせるまちを目指すこと。
- 認知症についての正しい知識と理念に基づき、認知症の人とその家族が地域で安心して暮らすことができる地域共生社会の実現を目指すこと。
- 認知症の人の意思により、その能力を活かして社会参加できる環境をつくること。
市の責務と市民、関係機関、事業者、地域組織の役割(第4条~第8条)
市の責務と市民や関係機関、事業者、地域組織の役割を定め、それぞれがお互いに連携しながら、認知症についての取り組みを進めます。
- 市は、認知症の人とその家族の立場に立った施策を実施するとともに、市民、関係機関、事業者、地域組織と連携・協力し、認知症施策を総合的に推進します。
- 市民は、認知症は誰もがなり得るものであることの認識の下、認知症の備えとして正しい知識と理解を深め、自らの健康づくりを意識し、見守りなどの「ともに支えあう活動」に努めます。
- 関係機関は、認知症に関する専門的な知識や高い対応力を有する人材育成を目指し、各機関が相互に連携しながら認知症の人とその家族の状況に応じた適切な支援に努めます。
- 事業者は、従業員が認知症についての正しい知識や理解を持ち、適切な応対ができるよう教育の実施と認知症の人が能力を活用できるよう特性に応じた配慮に努めます。
- 地域組織は、認知症の人とその家族が住み慣れた地域で安心して暮らすことができるように、認知症についての理解を深め住民がともに支え合うコミュニティづくりの推進に努めます。
認知症と伴にあゆむ笑顔のまちづくりのための施策(第9条~第10条)
認知症に関する市の取り組みについて定めています。
- 年齢や職域にかかわらず、教育機関や関係機関などと協力しながら、認知症に関する正しい知識の普及と理解の促進に努めます。
- 認知症サポーターの周知と養成を進めます。また、認知症サポーターなどが地域で活躍できる環境整備を行います。
- 認知症への備えとして、市民が正しい知識や情報を収集し、認知症の予防のための取り組みを進めます。
- 認知症の早期発見や適切な支援を受けることができるよう、相談や連携体制づくりに努めます。
※「認知症の予防」について、本条例では、「認知症になることを遅らせ、または、認知症になっても進行をゆるやかにすることを目的とした活動」としています。
施行日
令和4年10月1日
富田林市認知症と伴にあゆむ笑顔のまち条例制定に向けた取り組み
富田林市認知症と伴にあゆむ笑顔のまち条例は、市民アンケートのほか、認知症のご本人やご家族、医療・介護関係者などを交えてワーキングを行い、思いや意見を聞きながら条例の策定を行いました。
詳細は以下のリンクからご参照いただけます。