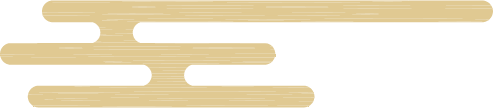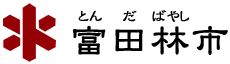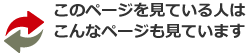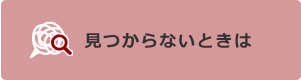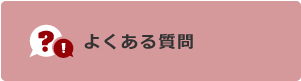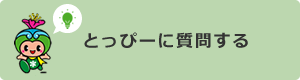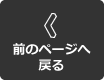海を超えた指定文化財
今年(令和7年)、日韓国交正常化60周年を記念して韓国のソウル市歴史博物館で開催された特別展に、本市にある美具久留御魂(みぐくるみたま)神社が所蔵する一枚の絵馬がはるばる海を越えて出展されました。
本市の指定文化財が海外で公開されたのはこれが初めてのことです。
いったいどんな絵馬か見ていきましょう。

ソウル歴史博物館での展示の様子
何が描かれているのか
韓国のソウル市歴史博物館の特別展に出展されたのは宮町にある美具久留御魂(みぐくるみたま)神社が所蔵する市指定文化財「朝鮮通信使淀川御座船図絵馬(ちょうせんつうしんしよどがわござぶねずえま)」です。
この絵馬には上下に3艘(そう)ずつ計6艘の御座船*(ござぶね)と、乗船するたくさんの人物が色彩豊かににぎやかに描かれています。服装はさまざまで、帽子をかぶり、長い上着にズボン姿など、当時の日本では見かけない服装の人もいます。船に掲げられた旗や幕などから、来日した「朝鮮通信使」(以下通信使と略す)を乗せた御座船の様子を描いたものと考えられます。
現存する通信使を描いた絵馬のほとんどは行列を描いたもので、御座船を描いたものは美具久留御魂神社の絵馬を含め国内に2点のみです。
また、通信使を描いた絵馬として最古級のものであり、学術的価値が高い資料であることから、令和4年5月に市指定文化財に指定されました。
*高貴な身分の人が乗るための豪華な船
使節団の長い旅路
一行は、都があった漢陽(韓国・ソウル市)を出発して陸路で釜山に向かい、そこから船で対馬、壱岐、筑前を経て、下関に到着すると、対馬藩や西国大名の護送船を加えた大船団で瀬戸内海に入り、上関(山口県)、牛窓(岡山県)、兵庫(神戸市)などを経由しながら大坂に入ります。
大坂からは、幕府が西国大名に用意させた御座船に乗り換えて淀川を遡(さかのぼ)り、淀(京都)に上陸した後、中山道、東海道を通って江戸城に向かいます。時には江戸からさらに北上し、日光に向かうこともありました。復路はこの行程を逆に辿(たど)って朝鮮に帰国しますが、往復で約半年に及ぶ長旅でした。
誰が乗っている?何の箱?
絵馬上段の三艘には龍を描いた形名旗とともに、「正」「副」「促」の旗が掲げられており、それぞれ正使、副使、従事官が乗った船と思われます。
また、船尾に掲げられた旗や軒下の幕の家紋から、上段左から臼杵藩稲葉家、宇和島藩伊達家、福山藩水野家、下段左は土佐藩山内家が提供した御座船を描いたものと考えられます。絵馬の左下の船には六角形の箱とそれを護(まも)るようにして座る、小童(こわらべ)と帽子を被った二人の人物が描かれています。恐らく国書が収められた大切な箱なのでしょう。
通信使が遺(のこ)したもの
通信使の来日は、外交面だけでなく文化面においても我が国に大きな影響を与え、絵画や歌舞伎などの題材にも取り上げられるほどでした。また、通信使の来日時には、その一行を見物する人が沿道に多く出て、たいそう賑わったと伝えられています。
絵馬に書かれた墨書(すみがき)から、この絵馬は元禄(げんろく)8年(1695)9月に、桜井村(現桜井町)の住民11人が奉納したものとわかります。この年代に近い朝鮮通信使としては、天和(てんな)2(1682)年の来日が知られています。
通信使の来日から13年後に奉納された理由はわかりません。しかし、異国の装束を身に纏(まと)った人々を乗せた豪華絢爛(ごうかけんらん)な御座船が、当時の人々に深い印象を与えたことには違いないでしょう。
(令和7年10月号)
「朝鮮通信使淀川御座船図絵馬」については、以下のページもぜひご覧ください。
・高精細画像<外部リンク>