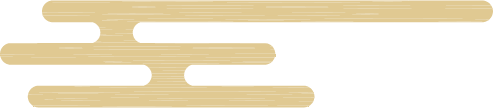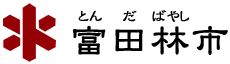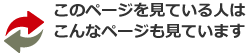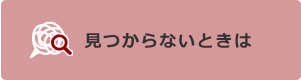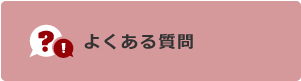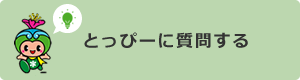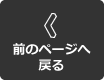本市の2歳女児死亡事案に対する取り組み
1.令和6年度の取り組み
(1)組織の見直し【充実】
組織変更によりこども未来部に子育て応援課を創設し、虐待対応などの相談等を行う相談係と18歳までの子どもの発達支援に関する業務を行う発達支援係を新設する。組織の見直しにより、これまで発達支援業務を兼務していた地区担当員は、より相談業務に専念できるようにした。
(2)人員体制等の強化【継続】
・地区担当員は令和4年度末9名(事案発生前7名)から令和6年度末10名に増員。
・地区担当員を兼務しないスーパーバイザーを令和4年度末2名から令和5年度末3名に増員し、現在も継続配置している。
(3)アセスメント力の強化【継続】
令和5年2月以降の新規受理会議や進行管理会議に外部の専門家のスーパーバイザー1名(弁護士)を招へいし、アセスメントや対応方針、各機関の役割等について共同アセスメントを強化。
令和5年4月以降、対応困難事案や個別ケース検討会議に指導助言を得るために、外部の専門家のスーパーバイザー1名(臨床心理士)を招へいし、職員のアセスメント力の向上を図った。
(4)関係機関との情報ネットワーク強化【継続】
令和5年7月より公立保育所の保育システムの情報を、また令和5年10月より健康づくり推進課の母子保健システムの情報を子育て応援課で閲覧することを可能とし、登園状況や個々の健診、予防接種記録などの客観的な情報を時系列で照らし合わせ、虐待の潜在化を検知する。
(5)職員の専門性向上のための研修【継続】
これまでの年2回の関係機関向け職員研修を年5回に増やし、各関係機関や子どもの年齢に沿った内容の職員研修を行うことで、子育て世代に応じた子どもや保護者の関わり方を学び意識等の向上を図った。
(6)見守りおむつ定期便の実施【継続】
2歳女児死亡事案の発生を受け、健全な育成や虐待の未然防止の観点から、子育て世帯へのきめ細やかな支援は喫緊の課題と考えた。そこで、物価高騰等の社会状況における子育て世帯への経済的支援につなげながら、特に孤立しやすく虐待リスクの高い0歳児のいる家庭に、毎月おむつ等の子育て用品を届けながら声掛けや見守りを継続することで、子育ての不安解消や孤立化の防止、虐待等の早期発見や未然防止にもつなげる取り組みを実施した。
(7)母子保健機能と児童福祉機能の一体化【新規】
令和6年7月に母子保健機能と児童福祉機能が一体化した「富田林市こども・子育て応援センター」を設置し、妊娠期から子育て期への切れ目のない相談支援に努める。
具体的には合同ケース会議を毎月定例開催し、一体的支援のための援助方針や役割分担など、丁寧に対応策を検討している。
さらに、支援対象者への効果的な課題・解決のため当事者のニーズに沿った支援計画「サポートプラン」を作成し、子育て世帯等に寄り添った支援につなげている。
(8)富田林市児童虐待マニュアルの改正【充実】
平成28年度に作成した富田林市児童虐待防止マニュアルについて、近年の児童福祉法の改正に対応した内容に更新し、関係機関で虐待の疑い事案の早期発見から初期対応、支援までの手順方法をわかりやすく示すとともに、関係機関を対象とする説明会を開催し、子どもや保護者の関わり方を学び児童虐待防止への意識向上を図った。
2.令和7年度の新たな取り組み
(1)地域子育て相談機関を市内4か所に設置【新規】
妊産婦や子育て世帯、子どもが身近な場所で気軽に相談できる窓口として「地域子育て相談機関」を市内4か所に設置。相談機関では、子育て世帯との接点を増やし、子育て世帯の不安解消や子どもの状況把握の機会を増やすことで、必要な助言や支援につなげる。
(2)出張発達相談の実施【新規】
地域子育て相談機関に、臨床心理士等の資格を有する心理相談員が定期的に出張し、地域の身近な場所で育児や発達課題について気軽に相談できる窓口を開設する。令和7年度は、年12回程度を予定。
※下記の内容については、令和7年度も継続して実施している。
・家庭訪問の強化
所属のない未就園児童に対し、地区担当員を中心に関係機関と協力し定期的な家庭訪問を実施している。
・実務者会議の運営の見直し
特定妊婦、市主担当の最重度・重度ケース、所属のない児童について、実務者会議における協議頻度を4か月に1回から、2か月に1回に変更し引き続き実施している。
・富田林子ども家庭センターとの連携
進行管理会議開催前の市内部の会議に、富田林子ども家庭センターに参加要請し共同アセスメントを行っている。