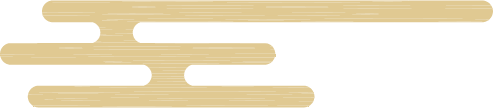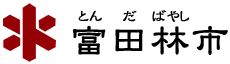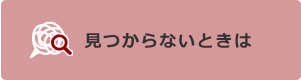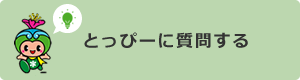土器のかけらが語るもの
発掘調査で掘り出されてくるものの多くは壊れた破片で、しかも、そのほとんどは元の形に復元することができません。しかし、そんなバラバラのへ片からも歴史の真実が読み取られていくのです。
本市が数回にわたって調査している中野遺跡は弥生時代中期(2000年前)に集落がつくられたらしく、調査の度にそのころの特徴をもった土器のかけらが大量に出土します。それらの土器片を観察していると、原料の粘土にいくつかの違った種類があることがわかります。その中の一つ、チョコレート色で角閃石(かくせんせき)という黒くてキラキラと輝く石粒の入った粘土は、生駒山の西の麓(現在の東大阪市付近)で取れる土で、富田林の近くでは手に入らないものです。
この土器はおそらく、生駒山の西麓で作られ、何かを中野の集落まで運ぶための入れ物として使われたのでしょう。この種類のものが全体の土器片の2~3割を占めていますから、この二つの地域にはそうとう頻繁に行き来があったことが伺えます。
さらに出土した遺物を詳しく見ていくと、中野の周辺で取れる粘土で作られた土器の文様や作られ方も、生駒山西麓の土器と似ていることが分かりました。つまり、物をやりとりするだけではなく、人も移り住み、技術を伝えていたのです。生駒の麓から中のへやって来たお嫁さんもたくさんいたでしょう。当時、土器作りは女性の仕事でしたから、そのお嫁さんが自分のふるさとの土器の作り方を中野の人に教えたわけです。
このように、一見、価値のなさそうな土器のかけらからも、様々なことがわかってきます。刃のすりへった石器、もみがらの跡のついた土器片、その一つひとつが当時の生活を今に伝えてくれています。それは、もし見逃したり壊したりすれば、二度と知ることのできない歴史なのです。
(昭和61年9月号)