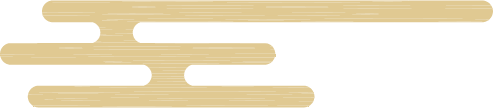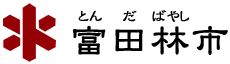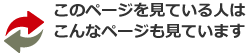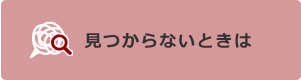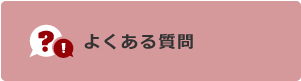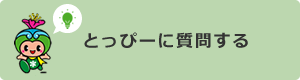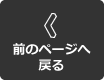浮ヶ澤古墳(喜志南遺跡内)の埴輪見学会を行いました
令和3年度の冬、喜志南遺跡(喜志町)の発掘調査で、5世紀末ごろの古墳が新たに見つかり、多量の形象埴輪が出土しました。浮ヶ澤(うきがさわ)古墳と名付けたこの古墳は、地表面に痕跡が残っていませんでしたが、発掘調査で墳丘を取り囲む周溝の一部を確認しました。その形から、墳長20m前後の前方後円墳とみられます。埴輪は周溝内などから、小さな破片となって出土しました。
現地調査終了後、埴輪の接合を進めたところ、巫女(みこ)・武人に加え、琴を弾いていた可能性のある人物や、馬・鶏といった動物、家、盾などをかたどった埴輪群であることが判明しました。この時期における一つの古墳から、これだけの豊富な埴輪が見つかったことは、市内では初めてのことであり、近畿地方においてもめずらしい事例といえます。世界遺産に指定されている古市古墳群と同じ石川流域にあり、距離も近いことから、王権を支えていた人物の墓かもしれません。当時の大王の古墳に並べられていた埴輪群を推測するうえでも、重要な発見です。
今回の成果を受けて、令和5年5月7日(日曜日)に埴輪見学会を開催しました(当日配布資料はこちら [PDFファイル/3.34MB])
出土した遺物は、今後も整理作業を進めていきますので、今後の進展にご期待ください。

浮ヶ澤古墳の近景

人物埴輪の腕
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)