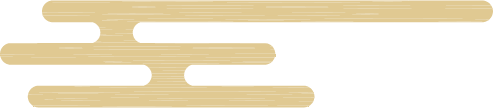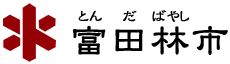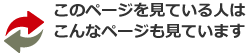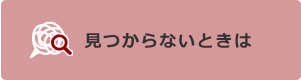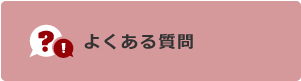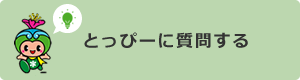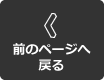第三中学校 教育目標
校訓
自主・自律協力創造
教育目標
豊かな心を育み、自ら学び、互いに高め合う生徒集団の育成を図る
教育実践(三つの自律)
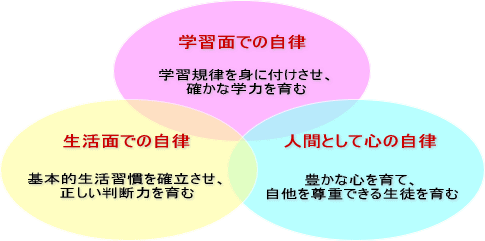
基本方針
富田林市立第三中学校の歴史と伝統を尊重し、社会の変化を見通しながら個性豊かに生き抜く力を持った生徒の育成にあたる。
- 基礎・基本を確実に習得させ、確かな学力を身につけた生徒の育成をめざす学習指導を展開する
- 基本的生活習慣の確立や規範意識を育てるため、ルールの重要性を教え挨拶の習慣や、その場に応じた言葉遣いや態度を身につける等、同一指導の堅持と常時指導の徹底を図る。
- 人権教育と道徳教育を充実させ、自尊感情と互いの個性を認め合う生徒の育成に努める。
- 行事・生徒会活動等を通して、生徒の自主的な活動を奨励するとともに、集団づくりを推進する。
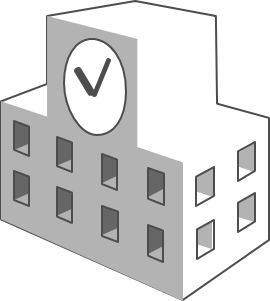
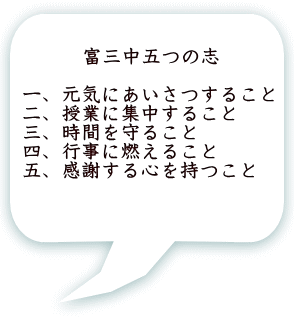
いじめ防止基本方針
富田林市立第三中学校 いじめ防止基本方針
1 本校では、「いじめは絶対許さない」という確固たる信念を持ち、校長のリーダーシップの下、以下の項目を中心に総力を挙げて取組む。
・二度と同じ悲しみを繰り返さない
・教職員全員による組織的な対応を心がける
・重大ないじめ事案等は直ちに相談・通報を行う他、学校と警察が日常的に情報共有や相談を行える体制の構築を図る
・未然予防への取組を学級活動、道徳授業、人権学習などあらゆる教育の場面で実践する
・早期発見、早期対応、早期解決
2 学校及び教職員は、すべての生徒が安心して学習やその他教育活動に取り組むことができるように、保護者や地域、関係者との連携を図りなが ら、学校全体で「特別の教科 道徳」を充実させることが大変重要である。いじめの防止と早期発見に取り組むとともに、『いじめの芽』・『いじめの兆候』も認知しなければならない。またネットいじめは、発見と指導が困難であり、情報モラル教育と情報活用能力の育成が必要である。いじめが疑われる場合は、迅速かつ適切に事案に対処し、早期解決、及び再発防止に努める。
<基本的考え方>
・いじめの未然防止に、すべての教職員が取り組む。
・集団づくり、仲間づくりをすすめる。
・未然予防の取り組みの成果について、PDCAサイクルに基づく取組を継続していく。
3 「いじめ防止対応会議」を設置し、定期的に取り組みをすすめる。
<構成員>
校長、教頭、首席、指導教諭、児童生徒支援コーディネーター、生徒指導主事、学年生徒指導担当、学年主任、特別支援教育コーディネーター、養護教諭、スクールカウンセラー
<活動内容>(原則として週1回定例実施)
・いじめの防止に関すること ・いじめの早期発見に関すること
・いじめ事案への対応に関すること ・不登校傾向者に係る情報交換
・生徒指導事案や不登校傾向にある生徒の情報交換とその対応に関すること
4、いじめの定期的調査
・生徒対象アンケート調査・・・・・・年3回(6月、11月、2月)
・保護者対象アンケート調査・・・・・年2回(7月、11月)
・生徒対象カウンセリング・・・・・・年3回(6月、11月、2月)
5、いじめ相談体制
・いじめ相談窓口の設置 ・悩み相談箱の設置 ・スクールカウンセラーの活用