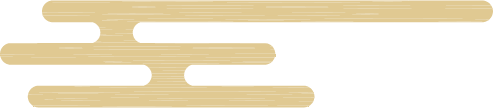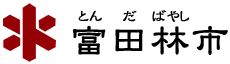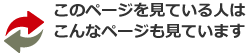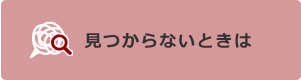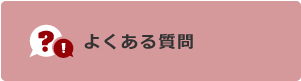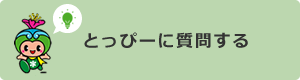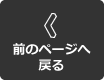もりもりくんの「先月の給食」
令和7年度
1月
30日

- わかめごはん
- かわちのっぺ
- あげたこやき
- おおさかしろなのからしあえ
- ぎゅうにゅう
給食は、よくかんで食べましょう。
今日は、「大阪府」です。河内のっぺは、里芋や鶏肉、野菜など、たくさんの具材を煮込んだ、とろみのある汁物です。里芋が煮くずれることで、自然なとろみが出るのが特徴です。大阪のソウルフードとも言われるたこ焼きを揚げた、揚げたこ焼きと大阪を代表する葉物野菜の大阪しろなを使ったからし和えが出ます。
29日

- タコライス
- もずくスープ
- ぎゅうにゅう
給食は、よくかんで食べましょう。
今日は、「沖縄県」です。タコライスとは、ご飯の上にタコスの具材をのせて食べる料理です。ミンチや玉ねぎ、人参などの野菜をケチャップやチリパウダーで味つけしています。今日は、キャベツも一緒にのせて食べてくださいね。今日のスープは、沖縄県で生産量が多いもずくが入っています。
28日

- サンマーメン
- とんづけ
- まぜまぜゼリー
- ぎゅうにゅう
給食は、よくかんで食べましょう。
今日は、「神奈川県」です。サンマーメンは、野菜炒めにスープを入れ、とろみをつけてラーメンに乗せた麺料理です。とろみをつけることで、冷めにくく熱々のまま食べることができます。とん漬けは、豚肉をみそに漬け込んだもので、焼いたり丼にしたりと様々な食べ方で親しまれています。
27日
- ごはん
- がめに
- あかうおのしょうゆだれかけ
- あちゃらづけ
- ぎゅうにゅう
給食は、よくかんで食べましょう。
今日は、「福岡県」です。がめ煮は、鶏肉と具だくさんの野菜を出し汁と調味料で煮た料理で、寄せ集めるという意味の博多の方言「がめくりこむ」が名前の由来だといわれています。あちゃらづけは、刻んだ野菜に赤唐辛子を加えた酢の物です。冷蔵庫がなかった時代から、日持ちする料理として食べられていました。
26日
- ごはん
- せっかじる
- せんざんき
- ゆかりあえ
- ぎゅうにゅう
給食は、よくかんで食べましょう。
1月24日から30日までは、全国学校給食週間です。給食の歴史を知り、食べ物を大切にする気持ちを育てるための期間で、今年は郷土料理をテーマに、それぞれの地域に伝わる伝統的な料理が登場します。今日は、「愛媛県」です。冬の石切場で、体を温められるように石を入れて食べられた石花汁と、骨付きの鶏肉を揚げたせんざんきです。
23日
- きりめいりコッペパン
- ふゆやさいのスープに
- さけのこうそうやき
- てづくりももジャム
- ぎゅうにゅう
給食は、よくかんで食べましょう。
鮭の香草焼きには、オリーブ油が使われています。オリーブ油は、オリーブという果実から絞られる、フルーティーな香りが特徴の油です。早摘みの緑色の果実が多いと辛みや苦みが強く、熟した黒紫色の果実が多いとまろやかで甘みを感じやすい味になります。日本では香川県が発祥地として、全国の9割以上を生産しています。
22日

除去食

- ごはん
- サンラータン
- てりやきハンバーグ
- こまつなのちゅうかあえ
- ぎゅうにゅう
給食は、よくかんで食べましょう。
サンラータンは中華料理のひとつで、酢の酸味と唐辛子やこしょうなどの辛味の両方が合わさったスープです。さっぱりとした味ですが、体が温まるのが特徴です。今日の給食のサンラータンは、酸味は酢、辛味はこしょうとトウバンジャンを使っています。
今日は、富田林産の小松菜を使用しています。
21日

- ハッシュドポークライス
- ココアまめ
- キャベツのピクルス
- ぎゅうにゅう
給食は、よくかんで食べましょう。
ココア豆は、砂糖で味つけした炒り大豆に、きな粉とココアをまぶしてからめたものです。豆が苦手な人もいると思いますが、甘くておいしいので一口食べてみてください。歯ごたえがあるので、口の中にたくさん入れずに、のどにつまらせないように気をつけて食べてください。
20日

- コッペパン
- やさいスープ
- たらのパプリカあげ
- だいこんサラダ(わふうドレッシング)
- ぎゅうにゅう
給食は、よくかんで食べましょう。
今日のパプリカ揚げは、「たら」という魚を使っています。冬が旬の魚で、北海道や東北地方などの寒い地域に生息しています。身は白く、脂肪が少ないという特徴があり、鍋物、煮つけ、焼き物、揚げ物など、加熱する様々な調理方法で食べられています。
今日は、富田林産の白菜を使用しています。
19日

- ごはん
- マーボーどうふ
- しゅうまい
- もやしのあまず
- ぎゅうにゅう
給食は、よくかんで食べましょう。
もやしの90~95%は水分のため、栄養がないと思われがちですが、ビタミンCや食物繊維など、体に必要な栄養素が含まれています。給食で使用しているもやしは、「緑豆もやし」という種類ですが、大豆から発芽させた「大豆もやし」や黒豆から発芽させた「ブラックマッペ」という種類もあります。
16日
- ふゆやさいのカレーライス
- ウインナー
- かんてんサラダ(フレンチドレッシング)
- ぎゅうにゅう
給食は、よくかんで食べましょう。
今日は、冬野菜を使ったカレーライスです。毎月給食に出ているカレーの食材の他に、かぶとれんこんが入っています。旬の野菜は、味がおいしいだけでなく、含まれる栄養素の量も増えます。かぶやれんこんのように冬に旬を迎える野菜は、体を温めてくれるものが多いので、積極的に食べるように意識しましょう。
15日

- ごはん
- とっぴーのとうにゅうなべ
- さばのゆうあんやき
- てづくりひじきふりかけ
- ぎゅうにゅう
給食は、よくかんで食べましょう。
今日の給食は、とっぴーの豆乳鍋が出ます。とっぴーは、富田林市の市の花である、つつじの髪飾りをつけて石川をイメージしたキャラクターです。豆乳鍋には、富田林市で作られた大根、人参、白ねぎ、白菜、春菊をたくさん使っているので、とっぴーとつけました。味わって食べてくださいね。
今日は富田林産の大根、人参、白ねぎ、白菜、春菊を使用しています。
14日

- ごはん
- キムチトックスープ
- こめこささみカツ
- もやしのナムル
- ぎゅうにゅう
給食は、よくかんで食べましょう。
今日の米粉ささみカツの「ささみ」とは、鶏のむね肉の一部で、むね骨にそって左右に1本ずつある部位のことです。細長い形が、笹の葉に似ていることから「ささみ」と呼ばれるようになったと言われています。今日は、米粉をつかったパン粉を衣にして油で揚げています。脂肪が少なく、淡白な味わいです。
13日
- ごはん
- とっぴーのおいわいすましじる
- ぶりのたつたあげ
- にしめ
- ぎゅうにゅう
給食は、よくかんで食べましょう。
今日から3学期の給食が始まります。冬休みは楽しく過ごせましたか?今日は正月献立です。正月には雑煮やおせち料理を食べて、豊作や家族の健康を願います。ぶりは成長すると名前が変わる出世魚で、縁起がいいと言われています。煮しめは1つの鍋で、たくさんの具材を煮込むことから家族が仲良く暮らせますようにという願いが込められています。
今日は富田林産の大根、人参を使用しています。