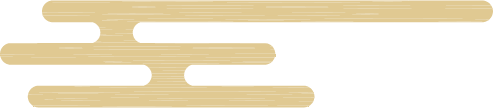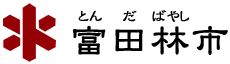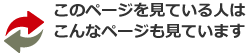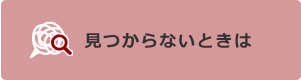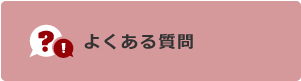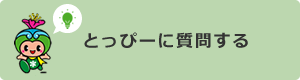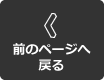市民の声の公表 - 令和7年度分(令和7年11月30日までに受付)
| ご意見 | 関係課 | |
|---|---|---|
| 4月 | 生活保護の担当者について |
生活支援課 |
| 5月 | 金剛図書館 | |
| 道路公園課 | ||
| 高齢介護課 | ||
| 6月 | 金剛連絡所 | |
|
危機管理室、環境衛生課、人権・市民協働課、都市魅力課 |
||
|
生涯学習課、図書館、公民館 |
||
| 市民相談での対応について |
都市魅力課 |
|
|
都市魅力課、こども政策課、人権・市民協働課 |
||
| 中学校給食のパブリックコメントについて |
学校給食課 |
|
| 総合案内について |
都市魅力課 |
|
| 7月 | 保育料について |
こども育成課 |
| コミュニティバスの喜志循環線について |
交通政策室 |
|
| こども育成課 | ||
| 8月 | 商工観光課 | |
| 中央図書館 | ||
| 障がい福祉課 | ||
| こども育成課 | ||
| 教育総務課 | ||
| 保険年金課 | ||
| 生涯学習課 | ||
| 環境衛生課 | ||
| 環境衛生課 | ||
| 図書館 | ||
| 9月 | 職員の接遇について |
保険年金課 |
| 空き缶の無断回収者について |
環境衛生課、都市魅力課 |
|
| 中学校のトイレについて |
教育総務課 |
|
| 10月 | 市民窓口課 | |
| 幼稚園の副食費について |
こども育成課 |
|
| 余ったごみシールについて |
環境衛生課 |
|
| 教育指導室 | ||
| 都市計画課、道路公園課 | ||
| 高齢介護課 | ||
| 公民館 | ||
| 教育指導室 | ||
| だんじりに関する苦情について |
人権・市民協働課、環境衛生課、道路公園課 |
|
| 11月 | 文化財課、住宅政策課、商工観光課 | |
| 健康づくり推進課 |
ご意見
生活保護の担当者について(4月)
生活保護の担当が変わりましたが、とても感じが悪いです。
改善を希望します。
回答
生活保護制度は最後のセーフティーネットとして市民の生活を支える重要な制度であり、職員は申請される方やご利用中の方と信頼関係を築きながら、適正かつ丁寧な対応に努めることが求められています。
今後とも、制度の適正な運用とともに、接遇面の改善にも引き続き取り組み、市民の皆様に安心して相談いただけるよう努めてまいります。
今回のご意見については課内で共有し、職員一人ひとりが日々の対応を振り返る契機といたします。
関係課
生活支援課
ご意見
金剛図書館の設備について(5月)
金剛図書館
・自習できる場所を作ってほしい
・借りようと思っている本を持ち歩けるカゴがあれば良い
河内長野市ではすでにやっている。
回答
「自習できる場所を作ってほしい」につきまして、本市図書館では、限られたスペースの中で、できる限りの机と席をご用意し、閲覧場所を提供しておりますが、自習できる場所はございません。
本市図書館では、自習場所の問い合わせがあった場合は、「富田林市きらめき創造館トピック」やコワーキングスペース「インフィニットコンルーム」をご案内しております。
富田林市役所の西側に Topic(富田林きらめき創造館)【富田林市常盤町16番11号(電話:0721-26-8058)】がございます。席毎に仕切り板が備えられた自習席が66 席あり、どなたでも無料でご利用いただけます。開館時間は午前9時から午後9時。祝日と年末年始(12月29日~1月3日)は休館です。
また、金剛地区に学生のための自習室、働く人のためのコワーキングスペース「インフィニットコンルーム」【富田林市寺池台一丁目9番70号S3号棟(電話:0721-60-6030)】が令和3年1月5日にオープンしております(富田林市とUR都市機構により設置/一部有料)。自習スペース・コワーキングスペースは、大テーブルで6〜8席、会議用机などがございます。開館時間は午前9時30分から午後9時。毎週月曜と、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は休館です。また、保守・点検等その他の管理上の都合で臨時に休館する場合があります。※16歳未満の18時以降の使用は必ず保護者同伴でお願いします。
加えて、夏休み期間中に限りますが、金剛公民館・図書館【富田林市高辺台二丁目1番2号(電話:28-1121)】の2階のラウンジ・ロビーにおきまして、自習スペースを開設いたします。令和7年度は7月23日(水曜日)~8月24日(日曜日)の午前9時から午後6時(日曜は午後5時まで)、市内在住在学の小学生から大学生にご利用いただけます。
毎週月曜日と8月11日、12日は休館です。
「借りようと思っている本を持ち歩けるカゴがあるとよい」につきまして、本市図書館では、本を選んでおられる間も、選ばれた本をご自身のカバン等にお入れいただいて問題ございません。なお、プラスチックなどの固い素材で隙間のある買い物カゴは、資料の角が隙間に引っ掛かるなどして資料を傷める要因となるため本市では採用しておりません。また、全資料にICタグを貼付し管理しており、万が一の貸出処理漏れ等にも対応していますので、安心して本をお選びいただければと思います。ご理解ご協力を賜りますようお願いいたします。
関係課
金剛図書館
ご意見
公園のベンチについて(5月)
彼方児童公園のベンチを復活させてください。もともと、同公園には、ベンチが2つありました。数年前に、ひとつのベンチ(道路沿い)の方が撤去されましたが、撤去したままで、新しいベンチがありません。
休みの日は、特に、公園利用者が多く、ひとつのベンチでは、到底、まかないきれていません。
また、撤去されたベンチの付近には、樹木もあり、直射日光を避ける意味でも、有意義なベンチでした。撤去した理由は、おそらく、ベンチが傾いてきたからだとは思いますが、新しいベンチがないままなのは、正直、不便で仕方ないです。夏も近づいてきていますし、直射日光を浴びないという意味でも、早急なベンチの設置をお願いします。
回答
ご意見をいただいたベンチにつきましては、ベンチの基礎が樹木の根で傾き、ベンチ自体の老朽化が進んでいたため、利用者の怪我につながる恐れがあったことから令和5年度に撤去したもので、ベンチの利用状況について把握ができていなかったことから、再設置は行っていませんでした。
しかしながら、ご意見をいただきましたように、一つのベンチでは公園をご利用される方にご不便をおかけしていることから、ベンチの再設置に向け作業を進めてまいります。(材料の手配に時間を要します。)
今後も、市民の憩いと潤いの場となる公園の安全で快適な環境の確保に努めてまいりますので、ご理解とご協力を賜りますようよろしくお願いいたします。
関係課
道路公園課
ご意見
市公式ウェブサイト上の介護事業所一覧の更新について(5月)
毎月、市役所のホームページの介護事業所一覧のデータを印刷し、利用者様への説明の際などに参考資料としてお渡ししています。
毎月およそ10日〜中旬には更新されていますが、今月はいまだに4月1日更新のままです。
利用者様のなかには最新の情報を求められる方もおり、毎月更新なのであればきちんと更新していただきたいです。
この旨は一度高齢介護課あてにも伝えましたが、そこから1週間ほど経った現在(5月28日)も音沙汰がありません。
ご対応頂ければ幸いです。
回答
ご指摘いただいております「介護保険事業者情報一覧」は、毎月初旬に南河内広域事務室より届く情報をもとに内容の改訂を行った上で、ウェブサイトの更新を行っております。通常は月の中旬には一連の作業を終えて、ウェブサイトの更新ができるよう努めておりますが、5月分につきましては連休の影響等で他の業務がたて込み、事務処理が遅れてしまいました。
ご連絡に対して1週間音沙汰がないとのご指摘に関しましては、職員に確認をいたしましたが、当課へのお問い合わせ履歴を確認することができませんでした。
今後は「介護保険事業者情報一覧」の最新情報を遅滞なく市民の皆様にお届けできるよう、毎月中旬を目安にウェブサイトを更新するよう努めてまいります。
この度はご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。
関係課
高齢介護課
ご意見
金剛連絡所での職員の対応について(6月)
金剛連絡所について、3点あります。
先日、授乳室を使おうとドアを開けると、職員のおじさんがソファでエアコンをつけて読書をしていました。授乳室を必要としていない方が、あろうことか職員(鍵を持っていました)が勤務中に使用するのはあり得ないです。これは許可されているのでしょうか?
次に、金剛連絡所の女性職員について。
勤務中暇なのか、窓口のところで料理のレシピ本を熱心に見ていました。こちらからはっきり見えます。挨拶もせず熱心に読書するほど暇なら職員を減らしてもいいのではないですか?
ちなみに熱中するあまり、私が来たことに気づいていませんでした。待ちの番号も廃止されているのにずっと待つことになりました。
勤務中暇なら、読書を許可されているのでしょうか?
次に別の女性職員ですが、とんでもなく長い尖った付け爪の人がいます。装飾にギラギラ光る石がたくさんついており、大変驚きましたし、書類のやりとりをする時も、刺さりそうで怖かったです。
衣料品の店員さん等ならともかく、事務をする人の指先とは思えません。全くオシャレをするなとは思いませんが、やりすぎです。
上司は注意しないのですか?一般企業ならありえないですよ。富田林市職員の服装の規定はどうなっていますか?
さらに態度も横柄で、言い方も偉そうでした。
金剛地区に住んでいるので金剛連絡所をよく使用しますし、無いと困りますが富田林のほうの市役所に比べ明らかに弛んでいます。いつ行っても暇そうにしています。
税金の無駄ですので責任者、本人共に指導、改善をお願いします。市民は見ていますよ。
回答
この度は、当所職員の対応により、ご迷惑とご不快な思いをおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます。
今回の経緯と今後の対応について、ご説明させていただきます。
まず、授乳室の件についてご説明いたします。使用していた職員は、休日や夜間に2 階ホールの利用があった際、出入口の鍵の開閉など施設管理を委託している事業者の従事者で、昼食や休憩時に授乳室を一時的に使用していたことがありました。
今後は、授乳室を必要とされる方が自由にご利用いただけるよう、従事者には使用しないよう指示し、昼食や休憩時には 2 階の別室を使用するよう徹底いたしました。
次に、女性職員の対応についてご指摘いただきました件です。この度、配慮に欠ける対応となってしまいましたことから、改めて本市職員接遇マニュアルを用いて職員研修を行い、今後は礼儀正しく丁寧な対応を心掛け、市民の皆さまが来られた際には、お待たせすることがないよう速やかに案内し、より一層緊張感を持って職務にあたるよう指導を徹底いたしました。
最後に、金剛連絡所は、今後も身近で気軽にご利用いただける総合窓口として、皆さまの利便性向上に努めるとともに、より親切で丁寧な対応を心掛けてまいります。
関係課
金剛連絡所
ご意見
住宅用脱炭素化機器等導入促進助及びLINEの活用について(6月)
1.住宅用脱炭素化機器等導入促進助成金についての要望
現在、定置型の家庭用蓄電池は非常に高価で、一般家庭にとっては導入のハードルが高く、適切な機種選びも難しい状況であまり現実的ではないような気がします。一方、最近では3kW以上の出力を持つ高性能なポータブル電源が手ごろな価格で販売されており、選択肢の一つと考えています。
このようなことから、
・ ポータブル電源の有効な活用方法
・電力会社の電力とポータブル電源・ソーラーパネルの併用の仕方
・ 必要となるソーラーパネルの出力の目安
など、助成金よりも実際の生活で役立つ電力利用の知識や選択肢について、わかりやすくレクチャーしていただけると非常に助かると思います。
2.LINE「オープンチャット」の活用の提案
LINEのオープンチャット機能は、地域内での情報共有ツールとして非常に有効な機能だと考えます。
たとえば以下のような使い方が考えられます。
・道路の陥没や河川の増水など、異常が起きた時の写真と情報をリアルタイムで共有
・広報誌の速報的な役割(デジタル回覧板)としての情報発信
・ 災害時の緊急連絡手段としての利用
さらに、オープンチャットは匿名参加も可能で、プライバシーに配慮しながら誰でも気軽に意見交換や相談ができる環境を整えることができます。
このような特徴を活かして、富田林市でも地域住民向けにLINEオープンチャットを導入してみてはいかがでしょうか。特に災害対策や防災意識の向上、日常的な地域のつながり強化にもつながると考えます。
回答
住宅用脱炭素化機器等導入促進助成金につきましては、本市では、脱炭素機器の普及を図ることで地球温暖化の防止を推進する目的から、住宅用の定置型蓄電池に対して1件あたり3万円の費用助成を行っており、導入に関しては適時相談を受け付けております。
また、近年では高出力可能なポータブル蓄電池が広く販売されていると認識しております。ご指摘のとおり、日々の暮らしの中で役立つ電力活用の知識や選択肢に関する普及啓発は、脱炭素社会の推進の観点から重要であると考えておりますので、今後もより一層の啓発に努めてまいります。
LINE「オープンチャット」の活用につきましては、本市では、LINEの公式アカウントを開設し、トーク機能を活用し、市が管理する道路や公園施設の破損(陥没・ひび割れなど)の情報提供を、市民の皆さまから平常時より受け付けております。
また、災害対策におきましては、発災後の時期に応じて、SNSの活用など、迅速かつ正確に、きめ細やかな情報伝達ができるよう、情報発信手段の多重化・多様化に努めております。
LINEオープンチャット等、市民のみなさまとテーマに応じた情報交換等ができるコミュニケーションツールについては、発災時真に使えるツールとするためにも、平常時からの市全体の取り組みとして、今後研究してまいりたいと考えております。
広報誌につきましては、市ウェブサイトへの掲載後、市公式LINEにて配信のご案内を行っております。広報誌の内容をご覧いただくことが可能ですので、ぜひご活用ください。
関係課
環境衛生課、危機管理室、都市魅力課
ご意見
自習室の設置について(6月)
富田林市には自習室と呼ばれる施設がほぼありません。
河内長野市や大阪狭山市にはあります。勉強したい人を応援するために、図書館や市の施設の使ってない部屋などを夏休みだけでなく、常に又は土日祝だけでも開放してほしいです。
回答
富田林市内では、自習室としてご利用いただける施設をいくつかご用意しております。
「Topic(富田林市きらめき創造館)」【富田林市常盤町16番11号/電話:0721-26-8056】では、祝日および年末年始を除く毎日、9時から21時まで、自習室66席と交流スペース24席を開放しております。
また、すばるホールでは、春休み、夏休み、ゴールデンウィークの期間に部屋に空きがある場合には、自習室として開放しております。
加えて、金剛公民館におきましても、一部のスペースを自習スペースとしてご利用いただいており、昨年に引き続き、今年度も夏休み期間中は自習スペースの座席を増設して開放する予定です。
他にも、金剛地区魅力向上拠点「∞KON ROOM(インフィニットコンルーム)」【富田林市寺池台一丁目9番70号 S3号棟/電話:0721-60-6030】(市とUR都市機構により設置/一部有料)もご案内しております。
一方、本市図書館では、限られたスペースの中で、できる限りの机と席をご用意しておりますが、その席を持ち込み資料で勉強される方が多くを占める状況になりますと、図書館の資料を探しに来館された利用者が席を利用できなくなり、図書館本来の役割を果たせなくなると考えております。
また、富田林市立中央公民館および東公民館につきましては、毎日多くの市民の皆様にご利用いただいており、施設の利用率も非常に高くなっております。
このため、現状では特定の部屋を自習室として常時開放することは困難でございます。
なお、今回お寄せいただきましたご意見につきましては、今後、施設の建て替え等を検討する際に、貴重なご意見として参考にさせていただきます。
関係課
生涯学習課、図書館、公民館
ご意見
市民相談での対応について(6月)
今回、市長に直接意見があり、このような手段をとらせて頂きました。
私、市民相談を受けて頂きました。
事前に内容を電話でお話していたので、全てが解決出来るものではないと理解して臨んだのですが、話はもっと低レベルなものです。
聞き手の方が相談中にあくびが止まらず、不謹慎だと感じましたので、話したい事もなくなり、早々と切りあげました。
(予約時間に伺っても待たされた上、30分程度の間に5回も6回もマスクの下であくびが止まりませんでしたよ。眠気がおさまらないらしくて立ちあがって話を聞いてましたしね。)
富見箱に投稿を考えましたが、対象の課が管理しているとの事でしたので、もみ消しの可能性があると思い、留まりました。
その後、自宅近くの金剛出張所の所長さんにも説明した所、信じがたい様子でしたが、市長に直接送れるこの手段をご教示頂きました。
で、何がいいたいかと申しますと、そういう方に組織外の人との接触をさせる事は控えて頂きたいという事です。
(対象の方を攻撃するつもりは全くありません。なんらかの疾病のある方かもしれませんし。)
まともに機能しないなら、やめた方がよいと思います。ないなら、こちらも期待はしません。
富田林市民でいる事がすごく恥ずかしい気持ちになっています。
以上、ご勘案下さい。
よろしくお願いいたします。
回答
このたびは、市民相談に関してご不快な思いをさせてしまい、申し訳ございませんでした。市民相談は、市政に関することはもとより、日常生活におけるさまざまなお悩みについてもご相談をお受けし、内容に応じて適切な助言や専門窓口のご案内などを行うことで、市民の皆さまの課題解決を支援する窓口です。本市といたしましては、市民の皆さま一人ひとりの声に真摯に耳を傾け、その内容を適切に対応することが使命と考えております。
つきましては、この度ご指摘いただいた職員には、丁寧な対応をこころがけるよう確認したところです。今後におきましても、親切丁寧な市役所業務の推進に努めてまいりたいと考えております。
また、市民相談は単なる意見聴取だけではなく、市民との信頼関係構築や地域課題解決への第一歩でもあります。そのため、今回の事例についても真摯に受け止め、今後の対応体制の改善に活かしてまいります。
関係課
都市魅力課
ご意見
「実子誘拐被害」「子の連れ去り被害」の相談窓口開設について(6月)
日々、市民の暮らしを守るため、公務に邁進して下さっている地方自治体のみなさまへ、厚く御礼申し上げます。
既に国会でも取り上げて頂いたとおり、令和5年9月の世田谷区主催の女性限定離婚講座で、参加者に対して「正当な理由のない子の連れ去り(実子誘拐)」を含む複数の不法行為が指南されました。離婚時に自らは制度の抜け穴を不正利用し、相手方には「不当な」不利益を与えるような知識を伝授する講座が全国的に開催されていることが、世田谷区の講座音声流出を皮切りに、青森県男女共同参画センターの講座の実施報告、奈良県女性センターの講師レジュメなど、客観的な証拠と共に明らかになりました。
子どもの権利条約第9条で、児童は「父母と分離されないことを確保」されているにも関わらず、全国各地で親子断絶が推進されているのです。
ある日帰宅したら、家財道具とともに家族が忽然といなくなっている。こんな恐怖はありません。しかし警察には「夫婦喧嘩の延長」と捉えられ相手にされず、結局高額な弁護士に相談するしか道がありません。
何故被害者がこんな負担を強いられなければならないのでしょうか。
今回私どもがお願いしたいのは、貴自治体の相談窓口の対象に「実子誘拐被害」もしくは「子の連れ去り被害」を加えて頂きたい、ということです。HPの相談内容の「家庭・夫婦の悩み」の横に書き加えて頂くだけで構いません。誰にも相談できず、苦しんでいる市民は数多く存在します。地方自治体は、社会問題の変化にきちんと対応すべきですし、その大きな変革を是非、貴自治体よりスタートさせていただきますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。
回答
本市におきましては、市民相談窓口にて市民の皆さまが抱えるさまざまな家庭や離婚に関するご相談に対し、適切かつ迅速に対応できる体制を整えております。具体的には、家庭問題や離婚に関するご相談については、「家庭・夫婦の悩み」などのカテゴリーでも受付を行っており、必要に応じて法律相談や専門機関への案内も併せて実施しております。
また、本市ではひとり親支援や離婚前の相談窓口、女性のための法律相談窓口を設置しており、市民の皆さまが安心して相談できる環境づくりに努めております。これらの窓口では、子どもの養育や親権問題などについて、丁寧に対応し、必要な支援策や法的手続きについて案内しています。
今後も社会情勢の変化を踏まえ、市民から寄せられる声を真摯に受け止め、新たな課題にも柔軟かつ積極的に対応していく所存です。
今回、ご提案いただいた「実子誘拐被害」や「子の連れ去り被害」に関するご要望につきましても、大変重要な問題であると認識しておりますので、更なる情報収集とともに、既存の相談体制を充実させて対応していきたいと考えます。
今後とも、引き続き市民一人ひとりが安心して暮らせるように、様々な問題等に的確に対応できるように努力してまいります。何卒、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
関係課
都市魅力課、こども政策課、人権・市民協働課
ご意見
中学校給食のパブリックコメントについて(6月)
中学校給食についてです。
以前アンケートはありましたが、デリバリーについてのアンケートではありませんでした。
そしてパブコメも賛成が1件だったにも関わらずデリバリー方式を採用したと広報にありました。
これは決定したのでしょうか?
パブコメの内容を踏まえてどのような話し合いがされてこのようなことになったのか保護者には一切プリント配布もありませんし、話し合いの場もありません。
学校のイトマンプールもそうですが、実施する前に保護者や子どもの意見を聞いて話し合いができる場を設けてほしいです。
全国に先駆けて自校方式を取り入れた富田林市、当時ニュースになった話を聞きました。
今や災害時対策などで自校方式やセンター方式が主流の中、なぜ逆行するのでしょうか?
避難所の役目も担っている学校です。
しっかり使えるように、このまま引き続き自校方式を続けてほしいです。
何より作っている方の顔が見える、安心・安全の食料、地産地消、地元の方の安定した職業としてこれからも必要不可欠です。
デリバリー方式での給食になるのであれば、食の安全性が心配なので家でお弁当を持たせて行く予定になりそうです。
育ち盛りの子ども達にオーガニックを取り入れたりしている自治体もあります。
食育の観点からもとても残念でなりません。
決定したのであれば小中学校へのプリント配布と質問窓口や説明会、働いている方達への対応などしっかり公表してください。
働いている方は何も知らされていないと言っていました。
丁寧な対応を求めます。
私はこのまま自校方式での中学校給食を望みます。
回答
本市中学校給食については、現行での全員給食は実施困難である状況をふまえて、現在の希望選択制から全員給食への移行等、実施方法も含め検討を重ねました。
全員給食の提供方式については、現行の自校方式は、給食を作っている方の顔が見えて、できたてを提供できるというメリットはありますが、この方式を継続する場合、老朽化した施設や設備の更新が必要となり、あわせて、全員分の食数提供に対応できるよう、設備の配置等も見直す必要がありますので多額の整備改修費用が必要となります。また、改修工事時期については、給食を実施しない夏休み期間中に行うこととなりますが、工事内容から全8校の整備を完了するまで複数年要するため、全校一斉の全員給食移行は困難と考えております。加えて、配膳においても、量の調節はできますが、適切な給食時間を確保するには、各教室で生徒が盛り付ける食缶方式に変更する必要があるため、生徒の配膳下膳や教職員の給食指導も新たに生じることから、負担が増大することとなります。また、これまでと同様にアレルギー対応食の提供が困難となります。
一方、HOTランチボックス方式の場合、適切な衛生管理のもと地元産の食材も可能な限り活用しながら栄養バランスのとれた多彩な献立が可能となります。また、配膳下膳や給食指導の負担増を抑えられることや、おかずの量の調節はできなくなりますが、ご飯のおかわり分の用意やアレルギー対応食の提供が可能となること、さらには、調理場が1カ所であるため給食の一括管理が可能となることから、仮に今後、アレルギー対応食の品目を増やすこととなった場合など、学校間で差異が生じないように対応することができるものと考えております。
また、施設や設備の更新や新たな整備が必要最小限で、全校一斉に全員給食への移行が着実で早期に可能であることなど、現時点では全員給食の提供方式として持続可能な学校給食運営であると考えております。
これらの様々な点を比較し、実現可能性や持続可能性、財政負担等も含め、十分検討した上で、素案をお示し、パブリックコメントを実施しまして、令和7年3月に「富田林市中学校給食のあり方基本方針」を策定しました。
本年6月の富田林市議会定例会におきまして、デリバリー方式による全員給食に関連する予算の議決をいただいたところであり、パブリックコメントで寄せられました衛生管理や危機管理対応等のご心配な点を含め様々なご意見を踏まえ、調理等業務の事業者を選定していくなど、今後は、基本方針に基づき、令和8年度2学期(予定)からのデリバリー方式(民間調理場活用HOTランチボックス方式)による全員給食の実現に向けて、準備を進めてまいります。
また、全員給食実施により変更となる様々なことにつきまして、生徒、保護者の皆さんに丁寧な周知に努める必要があることや、給食への満足度を上げられるように、生徒や保護者の方へのアンケート調査等を行い、改善できるところは改善していくことが重要であることを認識しております。今後も引き続き、食育を大切にし、子どもたちにとって望ましく、持続可能な中学校給食となるよう取り組んでまいりますので、ご理解のほどお願いいたします。
関係課
学校給食課
ご意見
総合案内について(6月)
建替中の庁舎内の案内についてのお願いです。
1階の「総合案内」の配置について、現状は奥に設置されていますが、2か所に設置したらいかがでしょうか。
回答
現在、「総合案内」は、市民サービスの向上を図る観点からも、適切な場所に設置することが重要であると認識していますことから、庁舎内の来庁者が最も多く通る1階の階段付近、エレベーター前に一箇所設置しています。
ご指摘のとおり、「総合案内」を複数箇所に設置することで、市民の皆様が目的の窓口へよりスムーズにアクセスできるというメリットが考えられますが、新庁舎建設に伴う限られたスペースでの執務スペースの確保や、人員配置などの理由から、複数箇所に「総合案内」を設置することは難しい状況となっています。
現在、来庁者の動線を考慮し、1階の複数箇所に案内表示を掲示するなど、来庁者の皆様に「総合案内」の場所が分かりやすくなるよう取り組んでいるところです。
今後におきましても、案内表示の工夫などにより、来庁された方々がスムーズに目的の窓口へアクセスできるよう、引き続き検討してまいります。
関係課
都市魅力課
ご意見
保育料について(7月)
保育料が毎月26000円になります。
正直支払いが厳しいくらいきついです。
2人とも債務整理をしてて、毎月マイナスの状態です。
保育園に入れる時に窓口で私と旦那が世帯主バラバラな事も説明しました。
その時に稼いでる方に息子の扶養を入れて、保育園のやつもそっちでやってください。と言われました。
なので、旦那だけ非課税の給付金とか来ますが私と息子はありません。
その事も説明するとそんなん言ってません。と言われ、世帯主バラバラなら旦那さんの方で息子さんの保育園やるとら26000円にもならないですよ。と後から言われ対応も酷くて、とりあえず払うしか方法はないんで。とアッサリ帰されました。
その後福祉相談の方に移動して全て説明すると、それは保育料もこんなけ高いですよ!と言われ、今の支払い状況、債務整理してること全て言うと子ども課と話してまた折り返します。と言ってもらえました。
ただ、私は旦那が確定申告でマイナスになって居なければ児童手当もあるので節約してでも払いますが、そもそもマイナスを私の給料から補って、そこに高額な保育料ものると生活が本当に出来ないんです。
私は市長に本当に苦しくてまだ生後5ヶ月なので夜職で副業も出来ずこれ以上収入を増やせない。けど保育料払わないと預けられない。色々本気で焦って困ってて助けて欲しくてご連絡しました。
回答
生活状況が厳しく、毎月定められている保育料を期日までに支払うことが難しい状況を改めて認識しているところでございますが、本市の保育料算定につきましては、国が定めた算定方法および基準額をもとに決定し、児童のご両親の市町村民税所得割課税額の合計で算定します。ご意見の内容をお伺いしますと、ご両親は同世帯ではなく別世帯とのことですが、保育料の算定上、別世帯であっても、婚姻関係または同居の事実あれば、上記の算定方法となりますので、ご理解いただきますようお願いします。
なお、毎月定められている保育料を期日までに支払うことが難しい場合、保育料の分割納付の相談は随時承っていますので、こども育成課入所係までご相談ください。
各課では日頃より親切・丁寧な対応を心がけておりますが、今回のご指摘も真摯に受け止め、より分かりやすく丁寧な説明に努めてまいります。
関係課
こども育成課
ご意見
コミュニティバスの喜志循環線について(7月)
とても辛いです。あるだけありがたい路線なのは理解しています。その上で、言いたいです。
コミュニティバスの喜志循環線の巡行をもう少しスムーズに行ってください。特に太子町役場前から喜志駅にかけてのダイヤが乱れない日がありません。道路状況がとか甘えたこと言ってないで、ダイヤ遵守を徹底してくださいませんか?待たされる身にもなってください。
それに、阿部野橋行き急行と連絡できる電車に乗れる可能性をチラつかされているのも辛いです。目の前で行ってしまいます。大深に18時42分、これが守られれば、本来は連絡可能なはずです。運転士は本当に一生懸命にやっているのですか?自分の休憩時間さえあれば構わない、とばかりに喜志駅には定刻通り着きますね。
仕事に対する誠意を感じません。
回答
喜志循環線の運行に関しご指摘いただいております、終着の停留所である喜志駅には定刻通りに到着しているが途中の停留所には定刻通りに到着できていない件についてですが、バスのダイヤにつきましては、道路の渋滞や天候など不確定要素による遅延を最小限に抑えるため、調整の時間を設けております。そのため一部の停留所で到着が時刻表より遅れるように見えることがありますが、これは 「終着停留所での定時運行を確保するための調整」として設定しておりますことから、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
いただきましたご意見につきましては、運行事業者に実態を確認の上、終着駅への到着時刻に大きな遅延等が発生しているのかなど今後のダイヤ改正の検討に参考とさせていただきます。また、太子町と運行事業者にも今回の情報を共有し、喜志循環線のさらなる安全安心な運行の確保に向けて、鋭意努力してまいります。
関係課
交通政策室
ご意見
市立幼稚園・保育園のあり方について(7月)
吉村市長、日頃より子育てに対する手厚いサポートに感謝しております。
市立幼稚園・保育園のあり方について、公立幼稚園に通わせる者として意見を述べさせていただきます。
幼稚園の数と園児数が釣り合っていないことは理解しています。
それでも、公立幼稚園の需要は間違いなくあると考え、現案に反対いたします。
子ども園の数も増え、無償化により私立(子ども園・幼稚園)にも通わせやすくなった今でも、公立幼稚園を選んでいる家庭が300近くあるということにも目を向けていただきたいのです。
働きやすさでいえば保育所や子ども園、私立幼稚園に劣るにも関わらず、働きながら公立幼稚園を選ぶ保護者もいます。
小学校との連携(隣接は大きな強みです)や、先生方の素晴らしさは、通っていて常々感じているところです。
幼稚園の数を減らすこと自体には反対いたしません。
ですが、「保育所が子ども園になるから幼稚園はなくてもいい」かとなると話は別です。
地域に愛される公立幼稚園を、数は減らしたとしてもなんとか守ることはできないでしょうか。
たとえば、北部の園を2園へ、南東部を2園へ、金剛を1園へ、(金剛東ブロックはそのまま)と数を減らすのではいけないのでしょうか?
今の案だと、いずれほとんどが消えてしまうし、それをジワジワ待つような悲しい案で、長い間地域を支えた公立幼稚園に対してあまりに寂しい策だと思います。
「1クラス20人以上、複数クラス」というのも、小学校ならいざ知らず、幼稚園にも必要でしょうか?
それよりも幼児には、先生と保護者の距離が近く、ともに子ども達を見守れる環境の方が大切だと思います。
数を減らすことで、1学年1クラスでも10人以上いれば十分ではないでしょうか。
そのうえで、公立の子ども園が必要なら幼稚園を一部子ども園にしてはどうでしょうか。
どうか、公立幼稚園の魅力と、そこに子どもを通わせたい保護者の望みに寄り添う政策になることを望みます。
回答
ご意見いただきました市立幼稚園・保育園のあり方については、立幼稚園の園児数の減少、保育所の待機児童の発生、施設の老朽化など様々な課題を解消し、今後の市立幼稚園・保育所が担う役割や総量を勘案した持続可能な運営を明らかにするとともに、未来を担うこどもたちの健やかな成長を育むことを目的として、「富田林市立幼稚園・保育所のあり方基本方針(以下「基本方針」という。)」を令和5年3月に策定しました。
この基本方針では、「幼児教育・保育の質の向上」、「市立施設の役割を明確化」、「需給バランスやニーズ等を踏まえた適正規模の施設の再配置」、「再配置によって生じた財源等を活用した新たな取り組みの展開」をこれからの幼児教育・保育の基本的な考え方としています。
頂いたご意見で例示されている「市域をブロックに分け、幼稚園の総数を減らす」といった方向も検討し、令和5年6月には、基本方針に基づく【個別施設再配置計画(素案)】を具現化するため、富田林市立幼稚園条例及び富田林市立保育所条例の一部改正案を市議会定例会に上程しましたが、実現しませんでした。
その後、令和7年2月に、「園児数が減少する中で適正規模の集団教育・保育を行うため、各園において2年続けて3歳の新入園児が10人未満となった場合に、翌年以降の園児募集を停止する」こと、並びに「こどもたちの最善の利益という観点で公による幼児教育は必要であることから、将来にわたって幼児教育を受けることができる環境を確保する」ことを主旨とした「富田林市立幼稚園の今後の方針について」を策定しました。
この方針により、市立幼稚園で新入園児が10人を超える場合、当該幼稚園は存続することとしております。
令和7年10月から、「令和8年度市立幼稚園入園児の募集」が始まります。出生数の減少や保育ニーズ等の影響により、今後、多くの市立幼稚園において、令和10年度の3歳新入園児の募集停止が見込まれる中、仮に全園において募集停止となる場合にも対応できるよう、また、市立施設の役割として、こどもたちのセーフティネット機能をより身近な地域で提供できるよう、令和5年3月に策定した基本方針を踏まえ、このたび「富田林市立幼稚園・保育所のあり方基本方針【認定こども園化計画】」の策定に取り組んでいます。
今後、同計画の素案についての市民説明会やパブリックコメントを実施し、市民の皆さんのご意見などをきかせていただき、計画を策定させていただきます。
関係課
こども育成課
ご意見
PL花火に代わるイベント(8月)
富田林に引っ越してから5年がすぎ、高速が遠いとかどこの道も混むとかいろいろありますが、子供たちと楽しく生活しております。PLの花火が開催されなくなり、今後も復活は難しいとささやかれておりますが、富田林市として代替の花火など地域の活性化に貢献できるようなことはできないのでしょうか。
子供が成長したらPLの花火を一緒に家の近くから見ようと楽しみにしていたし、富田林の自慢として話せるものでしたので、お隣の大阪狭山市に8月1日の花火を取られたような感覚で、少し寂しいです。規模は小さくなろうとも、どうにか開催できないものでしょうか。
回答
お手紙のなかにあるとおり、近年、大阪狭山市で花火大会が実施されています。大阪狭山市の担当者に問い合わせたところ、実行委員会が組織され、費用や雑踏警備等の安全対策など、開催にあたって調整すべき事項が多いと聞き及んでいます。
本市は富田林市観光ビジョンに基づき、「富田林の地域力を向上させる」・「富田林のファンを増やす」・「富田林の可能性を提示する」ことを目標に観光の取り組みを行っています。どのような観光コンテンツを企画立案するかについては、多様なニーズとの適合を図りながら、本市の課題にアプローチできることを念頭に決定しています。
現時点では、改めて市がPL花火芸術に代わる花火大会を開催する予定はありませんが、今後、どのようなコンテンツを企画立案して地域の観光振興につなげていくのか、様々なご意見を参考にしながら検討してまいります。
関係課
商工観光課
ご意見
中央図書館について(8月)
大阪市内から富田林市へ引っ越してまいりまして、それを機に蔵書の大半を処分しておりましたので、これからは図書館を大いに利用するつもりでした。
この図書館で果たして要望する本に巡り会えるかが心配でしたが、それはまもなく杞憂に過ぎないと判明しました。
読みたい本、予約本へ迅速な対応、話題の出版物の購入等。
以前のように大きな図書館や大型書店へ出かけなくなった身には最適なキャパシティーと考えます。
何よりも、貸出カウンターの真向かいに種々選択された話題本が並べてあるのも結構なことと思います。
数十冊ですが、豊富なジャンルでここの長所です。偏向した読書に新しい風を吹き込んでくれたことも再々です。
この点だけでもスタッフの努力が窺えます。
たまに児童書、絵本のコーナーも覗きますが、半世紀も昔に子供達に買い与えた本を見つけると嬉しく懐かしくなります。
紙離れ、本離れの時代ですが、皆さまにもっと利用していただきたいと願っています。
回答
当館に対するあたたかいお言葉をお寄せいただき、誠にありがとうございました。
本市図書館サービスについてご満足いただいているとのこと、職員一同大変嬉しく、今後の業務の大きな励みとなります。
これからも、利用者の皆さまにとって心地よく使いやすい、役立つ図書館であるよう努めてまいります。そして、本に触れる機会の少ない方々にもご利用いただけるよう図書館や本のPRをおこなうなど、より一層の努力を重ねてまいりたいと思います。
この度は、貴重なご意見をいただき、ありがとうございました。
関係課
中央図書館
ご意見
日常生活用具給付対象者の拡大について(8月)
未就学の知的障害児の子がいますが、排泄前の意思表示が難しく、まだまだ紙おむつが必要です。
子育ての支援施策で参考にしていらっしゃる明石市は、今年の4月1日から紙おむつの日常生活用具給付対象者の拡大をし、重度または最重度の療育手帳所持者(排尿排便の意思表示が困難な人)も可能となりました。
ぜひ、富田林市、南河内全域で、可能にして頂くと、同じように困っている方が、とても助かると思いますので、よろしくお願い致します。
回答
本市における日常生活用具の紙おむつ等の給付につきましては、身体障害者手帳の交付を受け、脳性麻痺等脳原性運動機能障がいにより排尿又は排便の意思表示が困難な者などとなっており、重度または最重度の療育手帳所持者は給付対象に含まれておりません。
対象者の拡大につきましては、新たな予算の確保などが必要なことから現時点では実施が難しい状況でございます。
しかしながら、いただきましたご意見につきましては、担当部署で共有し、今後の予算編成や施策見直しの参考と考えております。
関係課
障がい福祉課
ご意見
保育料について(8月)
子育て支援についてです。特に保育園の保育料についてです。
大阪市や堺市、南河内の各市町村で2人目無料、3人目無料等の政策がされていますが、富田林市はされないのでしょうか?
特に3人目については、保育園を利用している人数が3人目のときのみ無料となっているかと思います。
ぜひ、無条件での無料化の政策を実施してほしいです。
実際、職場等でも保育料が要因の1つとして、近隣の市町村へ引っ越しされたケースもあります。
ぜひ早急に実現して下さい。
回答
保育料のご負担につきましては、ここ数年の物価高騰等の影響により、保護者の方々へのご負担になっていることについては、改めて認識しているところでございます。
現在、本市の保育料等については、国の算定基準に準拠し、算定しております。ご提案の第二子及び第三子の保育料無償化につきましては、保護者の負担軽減に繋がるものと認識しておりますが、本市独自の費用負担が生じることとなり、限られた財源の中では、厳しい状況にございます。
今後もさらなる物価高騰が見込まれる中、子育て中の保護者の方々のご負担を少しでも軽減できるよう、限られた財源の中で子育て支援策を検討してまいりますので、何卒、ご理解をお願い申し上げます。
関係課
こども育成課
ご意見
小中学校体育館のエアコンについて(8月)
市内の小中学校の体育館に、エアコンの設置をお願いします。
例年、酷暑がやってきます。何かあってからでは遅くないでしょうか。早急な対応を願います。よろしくお願いします。
回答
お問い合わせいただきました市内の小・中学校体育館へのエアコン設置につきましては、現在、設置に向けた設計業務を行っており、今年度に設計を完了し、来年度以降に順次エアコン設置の工事を行う予定でございます。
また、今後も学校の環境改善のための改修整備を進めてまいりますので、ご理解たまわりますようお願い申し上げます。
関係課
教育総務課
ご意見
保険料の支払いについて(8月)
国民健康保険の事なのですが、4年ぐらい前の事なのですが、それまでは支払い用紙がきちんと届いていて、毎月きちんと支払いしていたのですが、突然支払い用紙が届かなくなりましたので、健康保険課の窓口へ行って用紙が最近届いていませんと伝えましたところ、私は今も信用していませんが、紙を一枚送りましたとだけ言われて、支払いもさせずに追い返されました。
その後一年間ぐらい届いていなかったので、その間3回か4回ぐらい窓口のほうへ行って届いていませんと伝えました。その時係の方ガですね届けたは!と大声で怒鳴って支払いもさせずに追い返されました。
大声を出さないといけなかったのでしょうか。
なぜ新しい支払い用紙渡しますのでそれで支払いお願いしますというふうに話をしていただけなかったのでしょうか。
そうしていただいていれば、今80万ぐらい溜まっているそうですが、こんなに大きい話にはならなかったのではないでしょうか。
私からするとあなた達のせいで溜まっているので、それと1人の係の人だけが送らなかった事を認めて再発防止を誓っていただけましたが、他の係の方は認めていただけません。その温度差は何ですか。
それから私もしばらく我慢して支払っていたのですが、最近の係の方の言動を聴いているとちょっと我慢出来ません。
それと家の従業員から聞いた話ですが、私は支払い用紙など来ていないし払ってないし今後も払うつもりないっていう事だったので、これは不公平ではないですかと抗議の手紙を健康保険課のほうへ届けさせて頂きましたが、三ヶ月気経過した今でも返答は来ておりません。
この前給料調査開始の封筒が届きましたが、この様な状態では納得しかねます。市長からの返答の他に国民健康保険の責任者からの返答も希望したい。
回答
まず、過去に国民健康保険料の納付書が届かなくなったとお問合せいただいた際に、ご納得いただける対応ができなかったことにつきましては、今後は同様の事態が生じないよう、職員への周知徹底を図ってまいります。
次に、国民健康保険被保険者証の返却があり、「今後の支払いはしない、今後一切電話をしないでほしい」との意思表示をされましたが、 国民健康保険料は医療費等の大切な財源であり、全ての納付義務がある人に納付をお願いしているものです。
現在、長期間の未納により未納保険料が累積している状況から、完納に向けた計画を立てるための納付相談が必要となっております。そのため、ご連絡をお待ちしているところでございます。
さまざまなご事情があるかと存じますが、滞納の解消に向けて保険年金課にて納付相談を承りますので、ご連絡いただきますようお願いいたします。
関係課
保険年金課
ご意見
錦織小学校の盆踊りについて(8月)
市長様
平素より市政にご尽力いただき誠にありがとうございます。
私は富田林市に住む市民です。
先日、開催された盆踊り大会に参加しましたが、会場において非常に不適切な行為が見受けられました。
具体的には、一部の参加者による
・くわえタバコのまま接客を行う
・トイレが設置されているにもかかわらず、会場内(小学校グラウンド)で立ち小便を行う
といった行為です。
会場は子どもたちが日常的に通う学校施設であり、このような振る舞いは教育環境の観点からも極めて不適切であり、子どもたちや保護者に強い不安と不快感を与えるものです。
なお、当日の状況については記録(動画)として残しており、必要に応じて提供することが可能です。
つきましては、今後同様の地域行事において、
・会場利用時のマナー遵守の徹底
・主催団体に対する指導・注意
・市としての再発防止に向けた取り組み
をご検討いただけますよう、強くお願い申し上げます。
市民が安心して参加できる健全な地域行事の実現を切に願っております。どうぞよろしくお願いいたします。
回答
この度、盆踊り大会で見受けられました不適切行為につきまして、ご不快、ご不安な思いをさせてしまい、誠に申し訳ございませんでした。
学校施設の使用につきまして、今回の盆踊り大会のように地域の皆さまの交流の場として、また地域福祉やスポーツの振興のため、使用させていただいております。
しかしながら、今回の事態を受けまして、大会主催者へは、通報の内容説明と注意喚起を行い、今一度学校施設利用に関してのルール・マナーを周知、徹底するよう指導いたしました。
大会主催者からは、直接、当該学校へ赴き、学校関係者へ謝罪を行ったとの報告と、今後の再発防止のため、改めて徹底指導していくとの謝罪文の提出を受けております。
なお、本市の今後の取り組みといたしましては、学校施設の利用申請の際に、利用者様に対して、チラシ文面や口頭説明にてルールとマナーの周知を徹底するなど、啓発の強化に努めてまいりますので、ご理解をいただきますようお願い致します。
関係課
生涯学習課
ご意見
富田林霊園について(8月)
富田林霊園の運営の改善について
未販売区画の雑草については現状除草が行われておらず、隣接する販売済区画へその種子が飛来し繁茂するため、対応に難渋している現状にあります。
本来、未販売区画の維持管理については、購入者が支払っている維持費をもって市が対応していただくべきものと考えますので、よろしく改善策のご検討をお願いいたします。
回答
富田林霊園をご利用いただき誠にありがとうございます。また、本市が管理している未販売区画からの種子が原因により雑草が繁茂することにつきまして、ご迷惑をおかけし申し訳ございません。
現状といたしましては、ご指摘の通り、使用者の皆様から納入いただきました維持費を基に、市が未販売区画の維持管理を行っており、販売済み区画は、墓石が建っていない区画も含め、使用者の皆様に維持管理をお願いしております。市が管理している未販売区画の除草作業は、区画ごとに清掃管理人が行っており、特に夏季は、作業頻度を増やして対応に当たっているところでございます。
このたび、使用区画周辺を現地確認しましたところ、数か所繁茂している区画があり、特に繁茂している区画につきましては、順次、使用者へご連絡のうえ除草の対応を依頼しております。また、未販売区画につきましては、今回、1か所繁茂している区画がございましたので、早急に除草対応いたしましたが、管理に漏れが無いよう改めて清掃管理人と情報共有いたしました。
今後も、適切な維持管理に取り組んでまいりますので、よろしくお願い申し上げます。
関係課
環境衛生課
ご意見
ごみカレンダーについて(8月)
粗大ゴミを捨てる時にいつもごみカレンダーを見ていたのですが、無くなってしまって不便です。
また、以前の様な何月何日と記載しているページを作って頂けないでしょうか。
月に一度しかないので捨てる週を間違えるとまた一月後になってしまいます。
よろしくお願いします。
回答
ごみカレンダーにつきましては、ごみの収集日が一目で確認できるということで多くの市民にご利用いただいておりましたが、運用の中で前月の予定表など古い情報がスマートフォンに表示される事例があり、ご利用されている市民から多くのお問い合わせを頂いたこと、また市内全域のごみの収集日を職員が手作業で定期的に入力し更新していましたことにより、事務負担が増大し、入力ミスにより誤った情報を市民に向け発信してしまう恐れもございました。
そこで、令和7年4月からごみカレンダーの運用を終了させていただき、市ウェブサイトや市公式LINEアカウントからごみ収集日を閲覧していただく形に変更させていただきました。加えて、令和6年4月から市公式LINEアカウントで各地域のごみ収集日をお知らせする通知サービスを開始しており、周知に努めているところでございます。
また、ごみの収集日を明記したページの再作成につきましては、市民が見やすく使いやすいアプリ等の活用も含め、先進自治体の事例等を参考に引き続き調査研究を進めてまいります。
関係課
環境衛生課
ご意見
図書館の蔵書について(8月)
市内の図書館に「はだしのゲン」10巻を置いてください。
戦後30年、戦争の惨禍が伝えにくくなっているので、増々、特に若い人達に伝える必要が強くなっています。
非核宣言都市として、市民を啓蒙していく機会を作ってほしいです。
世界的にも広がっている「はだしのゲン」。NHKの新プロジェクトXで取り組みが取り上げられていました。
漫画は図書館に置かないというルールを作っているのは知っていますが、漫画だからこそ、若い人達に戦争の実相が伝える格好の教材だと思います。
戦争の実相を伝えるために、特例として置いてください。
隣の大阪狭山市には置かれています。ルールに縛られるのはおかしいです。
回答
戦争の惨禍を若い人たちに伝えるため、マンガ「はだしのゲン」を置くことについてのご意見を頂戴しました。「はだしのゲン」が原爆の惨状を伝える資料であることはご意見の通りと承知しております。ご意見にご記入いただきました通り、本市図書館ではマンガを所蔵していないため、児童向きに読み物として編集された「はだしのゲン」を所蔵しております。また、マンガ版の「はだしのゲン」をリクエストいただきました折には、協力貸出を活用し近隣自治体図書館より借用し提供させていただきます。
あわせまして、一人でも多くの方に原爆をはじめ戦争の惨禍を知っていただき、平和について考える機会をもっていただけるよう「戦争と平和を考える」と題し、毎年8月にテーマ展示を実施しております。
関係課
図書館
ご意見
職員の接遇について(9月)
保険年金課の方、寝てましたよ。朝一に手続に来ましたが。朝一から寝てるのはどうなんですか?税金でお給与頂いてるんですよね?
見てて本当に不愉快です。
お年を召されている方ですが、必要のない方なら窓口近くに席を置かれるのはどうなんですか?
目につく所に席を置かないでほしい。
回答
職員の勤務態度についてご指摘をいただき、誠にありがとうございます。 関係する職員に確認を行いましたが、睡眠の事実は認められませんでした。
しかしながら、業務中の態度について、誤解を招きかねない行動があった可能性は否定できません。 そのため、今後は同様のご指摘をいただくことのないよう、職員一人ひとりに改めて注意を促すとともに、職員への指導を徹底してまいります。
関係課
保険年金課
ご意見
空き缶の無断回収者について(9月)
ようやく市長さんにメッセージを送れる手段を見つけることができました。
題目は中国人による空き缶泥棒に悩まされている件です。
皆が寝静まっている際に空き缶(実際には金になるアルミ缶だと思います)をあさって
持ち帰る輩が後を絶ちません。
うるさくて寝てもいられません。先日も警察に電話して相談するとめんどくさそうな口ぶりでそれはモラルの問題ですからと言われた挙句、依然市長にも相談させても頂いている旨話すと、では市長の方に言ってくださいと真剣に取り合う様子など電話越しでしたが、ありありとうかがえました。
富田林の警察はどうなっているのかとも思いました。それはとりあえず別件なので置いておくとします。
警察曰く、市からの被害届みたいなものがないと注意するくらいしかできないとのこと。その注意もどのような形でどこまでしてくれているのか普段の空き缶泥棒が後を絶たない現状を見れば察しがつきます。
また、昨年末市長にお話しさせて頂いた際には市役所でたらいまわしにされた挙句、担当部署にたどり着き本件に対する訴えをさせて頂いた際にも、その結果の後日報告を約束させてもらいながらもなしのつぶてであったことについても覚えておられるかどうか分かりませんがさせてもらっています。
市内からどれだけの声が上がっているか分かりませんが、あらゆる収集場に戒めの文句が掲げられているのが確認されます。
ただ、私の周りではお年寄りも多いこともあり、また私の妻においても仕返しみたいなものを恐れての注意や警察への連絡も控えている状況です。ただの注意など効くはずもありません。警察はモラルの問題と言いますが、彼らにはモラルなど無いことはこの行動が継続していることからも明白です。それを分かっていっている警察は何もやりませんと言っているのと同じです。
ただ、市の対応は違うことを願います。
市長さんのおうちではこういう問題が発生していないお静かなところにお住まいなのでしょうか。一度、ご自宅の目の前に空き缶の収集場を設け、そこで積極的に回収している旨、この市の広報等を通じて行われてみたらいかがでしょう。いろんなことに気づかれると思います。
最後に急ぎの場合は担当課にとありますが、既に長年耐えている話でもあり、1週間、2週間、対応が遅れようとかまいません。むしろ担当課に話を持っていってうやむやにされたこともあり、そのこともあり直接この言葉を市長に届けたいです。ただ、ほんとに届くのでしょうか。疑問は残りますが、届くという言葉を今は信じるしかありません。また、手紙の内容は原則公表とありますが、むしろ大弾幕にして市役所の建物に掲げてほしいくらいの気持ちです。「公表希望」です。ちなみにどこにどう形で公表さるのかもお教えください。また、もう一点気になる点が次の通りございます。「(4)同様の趣旨の内容を繰り返し提案または意見するもの」この条件に相当するものは取りあげてもらえないと書いてあるようにも思います。この場でのお願いは初めてですが、市長に直接その時は立ち話のような形態でしたが、お願いさせてもらいました。これがあったことにより取りあげてもらえなくなるのか心配です。もし、そうなら簡単に相談などできなくなってしまいます。いかがでしょうか。本筋とは離れるところでありますが、これについてもお返事頂きたい限りです。
夏場はまだましでした。日も長くやかましい音がする時間も既に起床している場合が多いです。また、エアコンを使うことで窓を閉め切っていることもありますし、音の軽減されます。しかし、これからの季節、日も短くなり窓も開けがちになる。涼しくなることで彼らの活動も活発になる。徐々に最悪の季節がやってくることになります。警察に言っても期待する動きをしてくれない。しないのならこちらで対応させてもらうと言ったらそれはやめてくれと彼らは言う。市も動かない。じっと我慢しろと皆が声を揃えて言っているような気がしてなりません。
分かりますか。また、あれってわずかかもしれませんが、市の財源になるものなのでしょ。要するに市に我々がおさめている税金のようなものです。それを奪い去れて言っているのですよ。そしてそれを知っていながら、お役人たちは実質見てみないふりですよ。失礼かもしれませんが、そんな細かいことに関わってもお役人たちにはなんの得にもならないとの考えが根底にあるのであろうと勘ぐってしまします。
以上、あまりにも腹立たしい案件でありますため、つい失礼な言動を交えてしまったかもしれませんが、それはこの文末で謝罪させて頂きます。
回答
ごみ置場から空き缶などの資源ごみを指定業者以外が持ち去る行為が、市内複数箇所で発生していることについては本市でも把握しており、住民の皆さまから通報や相談等が寄せられた際は、職員がパトロールするなど、持ち去り行為の抑制に努めているところです。
しかしながら、持ち去り行為が後を絶たず、ごみ置場を利用される方々にとっては、不安であるとご相談を受けるケースもあるため、富田林警察と連携したパトロールを実施しているところでございます。
今後、警察との連携強化に努めるとともに、持ち去り行為を禁止する条例の制定を含め、持ち去り行為の抑制に繋がる効果的な手法について、他市の事例も参考に検討してまいります。
「市長へのお手紙」の公表につきましては、行政の透明性を高める観点から、回答の有無を問わず、原則すべてのご意見を公表対象としております。
公表の可否を判断する際には、「個人に関する情報に該当するかどうか」「公表することにより、第三者(個人・法人)の利益を害するおそれがあるかどうか」「個人を特定できる内容であり、その個人情報に配慮することでご意見の趣旨が不明とならないかどうか」といった観点を総合的に勘案します。また、「公表を希望しない」とのご記入がある場合や、公表が適切でないと判断される場合には、公表は行いません。公表する際には、個人情報の保護に十分配慮し、必要に応じて内容を要約して掲載しています。
今回のお問い合わせについては、公表対象と判断しております。掲載にあたっては個人情報に十分留意し、適切な形で公表いたします。なお、公表までには一定のお時間をいただきますので、あらかじめご了承ください。
この度は、貴重なご意見ありがとうございました。
関係課
環境衛生課、都市魅力課
ご意見
中学校のトイレについて(9月)
切実なお願いです。
他の富田林市の中学校の現状は分かりかねますが、喜志中学校は現在まだ一部の個室を残し、ほぼ和式トイレです。
女性の生理中の生理による腹痛の際や、生理の際のトイレでナプキンの交換は立ちながらの和式では本当にしんどいのです。
私はもう既に当たり前に洋式であると思っていましたが、中学3年生の娘から生理中のトイレがしんどい事、トイレの汲み取り水圧が弱く、唯一の洋式トイレが使用禁止になっていることを聞きました。
毎日使用する設備になりますので、早急に改善をいただけないか、ご検討いただけると幸いです。 ありがとうございました。
回答
今回ご指摘いただきました洋式トイレは、水圧が低く汚物が流れないため、数日前から学校にて使用禁止としていたことを確認しました。トイレの使用に支障が出ているとのご意見から、早急に現地確認し、水圧の調整を行ったところ正常な水圧となったことから、現在は使用可能な状態に復旧しております。
また、トイレの洋式化改修工事については、毎年各校にて進めているところで、今回ご使用いただいているトイレも今後改修を行う予定となっております。
関係課
教育総務課
ご意見
自衛隊への情報提供除外届出について(10月)
こんにちは。
今日家のポストに自衛隊富田林地域事務所から郵送物が送られてきました。
先日市役所に自衛隊への情報提供除外届出書を出しに行き、14歳のため受け取れません、と言われて帰ってきました。
確かに届出対象者は4月1日現在で17歳以上22歳以下の方となっています。
そのため中3生には送られてこないんだなと解釈しました。
しかし実際にはこのように14歳にも送られてくるので、届け出対象者は14歳へと年齢の引き下げを早急にしていただきたいと思います。
よろしくお願いします。
回答
防衛大臣からの18歳及び22歳を対象とした「自衛官及び自衛官候補生の募集」に関する名簿提供依頼については、個人情報の保護に関する法律第69条第1項の「法令に基づく場合」に該当するものとして名簿の提供を行っています。当該依頼は、自治体に裁量の余地があることから、ご自身の情報の提供を希望しない人については情報提供除外の届出をいただくことで「自衛官及び自衛官候補生の募集」案内等が届かないよう対応しているところです。
一方、お子様へ届いた郵便物は自衛隊大阪地方協力本部が行う「陸上自衛隊高等工科学校の生徒募集」に関するものだと推察されます。こちらは、住民基本台帳法第11条第1項に基づき、住民基本台帳の一部の写しの閲覧請求によってなされたものであることから、自治体に裁量の余地はなく提供する情報を除外することはできないものとなっております。
つきましては、届出対象者の年齢を引き下げることについて、貴重なご要望を頂戴したにも関わらず、残念ながらご期待に沿うことが叶いません。ご理解のほどよろしくお願いいたします。
関係課
市民窓口課
ご意見
幼稚園の副食費について(10月)
こんにちは。
幼稚園の副食費についてです。
富田林市では、小学3年生以下の子どもを第1子とした第3子以降の子どものいる世帯の負担軽減のため、食材料費の副食費分について助成しています。
我が家は年少が1人おり、小学生2人いてますが小2と小5のため当てはまりません。
小3以下にしているのはなぜでしょうか?
もっと大きくなると食材費がかかるため学年を区切らず第3子以降を助成していただくと大変ありがたいです。
検討をお願いします。
回答
幼稚園の副食費の多子世帯の考え方については、国の制度として基準が定められており、これに基づき市は対象者に助成しているところです。
ご提案の、学年を区切らず第3子以降についても助成の対象にすることは、保護者の負担軽減に繋がるものと認識しておりますが、このような施策を実現するためには、市独自で新たな財源を確保する必要があり、本市では今のところ実施できていない状況でございます。
昨今、物価高騰が続く中で、子育て世帯の負担軽減は重要な課題であることから、子育て支援施策の拡充については、引続き検討してまいりますので、ご理解くださいますようお願い申し上げます。
関係課
こども育成課
ご意見
余ったごみシールについて(10月)
こんにちは。
ゴミ袋に貼るシールについてです。
毎年大量に余ってしまいもったいないなと感じています。
以前市役所に問い合わせをした際には捨てるか市役所に持ってきてくださいとのことでした。
せっかくゴミの量を減らしているのにゴミになってしまうのがつらいです。
以前は還付されていたと聞きました。
それが無理ならせめて期限は書いてありますがいつまでも使えるというようにするのはだめでしょうか?
何か捨てる以外に対策を練っていただけるとありがたいです。
回答
ごみ袋にシールを貼って排出していただく制度につきましては、各ご家庭のごみの排出量を抑制するためのもので、本市を含む河内長野市、大阪狭山市、太子町、河南町、千早赤阪村の6自治体共同で運用しており、各世帯の人数に応じて決められた枚数をお配りしております。このごみシールの使用期間は2年間としており、毎年ごみの排出を一定量に抑制することを目的として期限を設けております。
また、余ったシールにつきましては、ごみシール制を実施する近隣自治体とも情報を共有するとともに、廃棄を少しでも少なくする方法について協議してまいりたいと考えますので、何卒ご理解を賜りますようにお願いいたします。
関係課
環境衛生課
ご意見
学校の着衣水泳について(10月)
こんにちは。
学校の着衣水泳についてです。
小学校のプールが外部に委託されたことにより着衣水泳がなくなりました。
毎年ニュースで見る水害事故は後を絶ちません。
そのため着衣水泳は年に一度はしてほしいです。
検討をよろしくお願いします。
回答
本市は、これまで学校水泳学習において、自身の安全を守るための学習として、「着衣水泳」や「水の怖さを知るための座学による学習」を進めてまいりました。現在、委託事業所での水泳学習においては、施設管理上、着衣での入水は難しい状況にありますが、毎年のように痛ましい事故が起こっていることも事実でございます。今後、まずは、委託事業所や専門の方の意見も参考にしながら、事故を未然に防ぐための学習や、事故にあったときの対処法等、体験を通して学ぶことができるような「安全水泳学習」を実施していけるよう打ち合わせを進めていきたいと考えております。
関係課
教育指導室
ご意見
老朽家屋について(10月)
とある木造の建物の状態が心配です。長らく人の出入りも見られずどのように管理されているのかも不明ですが、老朽化が深刻でいつ崩壊してもおかしくないように感じます。前の道からでも外壁が崩れかかっているのが見えます。また、前に積んである木材にタバコでも捨てられたら大きな火事にもなりかねません。
子どもたちが通学で利用する道であるため、とても不安です。所有者が判明しているのであれば、建物の修復及び周囲の木材の撤去等お話をして頂くことは出来ないでしょうか。
お忙しいところ恐れ入りますが、ご対応よろしくお願いいたします。
回答
ご報告いただきました木造家屋の状況について、現場確認いたしました。
ご心配の通り、老朽化による外壁等の崩落の恐れが見受けられましたので、直ちに法令(建築基準法)上の指導等の権限を持つ大阪府に状況を報告し、所有者に対する指導を依頼しているところです。
また、道路付近に堆積している木材につきましては、隣接土地の所有者に対し、水路敷き上の私物を撤去するよう直接指導しております。
本市としては今後も引き続き状況を注視してまいります。
関係課
都市計画課、道路公園課
ご意見
介護サービスにおける駐車場について(10月)
府営住宅に住んでいる高齢者の家族ですが、訪問介護や看護などの人が駐車するスペースがなくなることを受けて、介護等のサービスの提供が難しくなるケースがあり母や周囲の方々も困惑されている様子です。
業者側も1,2件のために借りてまでサービスできるか?など対応に苦労されていると聞きます。コインパーキング等も常時空いているわけでもなく、母たちが個人で借りる経済的余裕もないかたもいらっしゃり、今後の生活に支障をきたしそうです。市としては公共の住宅にお住いの高齢者に対する訪問サービスに係る駐車問題について改善などは考慮できないでしょうか?
例えば市で駐車場を借りて各業者が事前登録制で使用するとか検討できないものでしょうか?
回答
訪問介護や訪問看護といった、訪問による介護・医療サービスは、高齢者が住み慣れた自宅で、自分らしく自立した生活を続ける上で不可欠なものであり、社会的な重要性も年々増しております。
こうした事業者が円滑にサービスを提供するためには、駐車場所の確保は重要な問題であり、継続してサービスを必要とされているご利用者様、ご家族様のご心配についてはお察しいたします。
こうした実情も鑑み、訪問看護、訪問リハビリテーション、訪問介護等のサービス提供に使用する車両が、訪問先に駐車場所がないために駐車禁止場所に駐車せざるを得ない場合は、状況に応じて警察署長の駐車許可を受けることが可能となっており、その手続きの簡略化も図られております。
市としましては、介護事業者向けの研修会等の機会を通じて、こうした情報の周知に努めてまいります。
関係課
高齢介護課
ご意見
スマホ講座について(10月)
何とか時代についていこうと中央公民館の「スマートフォンの使い方基礎講座」に申し込みましたが、いつも抽選に漏れます。
予算の問題など諸問題はあると思いますが、公民館のスマホ講座の増設・増員をお願いします。
回答
インターネット・携帯電話の普及に伴い、経済・社会・生活のあらゆる場面で情報化が進展する一方で、スマートフォンなど情報端末を使える人と使えない人による情報格差が問題となっています。
公民館としましては、情報格差の解消に向け、スマホ講座を度々実施しております。
スマホ講座をはじめ、公民館の講座には、市民の皆様からたくさんのお申込みがあり、参加が抽選となる講座も多数あります。
公民館では、スマホ講座を今後も継続して実施していく予定ですので、『公民館だより』や市のウエブサイトなどをご覧いただき、お申込みください。
関係課
公民館
ご意見
通学時の自転車走行について(10月)
11月から自転車の交通ルールが厳しくなりますが通学時、学生さんの自転車の運転について、学校から注意を促してもらいたいです
私は通勤で自転車を使っているものですが、学生の通学時の自転車が危ない運転で困っています
特に次の3点について注意してもらいたいです、
1.反対車線を走行している(正面衝突しそうになる)
2.スマホを見ながら運転している
3.友達どうし横に並んで、しゃべりながら運転している
この3点がとても危ないです
具体的な場所としては、府道35号線(PL病院の前の道 平尾近く)において、こちらは北行きで学生は南向きで結構なスピードで走行してきて接触しそうになります
どこの学生かはわからないので、堺市と富田林市に送らせてもらいました
ぜひ対応よろしくお願いします
回答
この度は、自転車通学に係る危険な状況について、ご迷惑をおかけしていること、また、ご心配いただいていることについて、ご連絡いただき、誠にありがとうございます。
今回お示しいただいている地域での出来事につきましては、進行方向等の状況から本市立学校に自転車通学している生徒が直接該当する可能性は低いと考えておりますが、一方で、本市立学校にも自転車通学している生徒がおりますことから、今回の事案と同様に危険な走行状況があることも想定されます。
本市教育委員会といたしましては、これまでも各校において自転車通学について安全指導等を実施しているところではございますが、今回ご連絡いただきました状況を踏まえまして、再度、学校に対して自転車の乗り方を含めた交通ルールの徹底について指導してまいります。
今後とも、本市教育行政及び本市立学校教育へのご理解とご協力をいただきますよう、どうぞよろしくお願いいたします。
関係課
教育指導室
ご意見
だんじりに関する苦情について(10月)
秋祭りについてお尋ねしたいです。毎年のことなんですが、夜9時を過ぎてもマイクや拡声器で歌ったり掛け声を出したりしていて、太鼓の音も住宅の中まで響いてきます。子どもが寝られず、本当に困っています。連日の練習でここまで大きな音を出す必要があるのでしょうか。もし理由があるのであれば、納得できるように市から説明していただけないでしょうか。
秋のいい季節なのに、毎晩どんちゃん騒ぎのような状態で、正直とてもつらいです。窓を閉めても低い音が響いてきて、家の中でも落ち着けません。「祭りだから仕方ない」で片づけられる問題ではないと思っています。
だんじり自体を否定したいわけではありません。太鼓や笛など、お祭りらしい音は理解できます。ただ、マイクや拡声器、ラッパなどの大音量は本当に耐えがたいです。小さい子どもが夜中に起きてしまう家庭もありますし、体調にも関わってきます。
また、本番の日には交通規制でバスが遅れたり、朝から大きな音が遠くまで響いたりと、生活にも影響が出ています。地域の祭りだからこそ、みんなが気持ちよく過ごせる形にできないものでしょうか。
各自治体で練習の仕方や音の出し方が違うと聞きましたが、音量や練習時間などについて、市として統一したルールを作っていただきたいです。節度を持って楽しめるお祭りにしていただけたらと思っています。
(※本件に関しては、同様の趣旨の問い合わせが複数寄せられています)
回答
日頃は、本市政の推進にご理解、ご協力いただきありがとうございます。
お問い合わせの件につきまして、回答いたします。
だんじりの祭礼行事は、私たちの暮らしと歴史に深いつながりがある伝統行事として、地域の町会・自治会等が自主的かつ主体的に企画・運営されており、市としましては、祭礼行事を指導出来る立場にはございません。
しかしながら、今後も行事を継続していくにあたり、騒音などについては、周辺にお住まいの市民の皆様のご事情や心情にも配慮していただくことが必要と認識していることから、これまでも町会・自治会の代表者が加入されている富田林市町総代会より、各町会・自治会長に周辺にお住まいの市民の皆様への配慮をお願いしているところです。
ご指摘の内容につきましては、町総代会にお伝えし、周辺住民へご配慮いただけるよう継続し働きかけてまいります。
関係課
人権・市民協働課、環境衛生課、道路公園課
ご意見
寺内町の景観、若松団地、巡回観光バスについて(11月)
とある物件の外観デザインが寺内町のイメージにそぐわないものになっているので心配です。また、他の土地も外観は白壁等ではないのでしようか。
このような寺内町の中のこれから建築する物件は、市役所がちゃんとデザインのチェックをするのでしようか。やったもん勝ちで、作ってしまったからしようがない、というような状況は避けてほしいです。
また、市に寄贈された東奧谷家住宅は、どうなるのでしようか。北側もちゃんと修理をしてください。今現在は、崩れ落ちており、外観に問題ありです。早く公開してほしいです。公開に時間がかかるなら、せめて北側をちゃんと修理をしてほしいです。
その他、富田林駅の周辺は古民家が壊され、普通の民家になっておりますが、若松町も指定したらどうでしようか。もったいないです。
巡礼街道は、本当に巡礼のような感じで石畳に改修したらどうでしようか。今現在、丁度、工事中のようですし。
因みに、大阪府富田林市若松町1丁目の若松団地ですが、全て滅失し、寺内町に隣接している貴重な土地なので、団地ではなく、全て寺内町の観光地化に繋がるようないい雰囲気の大規模施設を作ったらどうでしようか。
若松町1丁目4のほうと併せて、寺内町の観光に繋がるような使い方にしてほしいです。
団地はやめてほしいです。貴重な土地がもったいないです。
サバーファームと寺内町、滝谷不動尊のセットのツアーを組んでほしいです。もしくは、無料移動巡回移動バス等をして、観光客を増やしてほしいです。
宜しくお願い致します。
回答
富田林町の重要伝統的建造物群保存地区内で建築する物件につきましては、伝統的町並みと調和するように建物ごとにそれぞれの施主と市が協議しています。
保存地区内での新築住宅の建築や中古物件の立て替えにあたっては、計画の段階で事前にご相談いただき、屋根瓦や外壁について色や材質を確認するなど、施主や設計業者と対面やメールでのやり取りを何度もかわし、外観が保存地区内の町並みに調和する仕様となるまで協議を継続しています。
市に寄贈された東奥谷家住宅についても、町並みを形成する大型町家の一つであり、令和7年度には市場サウンディング調査、建物調査を実施し、富田林寺内町の町並みが後世に継承されるように持続可能な維持管理を目指しています。
寺内町絵図に描かれている保存地区については中世末期の成立以来の町割りが良く残る、12.9haを保存地区の範囲とし、地区内にあるおよそ200棟を「伝統的建造物」として特定していますが、ご意見の場所は地区外となっています。道路環境の整備につきましては富田林駅南地区の整備の際に城之門筋や旧杉山家住宅周辺をカラー舗装するなどの美装化を行い維持管理に努めており、新たに拡大する予定はございません。
若松第12住宅1棟につきましては、既に用途廃止を実施しており、跡地への新たな市営住宅の建設は予定しておりません。また、跡地の活用につきましては、今後、検討してまいります。
市内観光スポットを周遊していただく仕組みにつきましては、市内観光促進にとって有効な手法だと考えております。今後、来訪者のニーズが高い周遊セットツアーなどについては民間の旅行事業でのツアー造成も含めて検討していきたいと考えております。また、定期的な観光巡回バスを市が実施することについては、対費用効果等を踏まえますと現状では困難であると考えます。引き続き、頂きましたご意見も参考としながら、市内観光周遊の促進について、取り組みを進めてまいります。
関係課
文化財課、住宅政策課、商工観光課
ご意見
HPVワクチン接種について(11月)
男子のHPVワクチン接種についてご意見をお伝えしたく、メールいたしました。
現在、男子のHPVワクチン接種は自費となっており、特に9価ワクチンの場合は約9万円と高額で、子育て世代にとって大きな負担となっています。未来の健康を守るために接種したいと考えても、費用面で躊躇せざるを得ないご家庭が多いのが現状だと思います。
HPVは将来、子宮頸がんをはじめとするさまざまな疾患の原因となり得るウイルスであり、男女問わず予防していくことが重要です。
未来の子どもたちを守り、HPV関連疾患の減少・根絶を目指すためにも、男子へのHPVワクチン接種について、公費での実施、または助成制度の創設をご検討いただけないでしょうか。
市としてご検討いただけますと大変ありがたく存じます。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
回答
ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症は、子宮頸がんをはじめとした病気の発生に関わっており、HPVワクチンは、子宮頸がんを起こしやすい型であるHPV16型・18型などの感染を防ぐことができます。ワクチンには、2価ワクチン(サーバリックス)、4価ワクチン(ガーダシル)、9価ワクチン(シルガード9)の3種類があり、現在、国はHPVワクチンの定期接種(国の費用負担あり)については小学6年生から高校1年生相当の女子を対象として定めております。一方で、男子については定期予防接種の対象となっておらず、おっしゃる通り、特に9価ワクチンを任意接種(自費)で接種する場合には、3回で9万円前後の費用が必要であり、子育て中のご家庭では大きな費用負担が発生している状況であると認識しております。
ご要望のありました男子を対象としたHPVワクチンの費用助成につきましては、現在、厚生労働省での定期接種化に関する議論が進められているところです。定期接種以外の任意予防接種につきましては、健康被害が起きた場合の対応も含め、その有効性と安全性について慎重に検討する必要があり、本市においては、引き続き定期接種を中心とした予防接種施策を進めてまいりたいと考えております。ご理解の程よろしくお願いいたします。
関係課
健康づくり推進課