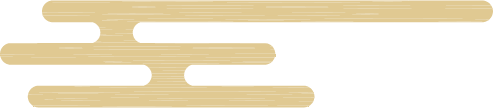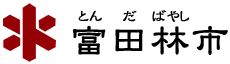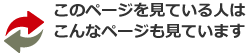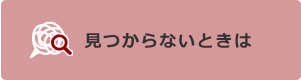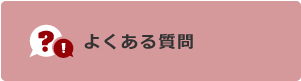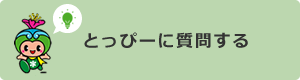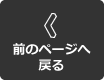令和7年度施政方針
PDFファイルは次のリンク先よりダウンロードしてください。
はじめに
本日ここに、令和7年度(2025年度)の一般会計予算をはじめとする各議案のご審議をお願いするにあたりまして、市政運営に関する私の基本的な考え方と施策の概要を申し上げ、議員並びに市民の皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。
初めに、私は、本年は3つの節目の年であると考えています。一つ目に、戦後80年。二つ目に、阪神・淡路大震災から30年。三つ目に、大阪・関西万博の開幕であります。
誰もが平和で幸せな暮らしを享受できる権利を持っていること、またそのために人々は支え合いながら様々な困難を乗り越える力を持っていること、そして戦争と震災の経験を踏まえつつ、より良い未来をめざして私たちが生きる大阪・関西の魅力を世界中に広げていくこと、以上3つの事柄をしっかり踏まえ、今年度の市政運営にあたっていきたいと思います。
それでは、今年度特に進めていきたいと考えております主な施策や取組について申し上げます。
目次
3.人とまちが賑わい、地域の魅力と可能性を開くまちおこし・地域おこしを推進
4.行財政改革・市役所改革の継続と市民サービス向上の両立を追求
1.すべてのこどもを、みんなで応援するまちづくり








国においては、昨年5月に、こども大綱に基づくこども政策の具体的な取組を一元的に示す「こどもまんなか実行計画」が策定されるとともに、「子ども・子育て支援法」の改正など、こども本人への支援とともに、こどもを育てる家庭への支援の拡充や体制強化が進められています。本市では、これまで、富田林版「こどもまんなか社会」の実現に向けて、こどもまんなか応援サポーター宣言を行い、「見守りおむつ定期便」や「こども誰でも通園制度」など府内においても先進的な施策を実施していますが、今年度におきましても、本年3月策定予定の「第3期子ども子育て支援事業計画」に基づく施策の推進をはじめ、子育て世帯等に寄り添った様々な取組を展開してまいります。
まず、市民全体でこどもの権利を理解し尊重する、こども一人ひとりの成長を守り、こどもの最善の利益を優先する社会の実現に向け、こどもたち自身が条例検討に参加する「こども会議」の開催をはじめ、こども版パブリックコメントの実施やシンポジウムの開催など、「こどもの権利に関する条例」の制定に向けた取組をさらに進めます。また、条例制定後に、こどもの権利の視点や要素を取り入れたこども・子育て施策を総合的かつ計画的に推進するため、「こども計画」の策定に取り組んでまいります。加えて、子育て情報にアクセスしやすい環境づくりとして子育て応援アプリの運用を開始します。
子ども食堂については、本年1月時点で市内9小学校区に開設され、広がりをみせています。今後も、すべての小学校区での開設を目標に運営団体を支援してまいります。また、運営補助金を見直し、食の提供を通じた居場所づくり等を促進するとともに、食材等の確保が難しくなっている生活困窮世帯や子ども食堂を運営する団体を支援するため、昨年度に続き市民向けのフードドライブを開催し、「もったいないをありがとう」に変える取組を推進します。
本市のこども・子育て施策の拠点として東西に整備を予定している「(仮称)こども・子育てプラザ」につきましては、本年3月策定予定の「(仮称)こども・子育てプラザ(東施設)整備基本計画」並びに「金剛中央公園・多機能複合施設等整備基本計画」に基づき、整備を進めてまいります。
次に、児童虐待防止対策についてです。令和4年6月に本市において2歳児の尊い命が失われるという事件が発生しました。このような事件が二度と起きないよう、市職員や関係機関等を対象とした児童虐待防止研修を引き続き実施するとともに、職員の育成、アセスメント力の向上、関係機関との連携強化など、市が一丸となって児童虐待防止に取り組んでまいります。
また、妊娠期から出産・子育て期にわたり、個々の家庭に応じた切れ目のない支援を行うため、昨年7月、母子保健と児童福祉の一体的な相談支援を行う機関として、「こども・子育て応援センター」を設置しました。今年度は、新たに市内4か所に「地域子育て相談機関」を設置し、これらの機関が保育所や学校園、民間団体等と連携を図りながら、継続的な子育て家庭への支援に努めてまいります。さらに、発達に課題のある児童への支援としまして、心理相談員が「地域子育て相談機関」へ出向き、発達相談を実施します。加えて、助産師等による産後の体調管理と育児をサポートする「産後ケア事業」につきまして、医療機関での「宿泊型」と「日帰り型」に新たに「訪問型」を追加し、より利用しやすい体制としてまいります。
次に、市立幼稚園・保育所の今後の方向性についてです。まず市立幼稚園で先行実施しております「3年保育」などの取組を継続したうえで、2年続けて3歳の新入園児が10人未満となった場合に、翌年以降の園児募集を停止する措置をとることで、適正な集団規模の幼児教育・保育環境を確保してまいります。これにより複数の市立幼稚園が休園となることも想定されますことから、まずは令和10年4月の受け入れを目途に、市立認定こども園の設置について、既存の公共施設の活用も含めまして検討を進めてまいります。
また、保育所等については、引き続き年間を通じた待機児童の解消をめざし認可保育施設の整備補助を行うとともに、保育ニーズを見極めながら適切な保育の受け皿確保に努めてまいります。学童保育については、保育ニーズが増加しており、多人数となったクラスの分割に向け整備を行い、集団規模の適正化に取り組んでまいります。
次に、学校教育の充実についてです。令和2年度に国のGIGAスクール構想の推進にあたって導入された1人1台端末が更新時期を迎えますことから、新たな端末を市立全小中学校に配備し、ICTを活用した教育の充実を図ってまいります。小学校では、教職員の負担軽減と、より充実した水泳指導の実施に向けて、昨年度に取り組んだ水泳指導の民間委託について、モデル事業をさらに拡大実施してまいります。併せて、小金台小学校・明治池中学校が「彩和学園」として取り組んでいる小中一貫教育校の取組成果と課題をもとに、他の中学校区へも取組を拡大し、さらなる充実に努めてまいります。学校図書館では、新たにシステムを導入することにより、蔵書管理や貸出・返却作業の効率化を図るとともに、貸出冊数ランキングなど、こどもたちに興味をもってもらえるような機能を活用し、読書活動の推進を図ってまいります。さらに、戦後80年の節目を迎えるにあたり、学校における平和教育の充実に努めてまいります。
国においては、不登校やいじめ、貧困などの問題に加え、コロナ禍や社会構造の変化を背景として、こどもたちを取り巻く環境が複雑化・多様化する中、改めてこどもの視点に立った教育の推進が求められています。様々な理由により学校に行きたくても行けないこどもたちへの支援は、本市においても喫緊の課題であり、解決に向けた施策の実施は、重要性を増しています。そのような中、日頃からの状況把握を通して、課題を早期発見し速やかに対応できるよう、スクールソーシャルワーカー等の専門人材の積極的な活用を進めてまいります。また、一人ひとりのこどもに合った学びの場を確保し、こどもたちが安心して過ごせる居場所を提供するために、引き続き教育支援センターや校内に設置しているスペシャルサポートルームの充実に努めてまいります。さらに、学校に慣れない新1年生の学校生活をサポートする「エプロン先生」を配置するとともに、引き続きフリースクールへ通うこどものいる家庭への経済的支援に取り組んでまいります。
学校給食では、地元産の食材を活用した食育や地産地消を推進するため、若者会議提案の地場産給食の魅力を伝える動画制作に取り組むとともに、大阪・関西万博の参加国の料理にちなんだ「万博献立」を実施してまいります。加えて、国の重点支援地方交付金を活用し、昨年度に引き続き学校給食への支援を実施してまいります。
小学校・幼稚園給食においては、食物アレルギーに対応した給食の提供を継続するとともに、小学校の給食配膳室に空調設備を設置してまいります。また、中学校給食においては、現在の希望選択制から全員給食への移行等、実施方法も含め、こどもたちにとって望ましく持続可能な給食のあり方について、本年3月策定予定の「中学校給食のあり方基本方針」に基づき、早期の実現をめざしてまいります。
「ふれあい給食」については、学校給食への理解を深めていただけるよう、地域の皆様とこどもたちが一緒に食べる給食交流や、地域の方々の交流の場とするなど、提供機会の充実に努めてまいります。
安心安全で快適な学習環境の向上を図るため、 今年度は、市立全小中学校の屋内運動場へのエアコン設置に向けた設計を行うとともに、老朽化した学校トイレや屋内運動場トイレの洋式化整備を引き続き進めてまいります。
余裕教室等を有効活用した「地域総合拠点・みなよる」は全16小学校区において整備が完了しました。今後は地域交流の充実や多様な地域活動の支援となるよう努めてまいります。
さらに、今年度も「こどもまんなか夏休みイベント」を実施し、こどもたちが楽しく学び、成長する機会を提供してまいります。
また、こどもたちが万博会場で国際社会の未来イメージを感じることで、将来の夢や希望を膨らませることができるよう、大阪府が実施するこども招待事業と連携し、市立小中学生が安全に会場まで移動できるよう観光バスを確保するとともに、その費用についても国の重点支援地方交付金を活用し支援してまいります。加えて、大阪府のこども招待事業と同様の対象者に市独自の無料招待事業を実施してまいります。
2.すべての市民の暮らしを支える住民福祉の増進














まず、この間取組を進めてきた増進型地域福祉についてです。人と人、人と地域の「つながり」が希薄化し、複雑・複合的な支援ニーズや孤独・孤立問題の深刻化が懸念される中、「地域総合拠点・みなよる」を中心に市内16小学校区で「福祉なんでも相談窓口」を定期的に開設するとともに、多様な地域活動の担い手と専門職等が連携しながら個々の状況に寄り添った伴走支援に積極的に取り組んでまいります。さらに、行政、NPO法人、社会福祉法人、市民団体、民間企業等による官民連携体制の基盤となる(仮称)増進型地域福祉プラットフォームを構築し、様々な課題を抱える潜在的な対象者の気づきと支援機関へつなぐセーフティネットの拡充、孤独・孤立対策に関する機運醸成を図るための啓発活動を行うなど、包括的な支援体制の整備に向けた取組をより一層進めてまいります。
また、校区担当職員が校区交流会議に引き続き参加しながら、行政情報の提供や地域課題を共有し、地域と行政をつなぐ役割を通じて、全市レベルでの課題解決に向けた施策の検討につなげるなど、行政や社会福祉協議会、福祉の専門職等が地域住民と力を合わせて、一人ひとりの幸せと地域の理想の実現を追求する「増進型地域福祉」を推進してまいります。
障がい者福祉では、障がいのある人が地域で安心して暮らせるよう、障がい者基幹相談支援センターを拠点に、引き続き相談支援に努めるとともに、これまで関係機関の連絡会議として開催してきた「障がい者雇用会議」を、障がい当事者やその家族、雇用主である事業者、医療関係者や学識経験者、福祉事業所やハローワークなどの関係機関が参画する会議へと強化することで、さらなる障がい者就労、障がい者雇用環境の推進を図ります。加えて、市としても障がい者の仕事創出の取組を強化することにより、「障がい者千人雇用」を進めてまいります。
また、様々な災害対策に取り組む中、外見では分かりにくい聴覚障がい、視覚障がいなどがある人は、避難所などにおいて情報が届きにくい実情があります。自ら障がいがあるということを周囲に伝え、支援が必要であることを理解してもらうことができる「災害時障がい者支援用スカーフ」を各避難所へ配備するとともに、重度の聴覚障がい、視覚障がいがある人に配布することにより、安心して避難できるよう努めてまいります。
これらの施策の推進を通じて、障がい者理解の促進・啓発に努めながら、障がい者差別の解消並びに障がいのある人が安心して暮らせる地域共生社会の実現をめざしてまいります。
高齢者福祉については、「高齢者保健福祉計画及び第9期介護保険事業計画」に基づき、地域包括ケアシステムの深化・推進に取り組んでまいります。その中で、認知症施策の推進として、認知症の理解を深め、認知症を自分事として考えるきっかけとなるようシンポジウムを開催するとともに、「認知症ケアパス」概要版を全戸配布してまいります。
令和2年度にスタートし、延べ2,000人を超える参加者と約30か所の事業者の協力により進めてまいりました、介護予防・健康ポイント事業「あるこっと」については、今年度も継続しながら、これまでの実績データの分析と事業の効果検証結果をまとめてまいります。
健康づくりの推進については、本年3月策定予定の「第3次健康とんだばやし21・第2次食育推進計画・第2次自殺対策総合計画」に基づき、胎児期から高齢期に至るまでのライフコースアプローチの視点を取り入れながら、地域・行政・関係機関等が一体となり、誰もが安心して健やかに暮らせるまちづくりに取り組んでまいります。加えて、様々な感染症危機に幅広く対応できる社会づくりをめざして、昨年7月に抜本的に改正された国の新型インフルエンザ等対策政府行動計画に基づき、本市においても、現行の「行動計画」の改定に取り組んでまいります。また、帯状疱疹の発症及び重症化予防に効果のあるワクチンの定期接種を実施し、接種費用の一部を公費助成いたします。
また、受診率向上に向けたピンクリボン運動等の「がん検診受診率向上集中キャンペーン」の取組や、節目の方への個別勧奨通知に加え、新たに20歳の方にがん検診と健康診査等の通知を行い、がんの早期発見と健康意識の啓発を図るとともに、がんミニドック・レディース検診の日曜日開催や「がんパック検診」を継続し、受診しやすい環境づくりに取り組んでまいります。
次に、防災・減災対策の強化、市民の安心と安全を守るまちづくりについてです。昨年元日、能登半島において最大震度7の大地震が発生し、石川県を中心に大きな被害をもたらしました。また、昨年8月には、南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)が初めて発表されるなど、大規模地震がいつどこで起ってもおかしくない状況の中、本年、阪神・淡路大震災から30年となることを受け、これまでの教訓や経験を踏まえた総合的な防災対策を進めることで、より一層「災害に強いまちづくり」を推進してまいります。
具体的には、地域防災力向上の取組として、防災リーダー養成講座やジュニア防災リーダー養成講座を継続して実施するとともに、地域防災訓練への支援、「とんだばやし発見出前講座」に外国人市民向けのメニューを新たに加えるなど、積極的に進めてまいります。訓練の支援や出前講座においては、講師として、防災リーダー養成講座修了生等の地域人材の積極的な登用や、ボランティア団体と連携し、より効果的な防災啓発ができるよう工夫してまいります。また、自主防災組織については、活動の活発化や備蓄の充実を図るため、補助制度を拡充してまいります。さらに、イベントや催し等を実施する団体に対し、AEDの貸し出し事業を行ってまいります。
改定から6年が経過する「地域防災計画」につきましては、最新の知見や災害の教訓、女性や要配慮者等、多様な視点を十分に取り入れ、より実効的な計画としてまいります。また、令和4年度から進めている「災害時学校利用計画」については、9校での策定が完了し、引き続き避難所に指定している市立全小中学校で策定してまいります。
次に、避難環境の確保としまして、計画的な物資の備蓄とともに、民間事業者・団体との災害支援に係る協定締結について継続して進めてまいります。特に、災害時のトイレ環境については、公共下水道整備区域内で指定避難所になっている学校施設へのマンホールトイレの整備を順次進めており、令和9年度を目途に、市内小中学校及び高等学校を含めた合計26校に設置してまいります。また、マンホールトイレ整備の予定がない避難所17か所においては、新たに衛生的に使用できる洋式の簡易トイレを凝固剤と合わせて備蓄してまいります。さらに、全国の加盟自治体による災害派遣トイレネットワークプロジェクト「みんな元気になるトイレ」に参画し、クラウドファンディングを活用して、トイレトラックを導入いたします。加えて、新たに駅前など多くの人が集まる場所に、スマートフォンで二次元コードを読み取ることで、避難所の場所や防災情報を把握できる表示板を設置してまいります。
次に、災害対応の拠点となる新庁舎の整備については、免震構造を採用することで、庁舎内の被害を最小限に抑え、被災者支援を含む行政機能をストップさせない、災害に強く安心安全な庁舎となるよう、現在、鋭意進めており、耐震性能の低い庁舎北館部分の除却を完了し、今年度より本格的に新庁舎建設に着手してまいります。また、昨年にご寄贈いただきました災害用発電機を活用し、大規模災害時に医療救護の拠点となる保健センターの防災対策を進めてまいります。
児童館については、既存施設の耐震性能不足に対応する工事を実施するとともに、工事期間中の一時移転を行い、利用者等の安全の確保に努めます。また、耐震工事完了後、新施設「(仮称)こども・子育てプラザ」が完成するまでの間は、既存施設において事業を継続してまいります。
防犯対策につきましては、本年3月、市設置型防犯カメラ115か所の更新及び主要幹線道路交差点等12か所への増設を完了するとともに、今年度より、町会・自治会による防犯カメラ整備に対する補助制度の充実を図ってまいります。併せて、富田林警察署や市内の金融機関等と連携し、特殊詐欺被害の未然防止と被害の拡大防止に努め、引き続き自動通話録音装置の無償貸与を実施するとともに、新たに音声発生器を用いたATM付近での啓発や、特殊詐欺被害防止サポーター認定制度の創設に取り組むなど、地域防犯力の向上に努めてまいります。
加えて、「犯罪被害者等支援条例」に基づき、国や大阪府、警察、支援団体等と連携しながら、経済的支援や日常生活への支援に取り組んでまいります。
都市基盤の整備といたしまして、引き続き通学路の整備や道路、公園等の適切な維持管理に努めてまいります。また、粟ケ池共園遊歩道の整備を進め、安全快適に利用いただけるよう努めるとともに、「ひとやすみベンチ寄附制度」の積極的活用についてもPRしてまいります。加えて、大規模災害時における緊急輸送路並びに広域的な道路ネットワークとなる「八尾富田林線」や「大阪南部高速道路」の早期事業化に向けて、引き続き関係自治体と連携しながら要望等を行ってまいります。
また、下水道事業では、令和8年度の汚水整備の概成をめざして、公共下水道や公共浄化槽の整備、普及に取り組むとともに、「ストックマネジメント計画」に基づき、効果的な下水道施設の管理運営に努めてまいります。
次に、効果的な空き家対策を進めるため、空き家の実態調査を実施するとともに、「空家等対策計画」の改定に取り組んでまいります。また、民間住宅の耐震化を促進するため、「耐震改修促進計画」に基づき、耐震診断、耐震改修補助を引き続き実施するとともに、耐震性のない木造住宅の除却補助につきまして、限度額を引き上げてまいります。
交通政策につきましては、「富田林市地域公共交通計画」に基づき、「すべての市民が安全に安心して快適に移動できるまち」の実現をめざし取組を進めてまいります。特に、レインボーバスにつきましては、金剛自動車株式会社のバス事業廃止を受け、暫定的に東條線の補完運行を行うため、既存の9便から3便に減便して運行しているところです。引き続き、今後のあり方について検討を進めるとともに、東西交通の充実に向けて、南海バス・近鉄バスの乗継割引について実証実験を行ってまいります。また、交通不便地域における移動手段の確保については、彼方上地区において、需要を見極めるため、タクシー車両を活用した運賃割引の実証実験を行うとともに、その他の不便地域においても、引き続き地域が主体となった持続可能な地域公共交通の導入に向けた取組を支援してまいります。
2年目を迎えました金剛ふるさとバスの運行につきましては、本年3月策定予定の「広域版の地域公共交通計画」に基づき、少子高齢化や公共交通利用者の減少、乗務員不足等の現状を踏まえ、将来にわたり持続可能な地域公共交通の実現に向けて取り組んでまいります。加えて、大阪・関西万博の開催に伴い観光客等の急増が予想されることから、駅前などの交通結節点におけるデジタルサイネージの設置や金剛ふるさとバス専用ウェブサイトを導入するなど、利用の促進と南河内の魅力発信に努めてまいります。また、大阪府では、大阪・関西万博のレガシーとして南河内地域における自動運転バスの導入に向けた取組を進められており、実証実験の実施など大阪府と連携、協力して取り組んでまいります。
次に、SDGs(「持続可能な開発目標」)を踏まえた「いのちと人権・環境」を守るまちづくりです。SDGsの実現に向けては、「SDGs未来都市・自治体モデル事業」を鋭意進めるとともに、「第2期SDGs未来都市計画」に基づき、大阪・関西万博を契機に、公民連携、民民連携を一層進めることで、まち全体の「健康」化を促進してまいります。
環境を守る取組として、再生可能エネルギーなど脱炭素化機器の設置補助を継続するとともに、「地球温暖化対策実行計画(第4次)[事務事業編]」が終期を迎えることから、2050年に温室効果ガスの排出を実質ゼロにする脱炭素社会の実現に向けて改定に取り組んでまいります。また、持続可能な森林保全については、国からの森林環境譲与税を活用し、森林境界の明確化等の取組を進めてまいります。
市民一人ひとりの人権が尊重される社会の実現に向け、「第2次人権行政推進基本計画」に基づき、人権教育・啓発活動を推進してまいります。昨年4月にオープンした多文化共生・人権プラザ(TONPAL)においては、生活相談、人権相談、外国人市民相談、女性相談の各種相談事業を実施するとともに、他の相談機関とも連携を図るなど内容の充実に努めてまいります。
人権課題への取組として、近年インターネット上の誹謗中傷や差別等の人権侵害等が後を絶たない状況を踏まえ、本市では、昨年7月に「インターネット上の誹謗中傷や差別等の人権侵害のない社会づくり条例」を施行しました。インターネット上の誹謗中傷等の人権侵害を防止し、市民の誰もが加害者にも被害者にもならないよう相談窓口の設置やインターネットリテラシーの取組を推進してまいります。また、モニタリングの実施も含めた効果的な対応策について検討してまいります。
すべての女性が活躍できる社会の実現に向けて、市の政策・方針の決定過程における男女共同参画を促進するため、審議会等における女性委員の登用率の数値目標40%をめざすとともに、「男女共同参画センターウィズ」では、女性のための悩み相談や無料弁護士相談を引き続き実施し、離婚・DV・貧困など困難な問題を抱える女性への支援に取り組んでまいります。また、男女が共に生きやすい社会をめざし、「第4次男女共同参画計画」の策定に取り組んでまいります。
多様な性を尊重する取組として、性的少数者に対する理解と支援を広げるため、引き続きLGBTQコミュニティスペース「にじいろブーケ」を定期的に開催するとともに、パートナーやこどもなどとの関係を家族として認める「パートナーシップ・ファミリーシップ制度」の促進を図ってまいります。さらに、「LGBTQ・ALLYカンパニー認定制度」を通じて様々な団体と連携を図りながら、社会的理解の促進に向けて取り組んでまいります。
多文化共生のための地域づくりとして、外国人市民との交流イベントを開催するとともに、引き続き「外国人市民会議」を開催し、いただいた声を市政に反映してまいります。
本年は戦後80年を迎えます。昨年12月、被爆者の核兵器廃絶を訴えてきた地道な活動が評価され、日本被団協がノーベル平和賞を受賞し、核兵器のない世界を求める声が高まりました。本市では、戦争を知らない人たちに戦争の悲惨さや核兵器の非人道性を伝え、非核平和の願いを広げるため、この節目の年に、戦争体験者の声を映像に収めるなど、戦争の記憶を後世に残す取組を進めます。また、毎年「親子平和の旅」として、8月6日に開催される「広島平和記念式典」に市民代表を派遣していますが、本年は、8月9日開催の「長崎平和祈念式典」にも派遣してまいります。さらに、「平和を考える戦争展」は、内容を充実して開催いたします。
3.人とまちが賑わい、地域の魅力と可能性を開くまちおこし・地域おこしを推進











大阪・関西万博は、本年4月に開幕します。想定来場者数は 2,820万人、そのうち350万人が海外からの来場者と見込まれています。この絶好の機会に来阪者を本市に呼び込むため、万博会場で開催される「大阪ウィーク」の「みなはれ・たべなはれ・やりなはれ」ブースに出展し、本市出土の文化財の展示や特産品の販売、伝統工芸品のPRを行ってまいります。また、万博最大級のフードコートである「大阪のれんめぐり」にも出展し、富田林商工会との連携により、富田林ええもんブランドの販売や観光PR動画などにより本市の魅力を広く発信してまいります。さらに万博閉幕後には、南河内地域において、スポーツツーリズム事業としてフルーツマラニックイベントが、大阪府の主催で開催される予定であり、本市としても地域の魅力発信のチャンスと捉え、大阪府や近隣市町村と連携・協力し、府内外からの誘客につなげてまいります。
また、デジタルマップ、デジタルスタンプラリー、AR(拡張現実)やVR(仮想現実)の機能を搭載した観光周遊アプリ「とんだばやし とりっぷ」の利用促進を図り、便利で楽しく市内をめぐってもらえるよう環境整備を進めるほか、観光ツアーと一体的にPRすることで、本市への効果的な観光誘客を図ってまいります。加えて、まちの賑わいを創出するため、「じないまち四季物語」や「石川こいのぼり」等のイベントに支援を行うとともに、冬の風物詩である「金剛きらめきイルミネーション」の実施にあたり、協賛金の獲得に努めてまいります。
さらに、産業の振興及び雇用機会の拡大を図るため、市内での新たな立地や事業拡充等を検討する中小企業に対し、企業立地促進制度の活用を促すとともに、協定を締結した市内金融機関等との連携を深め、地域経済の活性化に取り組んでまいります。
併せて、国制度を活用して大学等を卒業した若者年代を対象に、貸与を受けている奨学金の返還支援として市から助成金を支給することで、制度活用を動機とした本市への転入・定住を促進するとともに、市内の中小企業等における担い手確保にもつなげてまいります。
また昨今、物価高騰が長期化していることから、国の重点支援地方交付金を活用し、市民や市内事業者を対象に水道基本料金の2か月減免を実施するとともに、飼料価格等の高騰や鳥インフルエンザの蔓延防止措置により負担が増している養鶏事業者や、燃料費価格の高騰などにより経営に大きな影響を受けている公共交通事業者(バス・タクシー)に対しまして、安定した事業運営に向けた支援を行ってまいります。
次に、「金剛地区の新たなまちづくり」においては、「(仮称)こども・子育てプラザ」を含む金剛中央公園・多機能複合施設の官民連携による整備・運営に向け、事業者の選定を進めてまいります。また、金剛銀座街商店街においては、UR都市機構との連携によりピュア金剛跡の広場整備を進めます。さらに、南海金剛駅周辺においては、南海電気鉄道株式会社、大阪狭山市と連携し、駅周辺のまちづくりについて検討を行うとともに、ウォーカブルな空間づくりの実現に向け、社会実験「OPEN STREET+」の実施や広告付きデジタルサイネージの設置による新たな収入の確保等に取り組みます。また、寺池公園の魅力化など住民主体の取組のさらなる活性化に向けた支援を実施するとともに、昨年包括連携協定を締結しました大阪大谷大学、阪南大学、UR都市機構との4者連携「KLLP(KONGO Living Lab Project)」による学生まちづくりを推進するなど、引き続き金剛地区の再生・活性化に向けた取組を進めます。
農業振興につきましては、「農業振興ビジョン」に定める本市農業の将来像「人と仕事と環境を育む農業都市・富田林」の実現をめざし、担い手の確保や育成、農地の保全など各種施策を推進してまいります。具体的には、地域毎に策定した将来の農地利用の姿を明確化した「地域計画」に基づく取組を進めるとともに、新たな就農者の育成を目的に市内農業者が中心となり運営されている「きらめき農業塾」を引き続き支援してまいります。加えて、本市農産物の代表である茄子・胡瓜をはじめ、農林水産省の地理的表示(GI)に大阪府内で初めて登録され、また、大阪府内のなにわの伝統野菜に認証された「富田林の海老芋」などの特産品の販売を促進するため、万博会場で開催される「大阪ウィーク」や農業祭、マルシェへの出展などを通じて、広く市内外に積極的にPRしてまいります。
昨年より休園している農業公園については、農業振興のみならず観光や地域経済の活性化に資する重要な施設と捉えておりますことから、早期の開園をめざし、関係者との協議・調整を進めるとともに、既存施設の修繕等の準備を着実に行ってまいります。
さらに、老朽化が進む農道、水路、ため池等の農業施設については、適切な改修・修繕を進めるとともに、使われなくなったため池の潰廃(かいはい)を進め、地域農業の振興と安全・安心な農空間づくりに取り組みます。特に、石川に設置されたゴム井堰については、更新を間近に控えたものが複数あり、農業用水の取水に支障をきたし始めていることから、大阪府と連携し、地元に寄り添った支援ができるよう取組を進めてまいります。
また、活力ある地域社会を実現していくためには、市民、町会・自治会、市民活動団体、NPO法人、企業、行政など、様々な担い手がそれぞれの長所をいかし、協働していくことが不可欠です。市民公益活動や協働によるまちづくりを担う人材の育成に取り組む「Mira-ton´(ダッシュ)」を継続するとともに、引き続き「元気なまちづくりモデル事業補助金 チャレンジ・プライド」を実施し、団体の立ち上げや財政基盤の支援を行うなど、地域課題の解決をめざした市民の自主的な活動を支援してまいります。
次に、文化芸術・スポーツをはじめ市民文化活動の充実に向けては、「文化芸術振興ビジョン」の基本方針を実現するため、「子どもと未来プロジェクト」として、音楽、演劇、美術、文学といった文化芸術をこどもたちが体験できる事業を充実してまいります。また、万博会場で開催される「大阪ウィーク」において、「(仮称)南河内LIVE ART EXPO」を本市、河内長野市、大阪狭山市、太子町、河南町、千早赤阪村の6市町村で連携して開催し、多彩で豊かな南河内の文化芸術を発信してまいります。
若者が活躍するまちづくりについて、若者会議が今年度で5期生を迎える中、若者会議OB・OG会「心はいつも富田林」(愛称:こことん)は、富田林の心強い応援団となっています。今年度は、第4期若者会議からの提案を受け、高校生・中学生を対象に、若者の地元愛の醸成を目的としたイベント「夢灯祭(ゆめびさい)inとんだばやし」を開催いたします。
また、昨年度より進めておりますスポーツ活動についての意識調査や市民ニーズの分析に基づき、「スポーツ推進計画」の策定に取り組んでまいります。さらに、熱中症対策として市民総合体育館にエアコンを設置してまいります。
次に、文化財の保存と活用についてです。本市には、史跡新堂廃寺跡や重要伝統的建造物群保存地区である富田林寺内町をはじめとして、富田林の歴史文化を物語る文化財等が多様に存在しています。歴史・文化とともに生き、歩むまちづくりをめざすため、昨年12月に策定した「文化財保存活用地域計画」を推進してまいります。今年度は、富田林寺内町の中核寺院で国指定重要文化財「富田林興正寺別院」について、経年劣化による老朽化がひどく、早急に保存修理工事を行う必要がありますことから、保存修理工事基本計画業務に補助を行ってまいります。また、令和3年度にご寄贈いただきました伝統的建造物の旧東奥谷家住宅の持続可能な維持管理に向けて、サウンディング型市場調査等を実施し、効果的な運営の構築に取り組んでまいります。
図書館では、セルフ貸出機能をもった図書館システムを本年2月に運用を開始し、利用者へのサービス向上と業務効率化を一層図ってまいります。
4.行財政改革・市役所改革の継続と市民サービス向上の両立を追求





経営的視点に立った、効率的・効果的な行財政運営と質の高い行政サービスを持続的に提供していくことを目的に、引き続き全庁を挙げて行財政改革を進めてまいります。計画期間が終了する「行財政経営改革ビジョン」を見直し、「第5期行財政改革プラン」を策定します。また、「選択と集中」の観点から事務事業評価、施策評価により事業の点検・見直しを実施し、効果的に実施計画や予算編成につなげてまいります。また、「補助金等の適正化に関する指針(ガイドライン)」に基づき、より効果的かつ適正な補助金制度の構築に努めるとともに、さらなる見直しに着手してまいります。加えて、新たな歳入の確保並びに市民サービスの向上を図るため公共施設へのネーミングライツを促進してまいります。また、公共施設マネジメントを推進するため、本年3月改定予定の「公共施設再配置計画(前期)」に基づき、個別施設計画の見直し等に取り組み、公共施設の適切な維持管理につなげるとともに、生涯学習施設や教育施設の適正規模、適正配置を含めた公共施設の総量最適化について、引き続き庁内横断的な体制で検討を進めてまいります。
また、西山墓地の適正な維持管理を継続するために空き区画の販売を開始するとともに、富田林霊園は、新規使用者に係る永代使用料の還付率を改定し、霊園の収支の不均衡を改善してまいります。加えて、富田林斎場については、築後30年経過し老朽化が進んでいることから、大規模改修や今後の運営方針について民間活力の導入可能性調査を行い、対応を検討してまいります。
ふるさと寄附金については、さらなる寄附金獲得をめざし、寄附者にとって魅力的な返礼品の開拓に取り組むとともに、企業版ふるさと納税を活用し、地域活性化に資する事業への支援を募ってまいります。加えて、ふるさと寄附金制度を活用し、市内にある私立学校の教育環境の充実を支援してまいります。
次に、「広報とんだばやし」は、市民の皆様への「大切なお手紙」であるとの考え方のもと、親しみやすく読みやすい誌面づくりに取り組んでおり、今年度は、5月号より広報誌の全ページカラー化を行ってまいります。また、公共施設等に設置している「富見箱(とみけんばこ)」や市長へのお手紙、市政懇談会「市長と語ろう!わがまち富田林」並びに市政モニター制度「わがまちパートナー」等、様々な形で届けられる市民の皆様の声を大切にしてまいります。さらに、「聞こえ」に不安を感じている方が安心して市役所窓口をご利用いただけるよう、「軟骨伝導イヤホン」を導入するなど、一層の市民サービス向上に努めてまいります。
次に、組織力の強化として、「人材育成基本方針」に基づき、職員研修の充実を図り、複雑・多様化する行政ニーズに迅速かつ的確に対応できる人材の育成に努めます。また、資格取得に対する助成制度について、より多くの職員が活用できる制度となるよう取り組むとともに、大阪府等との人事交流や企業版ふるさと納税人材派遣型を活用し、組織の活性化を図ってまいります。また、働き方改革の一環として、職員の多様な働き方を支援する観点から、時差出勤や職員の社会貢献活動を応援するとともに、ハラスメントの防止に努め、風通しの良い、働きやすい職場づくりに取り組んでまいります。併せて、今年度は、効率的な事務執行と市民サービスを両立させる視点を持ちながら、開庁時間の短縮について、導入可能性の検討を進めてまいります。
また、「DX戦略」をさらに推進するため、昨年度に引き続き大阪府のデジタル人材シェアリング事業を活用し、専門的な知識を有する外部人材を招聘し、具体的施策への助言や支援などを着実に実行するとともに、生成AI技術を導入し、文書作成や企画立案、調査・分析の補助など、自治体業務の効率化を推進してまいります。加えて、市民サービスのさらなる向上をめざし、窓口業務支援システム「書かない窓口」を導入し、申請手続きの簡略化と、窓口業務の効率化を図ってまいります。さらに、公開型統合型GISを導入し、本市が保有する地理情報の利活用を促進するとともに、住民や事業者が必要な地理情報に容易にアクセスできる環境を整えてまいります。また、基幹系システムについては、国の策定する仕様に準拠したシステムへの移行を進め、引き続き自治体情報システムの標準化・共通化に取り組んでまいります。
次に、広域連携の推進についてです。昨年4月、消防力の強化を図るため広域消防として大阪南消防組合を発足させるとともに、水道事業につきましては、持続可能な事業運営により、将来も安全で安心な水道水を供給するため、本年4月に大阪広域水道企業団と統合いたします。引き続き、様々な分野において、近隣市町村との広域的な連携についての検討を進め、地域全体の活性化に取り組んでまいります。
最後に、本年は5年に1度の国勢調査が予定されており、外国人市民を含む本市常住のすべての世帯に、漏れなく正確なご回答をいただけるよう、事前の広報等に取り組んでまいります。
以上、令和7年度の市政運営にあたっての基本的な考え方、並びに主な施策の概要について述べさせていただきました。その他施策全般につきましては、予算書にお示ししているとおりで、令和7年度当初予算総額といたしましては、
一般会計で、51,932,000 千円、
特別会計で、27,579,593 千円、
公営企業会計で、5,082,712 千円となっております。
一昨年の所信表明以来申し上げていますように、「人口減少」並びに「定常型社会」といわれる時代を迎えた今日、私たちは決して後ろ向きになるのではなく、逆に全国それぞれの地域独自の発展の可能性が高まっている好機ととらえ、富田林の人と地域が持つ価値と可能性に目を向け、その可能性を広げ、新たな価値を生み出していくことで、富田林だからこそ実現できる豊かな未来を皆様とともに力強く創造していきたいと思います。まちは、市民と行政の協働による創造物です。富田林市は、もっともっと良いまちになります。市民の皆様とともに力を合わせ、「人とまちがにぎわい、こどもたちをはじめすべての市民の笑顔があふれる、麗しの富田林」を創っていくために、一つ、ひとつ、未来に向かって、今後とも全力で取り組んでまいりますので、議員各位をはじめ、市民の皆様のご支援とご協力を心からお願い申し上げまして、私の令和7年度施政方針とさせていただきます。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)